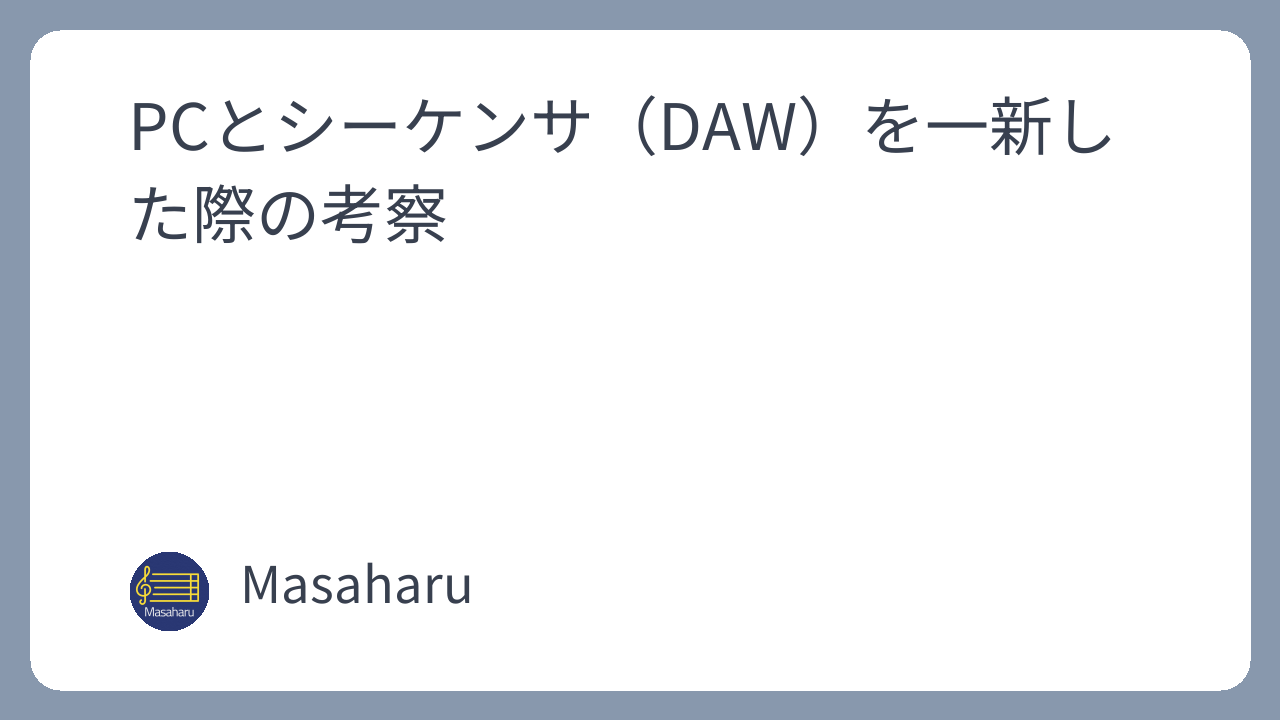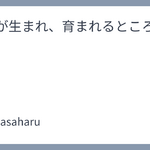※はじめに&注意書き
以下の文章は2007年11月10日に発表されたものです。PCやDAWに関する内容は当時の状況を踏まえたものであり現在とは異なる点があります(ちなみに2025年現在はWindowsでCubaseを使用しています)。
文章の主なテーマは「制作におけるDAWの位置づけ」についてであり、PCやDAWに関する情報の古さはテーマに影響しないという判断のもと、この記事を公開しています。
以上の点を踏まえた上でご覧いただければ幸いです。
◇
以下、2007年11月10日当時の記事を一部加筆修正して公開します。
PCの一新について
さて先月、パソコン周りの環境を一新しました。これまでも「もういい加減に新しくしよう」と何度も思いながらも、「これはこれでまだ使えるんだし……」などと先延ばしにしてきましたが、一念発起、遂に一新と相成りました。
今まで使っていたPC機材やソフト等は既にメーカーによる開発が終了したものが多く、「歩みを止めて化石へと変わり行く機材たち」といった風情を漂わせていました。
ですから、何かデジタル技術的に新しいことを取り入れようとしても、その環境では動作しないというケースが年々増えていました。そのため何かと窮屈な思いを感じていたのが正直なところです。
(ちなみに具体的な一新内容ですが、制作の要であるシーケンサを、これまでのWindows版のLogic 4.8からSONAR 7へと乗り換え、PCはCore2Duo搭載のミドルクラスのものにしました。そしてこれまでの環境では動かなかったために指をくわえていたソフト音源(バーチャル楽器)を今回、晴れて導入したといった具合です。Mac&Logicに戻ろうかという気も少しありましたが、総合的に考えてWindowsに留まることにしました)
そういうわけで、これから環境一新にまつわることを書こうと思いますが、内容としては“できごとや情報”ではなく“感じ思ったこと”を中心にしようと考えています。
さて環境一新の大きな柱は、パソコンとシーケンサ(音楽制作ソフト。DAW)です。今回はそれら「ハードとソフト」の検討を並行して行いました。細かいことを言えば、他にも色々と検討事項があり、実際に導入したものもあったのですが、今回の話の中ではこの二つに絞って取り上げます。
まず最初はパソコンについてです。私の音楽制作で重要な働きをしてくれる、文字通り文明の利器です。このパソコンの中でDAWもバーチャル楽器もその役目を果たすことになるわけですから、言うまでもなく正しく動いてくれないと困る機材です。
はっきり言ってPCに関しては浦島太郎状態でしたので、的確な導入へ向けた段取りは色々と大変でした。
PC関連のハードウェアに関することを学び直しながら、必要な性能を見積もり、その後はネット上でPCショップのセミ・オーダーメイド品を探して回ったり、等々。
しかし今回のことを通じて、Windows OSのメモリ管理方法を中心に改めて勉強できたことは、PCを楽器として扱う者にとっての大きな収穫でした(詳細は専門的なので割愛します)。
そのなかで改めて思ったのは、解らないことをネット検索で調べる際、それが正しいか、もしくは妥当かどうかについて、ついつい「検索結果の表示順位や多数決」で計ってしまおうとすることは想像以上に大きな罠になり得る──ということでした。
肝心なのは「その答えの前提となっている状況」を正しく把握することであり、また論拠となるものの存在とその信憑性・信頼度であり、結局は当たり前のことに行き着くものだなと痛感しました。
例えばネット上での常識や知恵が逆に大きな落とし穴だったというケースがありました。ネット上でよく目にするOSの基本的な推奨設定ですら、現在では却って性能を低下させかねないものだと解った例もありました。
ちなみにその罠を回避した先の真の回答は、皮肉にもマイクロソフトが一般公開している情報の中にちゃんと銘記されていたりします。
ですが、なぜかその情報はあまり知られていなかったり、軽視されていたり、さらには「マイクロソフトはそう言うけれど、こうするほうが実際には好ましい」として、ネット上のある分野では別のコンセンサスが成立していたりするのです。
例えば、Windowsでのメモリ使用法を「システムキャッシュ」に設定するという有名な推奨設定があります。しかしマイクロソフトのサイトには「これはサーバ用途専用のモードであり、一般的なPCではむしろパフォーマンスダウンを起こしたり不安定要素を増すので注意」という旨が書かれています。にもかかわらず、この設定はWindows2000以降、永らく音楽制作用PCのチューンアップの基本として広く流布されて来たのです。
結局、急がば回れということで、「新しい物事を知るに際しては、その概念の理解を目指し、自分の中でのモデル化を果たそう(つまり全体を模式的にイメージできるようになろう)」という方針に沿って、“にわか勉強”に勤しんだのでした。
用語の理解をある程度済ませた上で先人たちのハウツーを探すというやり方は、最短距離である反面、結局は「偉い人がそう言ってたから」の域を出ません。それに、それが自分のケースに本当に合った回答なのかという確信も無いまま、今後のトラブルへの大きな不安を残すことにもなります。
それに対して「そもそもマルチタスクOSにおけるアドレス空間とは?」とか「仮想PC概念の実装としてのWindows」云々――といったことを、ざっくりとでも理解していくことによって、本当に気を使うべき部分と気にしなくて良い部分とが徐々に見えてくるものです。
実際には困難を伴いましたが、Windowsに対しての誤解や理解不足がいくらか改められたように思います。結果的に現時点での自分なりの納得を得ることができ、その結果新しいPCは想定通りの堅調さで動作していますので、とても満足&安心しています。
我ながら少々度が過ぎていると思わなくもありませんが、私にとってこういったプロセスを辿ることの必要性とその意義は、ギターなどの楽器をオーダーメイドすることとある種同じなのかもしれません。
楽器のオーダーメイドも多種多様ですが、そのプロセスの中でどんなこだわりを貫いたり、理解の道を歩もうとするのかといった部分で、その人のスタイルが自然と浮かび上がってくるものだと思うのです。
例えば、ギターをつくってもらう際には、材料の木材を何にするか、ボディーと指板の材質の関係やそれらがどういった特徴を持っているのか、そのことが自分の音楽とどう関係するのか、何を望みどれが好ましくどれを選ぶのか、等々。
そして、それらの答えを求めて古今の知識を得たり知恵を学んだり、工房へ出向き職人と会ったり、そこで教えを請うたり、さらには職人の楽器論に触れ、果ては人生論を拝聴したり、巡り巡って自分の内面を見つめたり、等々。
私の場合、そうしたプロセスを経て出来上がった楽器を手にしたときに感じる、ある種の“確信”がとても好きですし、また分野を問わずそういったことを望んでいるのだと思います。
「動けば(鳴れば)それでいいじゃないか」という言葉が頭の上で聞こえたりもしますが、自分の気質はそうそう変えられません。
別の角度から少々大げさに例えるならば、このプロセスは儀式であり祭典なのかもしれません。言うなれば「地鎮祭」でしょうか。大きな工事の前に神主さんに祝詞を上げて頂いてお浄めをするというものです。
そのような儀式的なものとして捉えてみると、思い入れの強い物事に対して真剣にかつ熱中して調べたり勉強をして納得しないと気が済まないというのは、ある意味で合点がいきます。ただ、罰を畏れて萎縮しているのでなければ良いのですが、はてさてどうでしょうか。
さて、そのようなわけでPCが新調されていったわけですが、真の課題はシーケンサ(DAW)の乗り換えにあります。
シーケンサ(DAW)の乗り換え
シーケンサ(DAW)は制作環境の土台を成すソフトウェアであり、ことPCで音楽を制作する際には、鳴り響く音楽と自分とを結ぶ、ある意味で鍵盤以上に重要なインターフェースといえます。
つまり音楽制作の中核(コア部)なわけで、シーケンサの乗り換えとは極端な話し「永年使ってきた楽器を持ち替える」ような出来事です。
そういう事情もあって今まで乗り換えに躊躇していたのですが、次なる新たな音楽制作環境に移行するにはどうしても避けては通れない道ですので、新たなDAW探しが必要になってきます。
今までの環境で行っていた作業と同様のことが出来て、欲を言えば以前の不満を解消してくれそうな、そんなDAWをあれこれ探し、最終的にはSONARに決め、そしていよいよ新しい環境の慣らし運転として習作を作り始める段階に入りました。
さて、新しいDAWに慣れていく中で大きな部分を占めているのは、以前のDAWで行っていた処理や手続きと同等のことを新DAW上でも出来るように調査し、習作を通じてそれを習得することです。
新旧の各DAWには、それぞれの編集の流儀といったものがありますので、全く同じ操作方法や編集手続きを望むのは無理なことです。
ですので、当然そこではDAWごとの異なる設計コンセプトから生じる“数々の違い”が立ちふさがってきます。それぞれの作業結果は同じでも、そこへ辿り着くまでのプロセスが全然違うという、そんな違いの数々です。
ある目的地(作業結果)への新たな道を発見し、それを理解・習得するという過程では、数々のストレスと共に達成感や安堵感が訪れます。これはこれでとても楽しく、好奇心をくすぐられるものです。
さて、例えば旧DAWで「ショートカットを交えながら音符の長さをマウス・ドラッグで調整する」という作業を行っていたとします。
新DAWでも同じことが出来るのか、もしくは似たようなことを行うにはどんなプロセスを辿ればよいのか等について、マニュアルを参考に試みることになります。
その結果、幸いにして同程度の労力と手続きで同様の作業が可能だとわかったとします。ですがしかし、そこでなぜかある種のストレスや物足りなさを感じる場合があるのです。
上の例で言うと、新DAWでも「任意の音符長へマウスで迅速に編集する」という目的・要請を満たすことが出来ると判ったのに、なぜかそこで不満を感じるというわけです。
ちなみにこの例に限らず、それは大抵些細なこと、言うなれば「別にこちらの方法でも同じことが出来るではないか」と、自分でも指摘したくなることだったりします。
そこで気付いたのは、旧DAWで行っていたその作業とは、編集結果を求めるための単なる手続きだったのではなく、実はその作業を実施し体験することそれ自体が、無意識的な“隠れた”目的であったという事実です。
つまり、その「あるひとつの編集作業」を「体験し味わうこと」を、ほとんど自覚の無いままに求めていたのです。そしてその体験はとてもフィジカルなレベルのものなのです。
目は画面を追い、対象のデータを捕捉し、おもむろに右手でマウスを移動させ、人差し指がそれをクリック&ホールドし、左手小指はCTRLキーを押し込み、右手首が肘の動作と共にスルスルと移動を始め、それに合わせて画面上のデータは音を伴って変化していき、目と耳はその様子を子細に捉え続けます。
意識はこの状況を何らかのメタファーを通じてぼんやりと捉えながら、これら全体の流れを体験します。メタファーの例としては「じゃがいもの皮むき」ならぬ「MIDIデータの皮むき」といったものや「パラメータの産毛を剃る」といったものが挙げられます。
大事な点は、こうした体験そのものが自分にとって何らかの「フィジカルな心地よさ」を感じさせるものであり、その反復は肉体的なリズムとでもいうようなものとして感得されながら実行されて行くところにあります。
よく世間では、「道具を扱うにはリズムが大切」などと言われますが、DAWも例に漏れず、ちょっとした部分でのリズムが重要であり、それは、ある種のフィジカルな心地よさを生み出すものと言えるのではないでしょうか。
万年筆やハサミなど、身近でフィジカルな道具では当然のように感じていた、この「フィジカルな心地よさを伴う道具体験」。
パソコンによる作業は、マウスやキーボードそしてディスプレイ越しにデジタル情報を操るという、肉体的現実から見れば仮想の出来事を“こちら側”と“あちら側”の隔たりを感じながら扱うということであり、それは隔靴掻痒でかなり歪なものだと言えるでしょう。
しかし人はそうした作業からも、フィジカルな心地よさという体験を得られるのだと思うのです。
パソコンのアプリ・ソフトウェアという道具は、「目指す結果へ向けて論理的な手続き型処理を重ねる」という特徴がどうしても目立ちます。そのため目的とする結果を重視するあまり、プロセスの置換可能性ばかりに注目してしまいがちです。
“より高機能&高性能”と呼ばれる別のソフトを使えば、きっと今よりも“より良くより良い”結果を得られるはず――そんな願いが当然のように喧伝されるのも、この「プロセスの置換可能性」が根拠の一つになっているからだと思われます(この場合は、作業レベルに留まらず成果レベルの話に踏み込んでいますが)。
そういった側面と共に、実際には「このワープロソフトは手に馴染む」とか「このレタッチソフトの小回りの良さと軽快さは病みつきになる」という風に、それを手放せない様子を表したフィジカルな言葉が散見されるのもまた、大切な事実です。
恐らくそれらの背景には、使い手たちの肉体的リズムにフィットした、“心地よい体験”の蓄積が存在すると考えられます。
そして能動的に、もしくは受動的にそれら道具を切り替え(乗り換え)ていく際に感じるであろう「数々の些細な違和感」の存在は、それが自らの肉体的リズムに根ざしたものであるがゆえにこそ、鋭く厳しく使い手に迫ってくるのでしょう。
その事実に直面した際には、旧環境を美化礼賛したり新環境を悪し様に呪うのではなく、自分の求めているものが「結果のための手続き」なのか、それとも「フィジカルな心地よさを伴った体験」なのかを見つめる視点を持つことで、打開へ向けた方策が見え始めるのではないかと思うのです。
そして、PCソフトウェアの特徴である「プロセスの置換可能性の高さ」を意識的に取り入れつつ、新たなフィジカルな体験を模索し、自ら仕組みを構築し生み出していくことが健全なのだろうと考えています。
さて最後に私のケースに話を戻しますと、未だ乗り換えの道は途上ですが、「違うプロセスであろうと可能なだけまだマシ」とか、「やはりLogicがいい」などと苦々しく思うことがありながらも、幸いその後の詳しい調査の中で更なる便利手順や新機能と出会うというケースがとても多いです。
そして新たにそれらをフィジカルに体験することを通じて、トータルではとても満足&充実した乗り換えプロセスを味わっています。小さな習作を数多く重ねるという創作体験ことも、ずいぶん久しぶりで、改めて新鮮な気分を味わっています。
ただこれは、旧DAWが骨董品でしたので、今のDAWだと大抵の機能は上位互換的にカバーされていると言えますから、そういった事情が助けとして影響している部分も大きいのでしょう。
以上、「制作ツールの乗り換えは大変ですね」とか「エクスペリエンス(体験)デザイン領域のことを考えさせられました」で済みそうな話しではありますが、自ら体験したことを“経験”へと高めるためにはこのような意識化は避けて通れないと感じていますので、今回改めて文章にしてみた次第です。