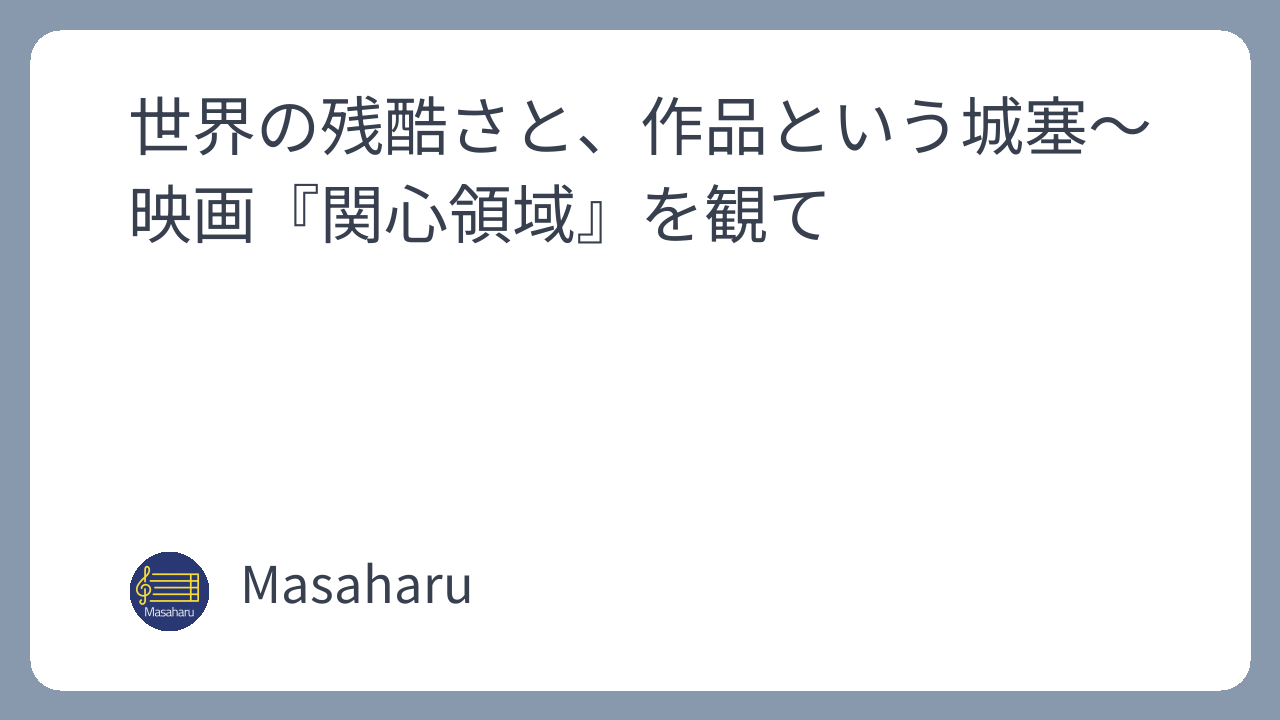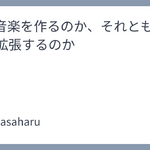先日、映画『関心領域』を観ました。アウシュビッツ強制収容所の所長だった、ルドルフ・ヘスとその家族を描いた作品です。その感想は「静かな衝撃」という言葉が最も近いでしょう。
この作品は、いわゆる「悲惨な映像」や「露骨な暴力描写」によって観客を揺さぶる映画ではありません。むしろ惨劇は画面に現れず、日常の営みと、遠くから聞こえてくる音、距離感、編集の設計によって、世界の冷たさそのものが立ち上がって来る作りになっています。
観終わった後は、映画の感想を思い描くことに留まらず、自分がどのような視点で作品を受け取ったのか、さらにそれが自分の創作姿勢とどのように繋がっているのかを、あらためて考えさせられました。
「残酷だが美しい」と「ただ不快で消耗する」の違い
私は、「世界は残酷である」という本質を描いた作品に惹かれる傾向があります。
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を始め、『ミスト』や『沈黙 -サイレンス-』など、いずれも世界の冷酷さや人間の無力さを赤裸々に突きつけてくる作品として、とても心揺さぶられました。
これらの作品には世界の残酷さが表現されていると同時に、具体的な残酷描写も描き出されています。しかしだからといって、すべての「残酷描写」が同じ質(クオリティ)を持つわけではありません。
例えば、暴力や苦痛を露悪的に先鋭化し、それ自体を刺激や消費の対象として前景化させる作品には、私は深い感動を覚えません。そこでは、世界の構造や認識の更新よりも、感覚刺激の強度そのものが目的化してしまっていると感じるからです。
言うなれば、私が惹かれるのは、残酷さが「構造」として立ち上がる作品です。
- 暴力や苦痛が主役ではなく、(必然的な)副産物として現れる。
- あからさまに感じさせようとしない、間接化する、距離を取る、といった編集志向が見られる。
- 世界が「人間による意味付け」を保証しないことが、静かに示されている。
- 鑑賞後に、認知の再編成が起こる。
こうした点において『関心領域』は、その極めて特異な到達点のひとつのように思われました。
崇高における恐怖
「世界は残酷である」という本質において重要なのは、「崇高」という感覚ではないかと思っています。
私にとって崇高とは、安堵や癒しよりも、明確に「恐怖」に近いものです。例えば、グランドキャニオンのような圧倒的な大自然を前にしたとき、人は畏敬の念と同時に、自分の小ささや、自然に対する制御不可能性、世界の圧倒的スケール感といったものを、体感的に理解させられます。
そうした体感は決して快楽ではありません。世界を矮小化せず、ありのままに受け止めるための、誠実な感覚ではないかと思います。
『関心領域』がもたらした衝撃も、歴史的惨劇への怒りや同情などではなく、「世界はこれほど無関心に、冷静に運動し続けるのか」という構造的な恐怖に近かったのです。
世界は無関心であり、人は無力である。しかし……
私が魅力を感じる映画作品の多くには、共通して次のような世界像が内包されていると思われます。
- 世界(この世)は本質的に人間に無関心である。
- 構造は個人の倫理や善意を容易に踏み越える。
- 人はその前で、驚くほど無力である。
同時にそれらの作品は、単なる絶望では終わりません。
- 人は完全に無力ではない。
- 限定的であっても、抗う裁量と選択の余地がある。
- その行使の仕方こそが、倫理の現場になる。
世界と人のあいだにある、この非対称で緊張を孕んだ関係性そのものを、私は観察し、感受し、味わいたいのだと思います。
マクロとミクロの相関
こうした視点を整理していくうちに、自身の創作について一つのイメージに辿り着きました。それは、以下のような三項構造をもつものです。
- マクロな世界(自然、社会、構造、無関心性)。
- ミクロな世界(内的世界、認知、創作)。
- それらを貫く「私の世界観」というフォルム。
映画鑑賞というインプットの嗜好と、創作というアウトプットの志向は、別々のものではなく、同じ世界認識のフォルムによって貫かれている──そのようなイメージです。
しかもその世界認識のフォルムは、スケールを変えても同型性を保つ、言わばフラクタル(自己相似形)な構造をしているようにも見て取れます。
こうした三項構造を少し具体的に表現すると、例えば以下のようになるでしょう。
- 巨大な世界構造の中で、人は微小な(しかし尊い)裁量を持つ。
- 一つの作品構造の中で、素材は限定的な(しかし開かれた)自由度を持つ。
- 一つのモチーフの中に、全体の性格が折り畳まれている。
自己表現ではなく、世界モデル構築としての創作
このように考えてみると、自分にとっての創作とは、いわゆる「自己表現」とは少し異なる場所にあるように思われます。
つまり、
- 感情を吐露する。
- メッセージを伝える。
- 内面を告白する。
というよりも、
- 世界はどういう構造をしているのか。
- 人はその中でどう配置されているのか。
- その関係性をどのような形式で安定化できるか。
という、そうした問いに対する一種の「世界モデルの構築」に近いのではないかと思います。
心理分析的に述べるなら、私は「世界の無関心性(残酷さ)とその大きさ・強さ」を歪めずに受け止め続けるために、自分なりの城塞を築こうとして創作している──と言えるのかもしれません。
つまり作品とは、心理的防衛であると同時に、世界理解の保存装置でもあるわけです。
最後に
映画『関心領域』を観たことは、単なる映画体験を超えて、自分自身の世界認識と創作姿勢の一貫性を、あらためて言語化し可視化する契機になりました。
- 世界を矮小化しないこと。
- 無関心性(世界の残酷さ)を直視すること。
- それでもなお、人の裁量と応答の可能性を手放さないこと。
こうした緊張関係を、これからも作品というフォルム(形態)の中に、静かに封じ込めていきたいと思います。