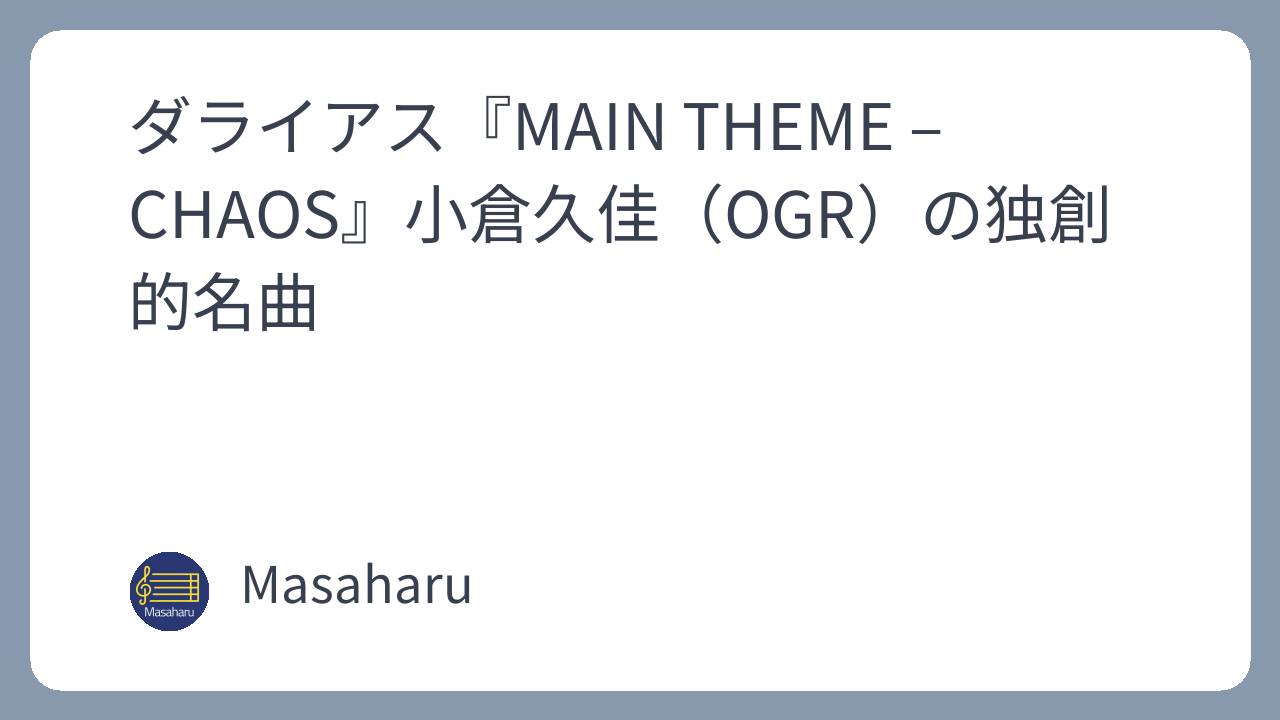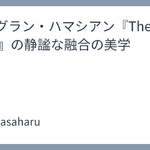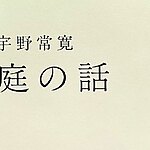1980年代のゲーム音楽には実験的で個性的な名曲の数々が存在しており、1987年に登場した『ダライアス』の「MAIN THEME – CHAOS」(以下「CHAOS」)もそのひとつです。
この記事では、ゲーム音楽の領域における特筆すべきクリエイターである小倉久佳氏(通称OGR氏)の業績、特に『ダライアス』の「CHAOS」に焦点を当てて考察していきます。
小倉氏は、初期のゲーム音楽業界において従来の枠組みを超えた挑戦を続けていました。彼の作品は単なるゲームの背景音楽という位置付けに留まらず、独自の音楽的アイデンティティが確立された芸術的表現だと評価し得るのではないでしょうか。
そんな小倉氏と『ダライアス』・「CHAOS」について、まずは小倉氏が所属していたタイトーのサウンドチーム「ZUNTATA」に関する話題から始めたいと思います。
ZUNTATAの軌跡~偶発から戦略へ
大手ゲームメーカー「タイトー」のサウンドチーム「ZUNTATA」は、ゲーム音楽の歴史に輝かしくその名を刻んでいます。このチームの誕生は、当時のレコード会社プロデューサーが「バンドのような形態の方が夢がある」と提案したことに端を発するとのことです。小倉氏自身は当初、ZUNTATAを『ダライアス』のアルバム制作のための一時的な「一過性のユニット」と捉えており、その後の広範な認知と継続的な活動を予期していなかったと述べています。
しかし当時のゲーム音楽ブームの追い風を受けて、ZUNTATAは予想外の成功を遂げることになりました。その結果、小倉氏はその長期的な存続を見据え、ZUNTATAの「ブランド化」の重要性を強調するに至ります。彼は、社内メンバーが制作した作品であっても、ZUNTATAの特定のムードに合致した「クリエイティブなDNA」を維持するために、厳格な基準を用いて作品をふるい分けしたとされています。
この戦略的なアプローチが、他のゲーム会社のバンドが活動を終える中で、ZUNTATAが独自の存在感を保ち続けた要因だと考えられます。この経緯は、小倉氏が作曲家としてだけでなく、サウンド制作とアーティスト的活動の方向性を統括する先見的なリーダーとしての役割を担っていたことを示唆しているでしょう。
ゲーム音楽の再定義~「映像メディア」としての視点
小倉氏は、ゲーム音楽に対する独自の哲学を展開していました。彼はビデオゲームを、プレイヤーが「プレイする」ものとしてだけでなく、根本的に「視る」もの、つまり「映像メディア」として捉えていました。この視点は、音と映像が共生し、プレイヤーの視覚的・体験的没入感を積極的に高めるという彼の姿勢を明確に示していると言えます。
小倉氏は当時の「ゲーム音楽の常識」に対して、「一掃し、再構築する」という明確な目標を掲げていたと言います。この目標は『ダライアス』において、変拍子の多用や型破りな構成といった「かなりの冒険」という形で具現化されました。小倉氏は、この大胆な試みが将来的に標準的な手法となることを確信していたと語っており、この事実は彼の先進的で実験的な精神を示すものと言えるでしょう。
また小倉氏は、現代のゲーム音楽におけるオーケストラサウンドへの過度な依存に対し、「聴き手を『誤魔化している』」と批判的な見解を表明しているのも興味深い点です。彼は、現代のゲームクリエイターに対し「『ゲーム』を作りたいのか、それとも『映画もどき』を作りたいのか」と問いかけており、映画的な要素がゲームのインタラクティブな性質と真に統合されなければ、映画的な要素の安易な導入は結果的にプレイヤーの体験を損なうと主張しています。
こうした批判は、映画的な「体験の直線性」とインタラクティブなゲームプレイのバランスに関する現代の議論にも通じるものであり、彼のゲーム音楽に対する本質的な視点を示していると考えられます。
「無機質な音」と「Z軸」~「CHAOS」の音響的深層
『ダライアス』のBGM、特に「CHAOS」の決定的な特徴は、低ビットレート・低周波数のサンプリング音源による「独自の存在感を付与された現実音」と、FM音源による「無機質な電子音」の両者を積極的に用いて構築されている点にあるでしょう。このユニークな音響パレットは、『ダライアス』を同時代のゲームから際立たせ、異質で宇宙的・未来的な雰囲気をもたらしました。
小倉氏はインタビューで、「ゲームセンターで目立つ音作り」を意識したと明言しています。『ダライアス』はその個性的で型破りなアーケード筐体(3画面構成やサブウーファーの搭載)という特徴も相まって、人々の記憶に強く残る作品になっているわけですが、彼はそのアーケード筐体のハードウェア性能を深く理解していました。例えば、低音域がシステムによって増幅処理されることや、搭載された2つのFM音源チップの同期に由来するフランジャー効果のことなど、それら音質的傾向を把握し活用していたのです。
その結果、FM音源による「キラキラしたシーケンスのフレーズ」や「ヌケのよいフレーズ」を作曲することによって、音楽性の高い楽曲の制作のみならず、騒がしいアーケード環境の喧騒の中でも効果的に音が際立つ音楽を成立させることにも成功します。これは、単なる作曲者の美的嗜好に留まらない、実用的・現実的なアプローチとして特徴的な点であったと言えます。
そんな『ダライアス』の音楽のなかでも「CHAOS」は、その「異質で個性的なFM音源サウンド」と独特でインパクトのある「オーケストラヒット」が音楽的に高次元で統合されていることから、ファンの間で高く評価されています。このサウンドは当時としては革新的で強いインパクトがあり、初期のゲーム基板におけるFM音源とサンプリング音源で達成できる音楽表現の、ひとつの個性的な到達点を示したものと言えるでしょう。
同時代のビデオゲームであるSEGA(セガ)の『スペースハリアー』や『アウトラン』なども、FM音源とサンプリング音源の組み合わせによって、センスあふれるゲーム音楽の数々を奏でていました。しかしそこでは、サンプリング音源は「FM音源には出せないリアルな打楽器音」などを補強し、既存の音楽ジャンルを取り入れて再現するために用いられるという側面が目立つものでした。
それらと比較すると『ダライアス』は、既存の音楽ジャンルを取り入れ再現するためにサンプリング音源を用いるのではなく、独自の音楽的世界観を生み出すためのジャンピングボードとして活用されている点で一線を画したものと言えます。
ちなみに小倉氏はインタビューのなかで「当時の技術的・コスト的な制約によってサンプリング音源の容量は極めて小さなものだった」と述べていますが、そうした制約が結果的に「原音が辿れないほど変質したリズム音やオーケストラヒット」を生み出すこととなり、独特の世界観を醸し出す重要な素材となったのは興味深いことです。
また「CHAOS」は、ファンから「どこか不安感を抱えたような音楽だ」とか「全体的に不気味、不穏な雰囲気を喚起する」などと評されていますが、これには私も同感です。闘争心を掻き立てるような勇ましさやヒロイックな華麗さといったムードではなく、複雑で尋常ならざる感覚が呼び起こされるのです。このような音楽的特質は、単に興奮を煽る従来のゲーム音楽とは明確に異なっており、「CHAOS」の独特のインパクトと印象深さに貢献しています。
小倉氏は「宇宙に雪を降らせる」という制作イメージを抱いていたと自ら語っているわけですが、この広大で冷たい、ある種の冷厳さや虚無といったものを暗示する宇宙のスケールと、それに伴う不穏な静けさという感覚とが、この「CHAOS」によって完全に調和し表現されていることが実感できるはずです。
小倉氏は、ゲーム音楽に「Z軸」を創造するという野心を表明していました。これはゲームプレイの従来のXY軸の二次元平面を超えて、表現の新たな深遠な次元を加え、作品に「様々な表情」を与えることを意味しており、実際にプレイヤーの体験を複数のレベルで豊かにすることに成功したと言えます。すなわち「CHAOS」は、この「Z軸」の概念を具現化した楽曲であり、単なる背景音楽ではなく、ゲームの世界観、雰囲気、心理的深さと相互作用する不可欠な要素として機能しているのです。
ゲーム音楽史における「フィールド」の拡張~「CHAOS」の遺産
当時ZUNTATAのメンバーだった古川典裕氏は、『ダライアスのメインテーマであるCHAOSは、ゲーム音楽のフィールド(外郭)を大きく拡げた』と述べていますが、その指摘の通り、FM音源とサンプリング音源を統合した環境のなかで『ダライアス』の世界観をアーティスティックに具現化しようとしたその「挑戦的な試み」は、当時としては類を見ないものであり、ゲーム音楽の新たな基準を確立したと言っても過言ではないでしょう。
さらに古川氏はシリーズ作である『ダライアスツイン』の制作時に、小倉氏から「シューティングゲームの音楽と『ダライアス』の音楽は根本的に違う」という発言を聞いたとコメントしていますが、これは『ダライアス』の先駆的な精神を象徴するものとして傾聴に値します。この指摘は、『ダライアス』の音楽がそのジャンルの機能的な慣習を超越し、より高い芸術的次元を目指していたことを示唆していると思われます。
ちなみに『ダライアス』の後継作品のひとつである『Gダライアス』の音楽は、1997年度の第11回ゲーメスト大賞ベストVGM賞部門において、歴代最高の492点を獲得して第1位となり、前例のない高評価を得ています。この受賞は、『ダライアス』から進化・発展していった小倉氏の画期的な音楽的クオリティとその功績を明確にしたものと言えるでしょう。
「CHAOS」・『ダライアス』によって切り開かれた芸術的領域は、後続のクリエイターたちが自由に新たな音楽を作り出すことを可能にしたといえます。私も「CHAOS」を初めて聴いたときの衝撃は今でも忘れられませんし、自らの音楽的イメージを飛翔させる小倉氏の力強さに心を打たれたものです。
『ダライアス』における楽曲群のなかでも特に「CHAOS」は、ゲーム音楽史において記念碑的な作品として位置づけられるのは間違いないでしょう。小倉氏の個性的なサウンド、アーケードゲームのサウンドデザインへの戦略的なアプローチ、そしてゲーム音楽への思索を通じて、彼は既存の慣習を再定義しました。
「CHAOS」は単なるBGMとしての機能的な意味に留まるものではありません。言うなれば、ゲーム音楽に対するイメージを根本的に変革したという、その実践の軌跡そのものなのです。
小倉氏の創造的アプローチと『ダライアス』・「CHAOS」という音楽遺産は、ビデオゲームというインタラクティブメディア内で達成可能な芸術的深さと文化的影響力に関する明確な証左として、これからも注目され続けることでしょう。
関連記事