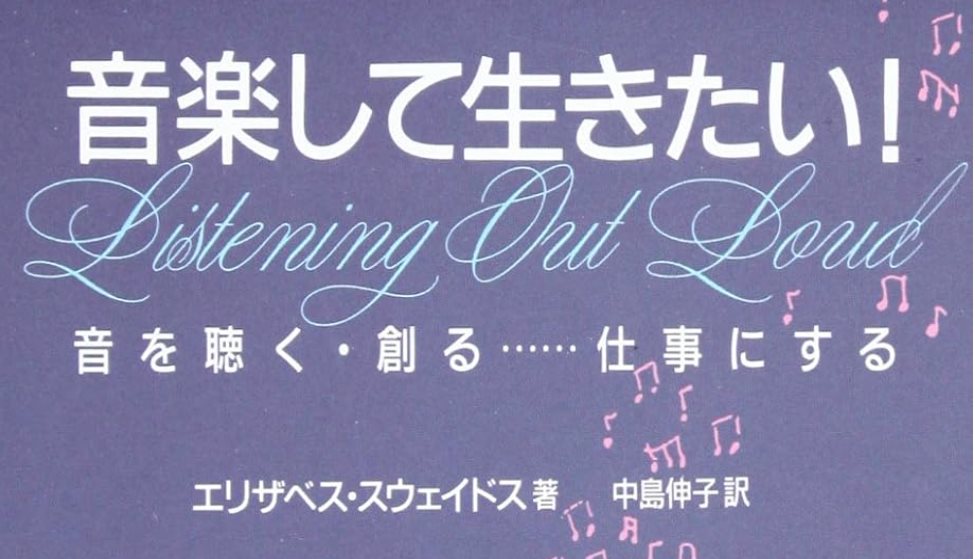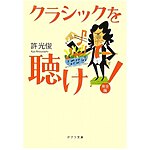(初出2002年4月9日)
作曲家を志す人のための応援歌と呼べる一冊です。著者はミュージカルやオペラなどの分野で活躍し、トニー賞へのノミネート経験もあります。そういった分野で揉まれてきただけあって、エネルギッシュであり、また時にシニカルな視線からのユーモアも感じさせる内容です。
第5章「自分の音楽形式を見つける」をはじめ、作曲経験を積むプロセスにおいて大切だと思われることを、詩的な表現も交えながら具体的に語っているのが特徴です。
例えば、音楽形式への向き合い方について、著者はこう語ります。「ある形式を選ぶ時には、その中心となる要素──ある楽器とか、特定の和声進行とか、抽象的な音とか、記念したり賞賛しようとする人物や出来事──に情熱を感じなければならない。形式は、この要素にできる限り印象的な捧げ物をしたいというあなたの願いによって形作られる。あなたが愛しているこの要素を、音楽的意味で最も雄弁に語るにはどうしたらよいか。そこから引き出せる最も鮮烈なサウンド・ペインティングは何か。こうした疑問を発する時、あなたは自分の形式を定義しているのだ。」
また、オープニングの章では強い思いと自負を込めながら、作曲家という存在について次のように述べています。「音を組織しようという情熱、そして音を自分のものにして形を整えたいという欲望は、全ての作曲家が持つ特徴である。そして私は、ほとんどの作曲家はこうした衝動を人生の早い時期に経験するのではないかと思う。音との類まれな関係と音に対する熱狂は、それを発達させようと意識して決意するような技術ではない。それらは作曲家に与えられるものであり、彼らにとって一つの出来事とは総合的な音のオペラである。作曲家の望みは、その中で演じたりそれについて語ることではない。楽器や和声やリズムを駆使して、絶対的な支配者としてそれを統治することなのだ。」
◇
さて、その人にとって作曲行為は「何のため」の「手段」であるか、またはそれ自体が「目的」であるのか、そしてその双方のバランスについてなど、こういったことは永く作曲をしている方ならば一度は脳裏をよぎる問いではないでしょうか。音楽をつくるプロセスでの他者とのコミュニケーション自体が目的だ、ということもあるでしょう。また、創作という行為に我を忘れている状態が自分にとって自然なのだ、ということもあるでしょう。
作曲家である著者も同様に悩み、選択し、行動して来たことが本書から分かります。自分の好きなものを職業に選んだことによる悲喜交々が、ここには一杯詰まっているのです。それは実に具体的で、赤裸々ですらあります。
一種、神格化された過去の作曲家の自伝では味わえない、等身大で身近に感じることの出来る、そんな共感にあふれる本だと思います。若い人にはリアルな体験談を、経験者には共感と気付きを与えてくれるでしょう。著者の、音そのものとの出会いを大切にするその姿勢からは、大切な初心を思い出させてくれるのではないでしょうか。
書籍情報
『音楽して生きたい!』の目次
- 謝辞
- 1 オープニング
- 2 本当にいい師とは
- 3 基本を身につける
- 4 曲づくりのプロになるために
- 5 自分の音楽形式を見つける
- 6 何度でも書きなおす勇気を
- 7 この世界で生き残るために
- 8 作曲家として、女性として
- 9 成功……さて、それから
- 訳者あとがき/索引
著者について
エリザベス・スウェイドス
著者は、おもにオペラやミュージカルなどの舞台音楽を作っている現在活躍中の作曲家で、トニー賞にも数回ノミネートされている。また、本書にもあるとおり、大学で学生達の指導にあたり、ユニークな教育方法を実践するかたわら、自作のイラストをふんだんに使った子供向けの物語も数冊出版している。年齢は不詳だが、日本でいったら全共闘世代の少し後の世代、といったところだろう。(本書より引用)