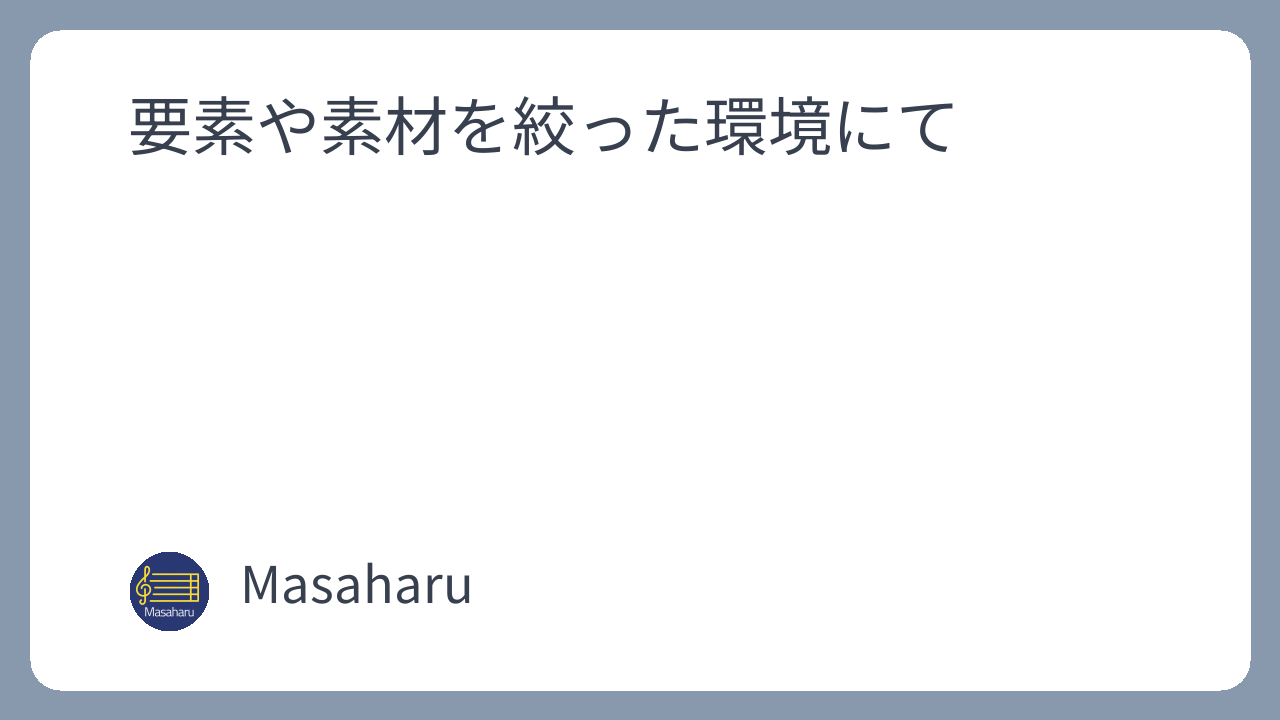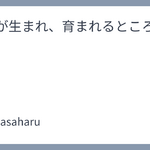(初出2006年7月1日)
先日、アフリカの民族楽器カリンバの「組立キット」なるものを購入。久しぶりに簡単ながらも工作を体験しました。仮止めした金属鍵の下に支点となる金属棒を潜り込ませるという作業に若干手こずりながらも、予想より早く無事に完成。
さて、ここからが要の作業でありお楽しみの「調律」です。カリンバは必ずしもひとつの音律に固定する必要はなく、演奏ごとに色々と変えてみることが出来るのが良いところです。
お約束の12平均律の世界から、メジャースケール、ペンタトニックやヘキサトニックスケール、スパニッシュ系、リディアンなどを。また、7平均律もどきを通じてガムラン的な響きや、その他、複数の音律を右手側と左手側に別々に割り当ててみたり。
音律によっては、共鳴箱としての本体が独特のうなりを発するのが面白いです。メジャースケールなどは、終始「ぽわーん」とした残響がまとわりつきました。これは共鳴というよりも、濁りとしてのうなりが加味されたものでしょう。
不思議と心地よい濁りで、音楽的な豊かさすら感じさせます。これは要するに、ピアノのダンパーペダルを踏んで打鍵した状態と似ているのかもしれません。
さてカリンバと戯れていると、即興演奏による刹那的な快という状態から、即興によって生まれた音楽時間(とその記憶)を構成していこうという心理状態にシフトし始めました。
「ここまでの演奏に“かたまり感”を感じるから、これと対になるような別のかたまりを意識して続けて即興してみよう」という風に、即興的な構成作業すなわち一つの作曲行為が形作られていきます。
この行為でスリルとカタルシスを一番感じるのは、もちろん曲を終わらせる時です。音楽的なピークを最後の瞬間に持ってくるのか、それともクールダウンさせて時間を止めようとするのか。そこまでの音楽時間と今この瞬間とを感じることを通じ、終わりを模索するのです。
先の調律において、自分の音楽ボキャブラリーと遠い音階にすればするほど、つまり自分にとって音階としての意味を成さないただの「音塊」にすればするほど、即興的な作曲をする自分の感覚のバランスが、アウトプット寄りからインプット寄りになるのに気づきます。
「こんなのはどうかな?」というアウトプット志向の意識よりも、「何が鳴っているんだ?」というインプット志向の意識が全面に出てくるように感じるのです。例えば、打楽器的に弾いてみた自分の音に対してそこにメロディーを聞き取った結果、その事実に驚き戸惑いながらもフレーズを即興してみたり、そしてまたそれに聞き耳を立てたりするのです。こうして即興的な作曲は続いて行くのでした。
アンサンブルではなく単一の楽器演奏において、リズム・メロディー・ハーモニーの各要素を不明瞭にしたり限定したりすること。──こういった環境に即興を通じて没入することを通じて、自分自身の音楽感覚を再確認したり再発見すること、そして育むことが出来るという事実を、素朴なカリンバ組立キットに思い出させてもらったような気がします。