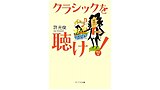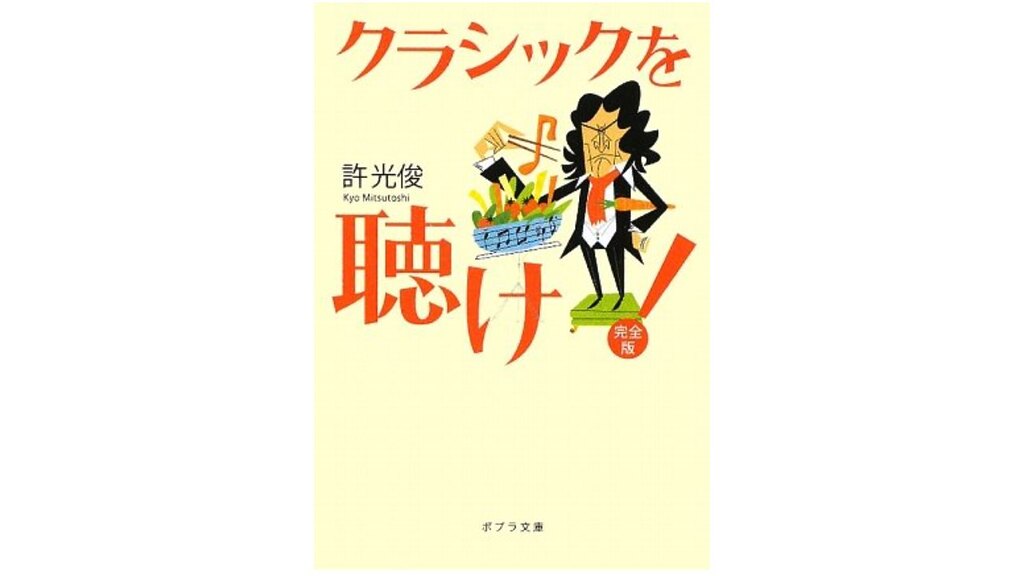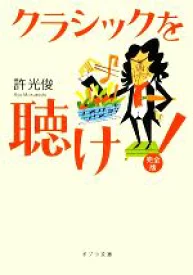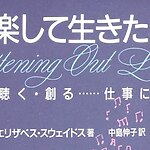(初出2002年4月9日)
シンプルな語り口で大胆に解説する痛快な一冊です。クラシックを聴き始めたものの、延々と繰り広げられる音の洪水に目を回している人には、うってつけでしょう。特に、ソナタ形式という名前は知っているもののその実感がつかめない人は、この本によってグッと近づけるようになるでしょう。
作曲をする人にとっては、音楽構造の把握とその操作についての気付きや発見につながると思います。特に、ある程度作曲経験を積んできている中級者には、音楽を形作る視点が一皮むける可能性があります。
本書は、単なるクラシック入門書とは一線を画し、既存のクラシック音楽界に対する痛烈な批判精神に満ちています。「お気楽極楽入門書」というサブタイトルとは裏腹に、クラシック音楽の本質を深く掘り下げ、著者のいう「真のクラシック」と呼ぶに値する音楽とはどのようなものなのかを問いかける内容になっています。
第1章で提示されるのが、「クラシックに親しもうと思ったら、推理小説を読んで、自分でサラダを作りなさい」という、意表を突くような提言です。著者は、個性の異なる素材が混然一体となって調和したサラダの味わいは、クラシック音楽におけるハーモニー(調和)と同様であると指摘します。
また、この提言は、クラシック音楽を単なる受動的な鑑賞物としてではなく、能動的に分析し、自らの手で「調理」するような姿勢で向き合うことの重要性を示唆しているとも言えるでしょう。
続く項目では、クラシック音楽を聴く上での心構えや、その本質を見抜くための視点が提示され、二種類ある美しさとして「抽象的な美しさ」と「感情移入型の美しさ」を取り上げ、クラシック音楽の一大特徴は「抽象的な美しさを追求することによって“人間以上の何か”を表現することにある」と指摘します。
このようにしてクラシック音楽の基本を提示した後、次章から具体的な作品が取り上げられて解説が進んでいくことになります。
「芸術や美が人間の生活を豊かにするという考えは恐ろしく楽天的で鈍感な人間の考えである」──これは、許氏の他の著作『クラシックCD名盤バトル』からの引用ですが、彼の根底にある思想が凝縮されています。単なる慰めや癒やしとしての音楽ではなく、時に人を突き放し、痛みさえも伴う、そんな芸術としてのクラシック音楽の姿を提示しようとする姿勢が、類書にはない厳しさと深みを与えていると思います。
◇
元々クラシック音楽とは縁遠かった私は、本書を読んで「ロメオとジュリエット」を聴くまでは、チャイコフスキーをしっかりと聴いたことがありませんでした。著者の言うような、「甘いメロディーだけの作曲家」とまで思っていた訳ではありませんでしたが、有名なバレエ曲を断片的に聴いていた程度だったのです。
しかし、初めて「ロメオとジュリエット」を聴き、本書64ページからの詳細な説明をはじめとする内容に触れるにつれ、なるほどチャイコフスキーはメロディー・センスだけではなく、音楽の構造に対する確かな耳を持った作曲家だったのだな、と実感しました。
その後、遅れ馳せながら交響曲などのメジャー曲を聴き、「構造」と「エモーショナルなもの」とのせめぎあいが垣間見れることに面白さを感じたりもしました。そしてチャイコフスキー自身、構造と感情的なものとを、どのように折り合わせるかに悩んでいたのではないか──と思ってしまうのです。
さて、本書をご覧になればお分かりの通り、著者はかなりの辛口です。大学での講義はどんな調子で行われているのか、少し気になってしまいます。
書籍情報
『クラシックを聴け!』の目次
- 序文に代えて
- 第1章 超基本1から6まで-聴き始める前に
- クラシックの超基本1と2/推理小説とサラダの秘密
- 超基本3/とてつもなく大事な演奏家
- 超基本4/ナマ以外はウソなのだ
- 超基本5/美しさには二種類ある
- 超基本6/これがクラシックの曲種だ
- 第2章 実践編1-基本の三曲、これだけ聴けば、クラシックは完全にわかる
- 恋愛大悲劇をテーマにした音楽に隠された奥義/チャイコフスキー「ロメオとジュリエット」
- ソナタ形式の謎、これがわかればクラシックは九〇パーセントわかる/モーツァルト「ピアノソナタ第十五番」
- クラシックのパターンはここに完成した/ベートーヴェン「交響曲第九番」
- 第3章 実践編2-もっとディープに、もっと危険に
- ベートーヴェンを尊敬しつつベートーヴェンを超えた大天才シューベルト/シューベルト「交響曲第八番 未完成」
- ベートーヴェンとシューベルトの末裔たち
- アントン・ブルックナー「交響曲第八番」/そして、本書の結論、クラシックのその後
- 第4章 コレッキリ!実用情報
- これがスゴイ作曲家だ!
- クラシックのホール徹底解析
- クラシックのチケットは高いか?
- これがコンサートの最初から最後まで
- どれが聴くに値する演奏家?/<生きている人>編
- どれが聴くに値する演奏家?/<死んじゃった人>編
- 世界のオーケストラ、どれを聴けばいいのか?
- オーディオは重要か?
- 誰を信じればいいのか?/評論家ぶったぎり
- 古楽とは何か?
- あとがき
著者について
許光俊(きょ みつとし)
1965年、東京生まれ。慶應義塾大学で美学、東京都立大学大学院でドイツ文学を専攻。現在、横浜国立大学マルチメディア文化課程講師。(本書より引用)
関連記事