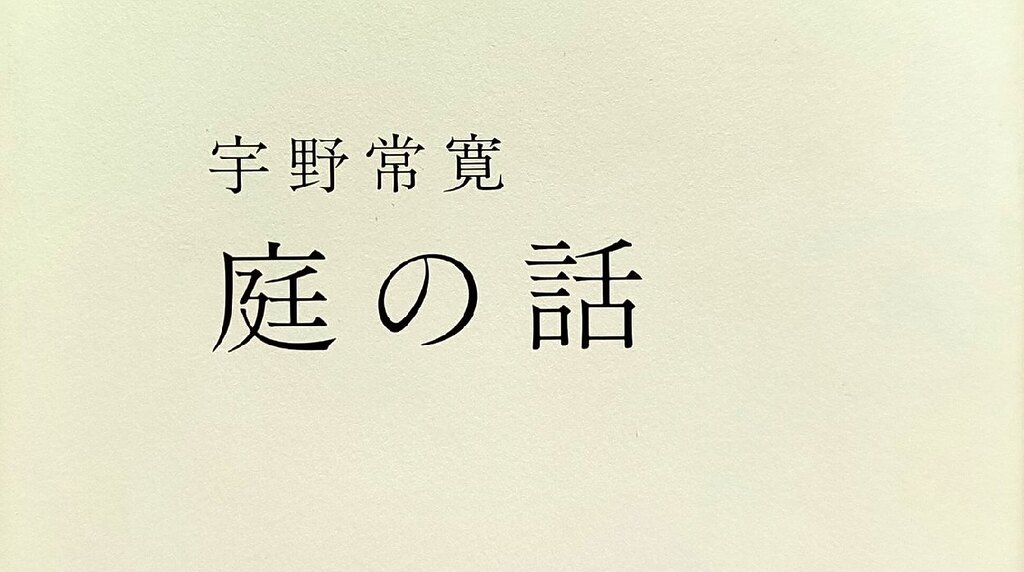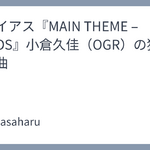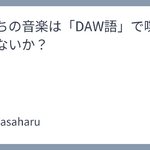宇野常寛氏の『庭の話』は、現代社会の諸問題に対し、「庭」という独自のメタファーを用いて新たな視点を提供する、示唆に富む一冊です。
この記事では本書『庭の話』の内容を「DAW(Digital Audio Workstation)による音楽制作」に応用することを通じて、創造性を追求し続けるための精神的・実践的な指針を提示することを試みます。
宇野常寛 著『庭の話』について
宇野常寛氏の『庭の話』は、現代社会のあり方を「家」と「庭」という二つの象徴的なメタファーを用いて深く考察する一冊です。
宇野氏が批判的に捉える「家」とは、家族や企業、オンラインコミュニティなど、閉鎖的で人間が全てをコントロールしようとする関係性や空間を指します。ここでは同調圧力が生まれやすく、多様性や偶発的な出会いが排除されがちです。
これに対し、宇野氏がその重要性を説く「庭」は、人間の意図を超えた偶発性や予測不能な要素を積極的に受け入れ、多様な事物との対話を可能にする、半分閉じられ半分開かれた空間を意味します。
本書では、この「庭」の概念を通じて、デジタルプラットフォームがもたらす「人間性の画一化」と「多様性の喪失」に対し、個人がいかに真の創造性を取り戻して豊かな人生を送るべきかが考察されています。
國分功一郎氏や安宅和人氏といった現代の論者からもその重要性が指摘されている本書は、デジタルプラットフォームと人間との望ましい関係性を深く考察する試みとして、私のようなDAWを使って音楽制作を実践する者にとっても、非常に示唆に富む内容でした。
SNSをはじめとするデジタル・プラットフォームが社会に与える影響を丹念に分析し、その先で個人が目指すべき可能性を「制作」という行為を軸に探求する宇野氏の視点は、DAWと向き合い音楽制作をする私の創作論に新たな光を当ててくれました。中でも、SNS上で繰り広げられる承認と評価のゲームが、本来あるべき多様な課題設定や創造性を阻害しているという指摘には、頷くばかりです。
この「家」と「庭」の概念は、DAWを用いた音楽制作における葛藤をとても的確に捉えています。DAWは音のあらゆる側面を完璧にコントロールし、計画通りに作品を仕上げる「家」のような環境を提供します。
しかし宇野氏が批判する通り、この過度なコントロール志向は、新しいアイデアの停滞や、SNS上での「承認と評価のゲーム」に起因する内発的動機の喪失といった葛藤を生み出す原因にもなります。なお次章では、このDAWの「家」としての側面が持つ、創造性における「肯定的な役割」についても考察していきます。
宇野氏は、「庭」というものが「半分閉じられ、半分開放された空間」であると述べます。「半分閉じられ」ているのは、外部の評価や流行から距離を置き、自身の内面的な探求心と向き合う「孤独」の領域のことです。
一方、「半分開放され」ているのは、人間の意図や思想を超越した偶発的な出来事、つまり予測不能な「ズレ」や「ノイズ」が入り込む余地がある領域のことです。その結果生じる偶発性との出会いこそが、固定観念を打ち破り、より人生(そして創作)を豊かにする機会をもたらす──そう著者は続けます。
「庭」としてのDAW空間~デジタル制作環境の再解釈
では次に、上述した「家」と「庭」のメタファーや『庭の話』に登場するキーワードを用いながら、「DAWによる音楽制作」について考えていきます。
DAWは現代の音楽制作において、もはや必要不可欠なツールです。作曲、編曲、レコーディング、ミキシング、マスタリング、プラグインや外部MIDI機器の操作といった多岐にわたるプロセスを、自宅スタジオという個人的な空間で一元的に管理・実行できます。
これらの特性、特に自宅というプライベートな環境で、制作の全てを細部にわたって管理し、コントロールできる点こそが、DAW環境を「家」というメタファーで捉えることができる理由です。
このようなDAWの制作環境を「家」と捉えることは、前の章で宇野氏が批判的に指摘する「閉鎖性や画一性」を肯定するものではありません。むしろ、制作における「安定性」「管理可能性」「計画性」といった側面を指します。秩序とコントロールが確保された「家」のような環境があるからこそ、その内部で「庭」のような偶発性を受け入れ、創造的な活動に没頭できるという、制作の土台としての肯定的な側面を強調しています。
私はプロジェクトファイルを開くたび、こうしたデジタルな「家」に帰ってきたような感覚を覚えます。トラック構成、アレンジの構造、MIDIの打ち込み、ミキシングバランス、エフェクトの適用、オートメーションなど、これらすべてを精密に管理し、意図通りの音響空間を構築しようと試みる行為は、住み慣れた家の中で黙々と集中してものづくりに取り組む姿を彷彿とさせます。コントロール可能な領域を緻密に設計し、作品の骨格を築き上げていく作業は、厳密なものづくりのプロセスそのものです。
そしてこのDAWプロジェクトの内部には、同時に「庭」の要素も深く息づいていることに気づかされます。例えば、作曲家が意図しない、あるいは偶発的に導入される予期せぬ音の組み合わせや、初めて試すプラグインがもたらす予測不能な効果、さらにはシンセサイザーのランダマイズ機能や、あるいは単なる操作ミスや偶然の連鎖などが挙げられるでしょう。
こうした不確定で偶発的な要素が、計画を超えた新たな音響要素を生み出すことは多々あります。複雑なエフェクトチェーンを組んだ際に生じるフィードバックノイズや、複数の音源を重ねた際に生まれる意図せぬ倍音の響きなどは、作者のコントロールを一部逸脱し、作品に予期せぬ深みや広がりをもたらしてくれます。
宇野氏は「庭」の特徴として、「人間の思惑や思想を超越した偶発性」や「動く乱数供給源」としての自然を挙げているわけですが、これらと「DAWが生み出す予期せぬ音との出会いと共創」とは、共鳴しているように思われます。
つまり豊かなデジタル創作とは、必ずしも絶対的な制御から生まれるのではなく、構造化された「家」の中に、偶発的な音の「生命」と創造的な「成長」を許容する、そのような「庭」を育むことから生まれる──そんな風に捉えることが可能でしょう。
そして作曲家の技量とは、単なる技術的熟練に留まらず、デジタルな「庭」から生まれる偶発的な「贈り物」を認識し、それを作品に統合する能力にあるのだとも言えるのではないでしょうか。これは「一種の偶然の美学」であり、「創る=成ることへの共同と立ち合い」と表現することが出来ると思います。
宇野氏のメタファーを用いていうなれば、創作行為とは、偶然生まれる音と共に「作品が自ら形作られていくプロセス」に立ち会うことなのではないか、ということです。
プラットフォーム社会とDAW音楽~承認欲求と創造性のジレンマ
ここまでは、DAWが持つ「家」と「庭」の両側面について考察しました。次に、DAWを用いた音楽制作が直面する、現代のプラットフォーム社会における課題について掘り下げていきます。
現代において、DAWで制作した楽曲が世に出る場は、YouTube、SoundCloud、Bandcamp、Spotifyといった音楽プラットフォームやSNSが中心です。「いいね!」や再生数、コメント、シェア、フォロワー数といった指標が作品の「評価」として可視化され、作曲家自身も、これらを通じて「承認」を得ようとする傾向があることを否定できません。
宇野氏が指摘するように、この「承認の交換」は本来の創作目的を見失わせ、プラットフォームのアルゴリズムやトレンドに合わせた「攻略」を目的化させる危険性を孕んでいます。より多くの「いいね!」や再生数を獲得するために、既存の話題に便乗したり、手軽に承認を得やすい音楽スタイルに傾倒したりする誘惑に晒されるのは、DAW音楽制作を手掛ける作曲家も例外ではなく、このような状況は創作の「目的化」と「画一化」を引き起こす可能性をはらんでいます。
宇野氏の言う「虚構の敗北」――作品の内容そのものよりも「作者の現実の物語」や「共感」が重視され、21世紀が「自分の物語」を発信することに夢中になる時代になった――という分析は、DAW作曲家が直面する「発信の課題」と重なります。
現代では楽曲を公開するだけでなく、自身の制作プロセス、インスピレーションの源、ライフスタイル、個人的な苦悩や成功といった「作者の物語」をSNSで発信することが求められる傾向にあると考えられます。例えば制作風景のVlogや、楽曲に込めた個人的なエピソードなどが、作品以上に注目を集める状況も珍しくありません。
しかし宇野氏が指摘するように、「ほとんどの人が発信に値する自分の物語を持っていないにもかかわらず、自分の話をする方が楽しいという人間の悲しい習性がある」ならば、次第に承認を獲得しやすい表層的な発信を反復するようになるかもしれません。これは、本来の創作活動から乖離し、自己演出に多くのエネルギーを費やすことになりかねない危険性をはらむものでしょう。
この状況は、作曲家が本来追求すべき深い「制作」──つまり、音そのものと向き合って探求することに注ぐべき重要なエネルギーと集中力を奪いかねません。結果として、本質的な創造的表現ではなく、作曲家自身が「製品」となって、音楽がその「製品」を際立たせるための単なる背景やツールになってしまうという、新たな「承認ゲーム」の形へと変質させてしまうリスクがあると考えられます。
「孤独」な制作と「共同体」への接続~音楽制作コミュニティの役割と課題
上記のようなプラットフォーム社会の課題を踏まえながら、続いて、作曲における「孤独」の重要性、そしてオンラインコミュニティとの関係性について考えていきます。
宇野氏は、プラットフォームの支配力から逃れるためには、相互評価のゲームの外部としての「事物とのコミュニケーション」が必要であると考え、そのために「人間を正しく孤独にする」ことの重要性を説いています。つまり、常に誰かと繋がっている現代において、物事と直接向き合うためには、一度孤独になる必要があるというのです。
DAWを用いた音楽制作は、多くの場合、自宅スタジオという個人的な空間で行われます。この環境こそが、他者の評価や視線から切り離された「孤独」な状況下で音と向き合い、内省的に作曲に没頭することを可能にします。例えば深夜、一人DAWと向き合う時間は、まさに外界から隔絶された聖域であり、自身の内面と対話する貴重な時間と言えるでしょう。
この「孤独」は、宇野氏が提唱する「承認の交換からも、社会からの評価に依存することからも解放され、人間らしく生きられる社会」の基盤となり得るものではないでしょうか。表面的な話題に埋もれることなく、自己の根源的な問いを掘り下げ、独自のテーマを見出すための「庭」は、こうした「孤独」の中にこそ育まれるのだと思うのです。
DAW作曲家は、オンラインコミュニティ(例:フォーラム、Discordサーバー、SNSグループなど)を通じて、作品のフィードバック、情報交換、モチベーション維持、コラボレーションを行うことができます。
そこには、宇野氏が批判する「共同体」の負の側面(承認の交換、画一化、同調圧力)ばかりではなく、緩やかで目的志向をもった「共同体」としての機能を持つ正の側面もあります。これらのコミュニティは、個々の「孤独」な制作活動を補完し、学びや刺激の場を提供する点で有益です。
しかし、これらのオンラインコミュニティもまた、プラットフォーム上に存在するため、承認欲求のゲームに陥るリスクを常に抱えています。コミュニティは貴重なサポートとのつながりを提供する一方、宇野氏が批判する「承認ゲーム」や「相互評価」に陥りやすいという本質的な脆弱性を持っているのです。フィードバックを求める欲求は、コミュニティ内での「いいね」や評価の追求へと容易に変質し、本質的な創作に必要な「あるべき孤独」を損なう可能性をもっています。
共同体がもつ「不都合なこと」(同調圧力、批判への過敏さ、内部での評価基準の固定化)は、たとえ「緩やかな」オンライン環境であっても再浮上し、作曲家が「根源的な問い」を追求したり「事物そのもの」と向き合ったりする能力を阻害する可能性があります。
共同体とDAW作曲家との関係のバランスはとても繊細なものです。共同体との関係性が強過ぎると孤独が侵食され、少な過ぎると孤立につながります。DAW作曲家にとって、深く本質的な創作に必要な「孤独」と、成長と共有のための「共同体」との間の、この緊張関係を乗りこなすことは、極めて重要な課題だと思われます。
このような状況下において、宇野氏の提唱する「庭」の概念を用いることで、DAW作曲家が「共有されたデジタル環境(デジタル・コモンズ)」の恩恵を受けながらも自身の創造性を見失わないための、とても重要な「枠組み」を導き出せるのではないかと思います。
その「枠組み」とは、単に偶発的な音を作品に取り入れるという行為に留まるものではありません。この「枠組み」には、外部の評価や情報過多から自身を守る「孤独」を確保する思考様式や、コントロールできない偶発的な要素を創造の源として活用する「共創」の行動原則、そして音そのものと深く向き合い探求を深める「事物との対話」という精神的な態度が複合的に含まれます。
つまりこの枠組みは、AI時代においてDAW作曲家が自身の創造性の本質を見失わず、真に豊かな音楽を生み出し続けるための、包括的な指針となり得るものだと言えます。
そして、その枠組みの中心にあるのが、「自身の内なる『庭』を育む」という考え方です。
「自身の内なる『庭』」とは、外部の評価や共同体からの同調圧力に過度に囚われることなく、作曲家自身が音そのもの、つまり「音楽」という創作対象と直接的に対話し、探求を深めるための「精神的かつ実践的な聖域」を指します。
これは、DAWというツールが生み出す予期せぬ音との偶発的な出会いを受け入れ、それを自身の創作に取り込むプロセスです。
この偶発的な出会いこそが、ひとつの具体的な『庭』の要素となります。と同時に、こうした実践の根底には、人間の思惑を超えた偶発性を尊重するという思想があり、これは『抽象的な概念としての庭』を内面化することに他なりません。
したがってDAW作曲家は、広範なデジタル空間の多様性を享受しつつも、自身の内なる「庭」を意識的に耕し、そうして外部の誘惑に左右されない本質的な創作活動を育み続ける、そのような努力が求められることになるでしょう。
DAW作曲家から見た『庭の話』の創作論的意義と未来
ここまで、『庭の話』における「庭」の概念がDAW音楽制作にどのように関わるのか、そしてプラットフォーム社会での承認欲求や「孤独」との関係性について考えてきました。
次は、ここまでの考察を踏まえながら、DAW音楽制作がAI時代において持つ創作論的意義とその未来について見ていきます。
宇野氏は、國分功一郎が『暇と退屈の倫理学』で「消費」に対し「浪費」を主張したことについて、『庭の話』では「評価と承認」に対し「制作に没頭すべきだ」と主張します。これは、現代の情報社会において、人々が情報消費や承認獲得に時間を浪費する傾向にあることへの警鐘と言えます。
DAWを用いた音楽制作は、この「制作に没頭」する行為の典型例のひとつです。それは単なる消費(音楽を聴くこと)や浪費(無目的な時間潰し)とは異なる、具体的な「作品」を生み出す創造的なプロセスです。
DAW作曲家は、音の細部にこだわり試行錯誤を繰り返す中で、深い没頭状態(フロー状態)に入ります。この「評価がなくても好きだから続けてしまう」という感覚は、DAW音楽制作の具体的で問題解決的な性質から直接的に生まれる、強力な内発的動機です。
近年、AI作曲ツールの台頭により、音楽制作の民主化が加速し、技術的なスキルがなくてもある程度の音楽制作が可能になりました。AIは、作曲のアイデア出し、編曲、ミキシングなどをサポートし、制作コストを削減する(リソースを節約する)可能性を持っています。これにより、より多くのアーティストが音楽制作に参入しやすくなることが期待されますし、それは実際に実現し始めています。
しかし、AIは学習データに基づいて典型的な処理を施してアウトプットするため、オリジナリティが欠如する恐れがあり、作者の細かい意図やニュアンスを汲み取れないという課題も指摘されています。また、生成された音楽が既存の楽曲と類似してしまう可能性があり、著作権の問題も複雑です。
このような背景の中、識者たちによる未来予測として次のようなものがあります。曰く、AIが普及する未来では「AIには生み出せない人間ならではの新しい音楽性や可能性」が、これまで以上に再評価されるだろう──というものです。AIが統計的に妥当な答えを出力するという性質を踏まえれば、音楽的文脈や個性を人間が付加していくことが重要となっていくのは、自然な方向性だと言えます。
宇野氏の「庭」の概念は、AI時代における人間ならではの創造性を考える上でとても重要です。宇野氏が「庭」を、「支配できない場所」「偶発性に出会うための場所」「事物そのものへのコミュニケーションを取り戻すための場所」と定義していることから分かるように、AIが生成する「統計的な正解」や「典型」ではない、予測不能で有機的なズレ・ノイズを積極的に取り込む姿勢こそが、人間とAIとの「庭における共生」を可能にすると考えられます。
AIツールは、デジタルな「庭」における「素材」や「自然な成長」を提供できます。AIは効率的に多様な素材やバリエーションを生成する「動く乱数供給源」として機能するのです。これに対し、人間の作曲家は、こうしたAIからの出力に対して、宇野氏が提唱する「多自然ガーデニング」の概念のように「ガーデニング」を行う役割を担うことになります。
具体的には、生成された素材を単に受け入れるだけでなく、それを選択し、洗練させ、AI単独では考案できないような「不完全さ」や「逸脱」、あるいは作曲家自身の独自の芸術的解釈を意図的に導入することで、作品に唯一無二の価値を付加していくということです。
AIの生成物を人間が「ガーデニング」するプロセスは、人間特有の創造性や感性によってのみ生まれる「音楽的価値」の重要性を浮き彫りにします。これは、AIが提示する「正解」や「典型」では捉えきれない領域です。
かつて写真が世の中に登場したとき、絵画が「現実の忠実な描写」という役割から解放された結果、画家の内面や表現そのものの価値が高まったという経緯があります。同様にAIの進化も、音楽における「人間ならではの感性」や「意図的なズレ」の重要性を際立たせることでしょう。
つまり、AIが効率的な「正解」を生み出すほど、それは人間が創り出す「不完全さ」や「予測不能な美しさ」といった要素がより深く新たな形で評価されるための、その「きっかけ」として活かされるようになるわけです。
これはAI時代における人間の創造性を再定義するものです。DAW作曲家は、AIの苦手とする「混沌」や「予測不可能性」を積極的に受け入れる姿勢が求められます。そしてその姿勢を、自身の内面から湧き出る探求心と環境の偶発性を受け入れる「庭という創造プロセス」の核とするのです。
こうすることで、AI時代のDAW音楽制作は、単なる効率的なアウトプットに終わらず、人間の意図と偶発性によって常に駆動され進化し続ける、そんな芸術形式であり続けられるのではないでしょうか。
DAW音楽制作の未来へ~「庭」の思想が導く創造性
これまでの議論を通して、宇野常寛氏の『庭の話』が、DAWを用いた音楽制作の実践、そして現代のプラットフォーム社会におけるDAW作曲家の立ち位置について、いかに興味深い洞察をもたらしてくれるのかを見てきました。
最後にこれまでの内容をまとめ、DAW作曲家がAI時代にどのように創造性を育み、その未来を切り拓いていけるのか、その指針を検討していこうと思います。
『庭の話』は、DAW作曲家が現代社会において直面する多岐にわたる課題、特にプラットフォームによる「承認欲求の肥大化」とそれに伴う「創作の画一化」に対し、深い洞察と具体的な解決の糸口を提供してくれています。本書の核心である「庭」というメタファーによって、デジタル空間における創作活動の望ましい環境と、作曲家が選び取れるひとつの創造的な姿勢を描き出せるようになるわけです。
DAWという制作環境そのものが、作曲家が綿密に設計しコントロールする「家」としての側面を持ちながらも、同時に予測不能な「偶発性」や「非人間との協働」を許容する「庭」となり得るという視点は、デジタル空間での創作活動に新たな意味と価値をもたらすものと言えるでしょう。この二重性は、計画された構造の中に予期せぬ「生命」を吹き込み、デジタル環境における作曲家の創造的な「成長」を促すことを可能にするはずです。
「制作に没頭する喜び」「正しい孤独の確保」「非人間との協働」「偶発性の受容」といった「庭」の概念は、デジタル時代の音楽制作における本質的な創造性を育む上で大切な指針となることでしょう。
これらの概念は、プラットフォームの画一化された情報環境や承認ゲームから距離を置き、事物そのもの、音そのものとの直接的なコミュニケーションを取り戻すためのメタファーとして機能します。そしてこのアプローチは、SNS上の「相互評価のゲーム」や「アテンション・エコノミー」の、その外部で思考し発信する姿勢へと繋がっていきます。
この「庭」という概念は、技術の進化が加速し、AIが創作の領域に深く入り込む現代において、人間ならではの創造性、すなわち「意図せぬものとの出会い」「コントロールできないものとの共生」を追求する姿勢の重要性を再認識させてくれます。つまり豊かな創造性は、「家」の中だけでなく、偶発性と多様性に満ちた「庭」の中でこそ育まれるのではないか、ということです。
DAW作曲家は、自身の制作環境を単なる効率化ツールとしてではなく、「多自然ガーデニング」を実践する「庭」として捉えることで、新たな視野が広がるはずです。これは、様々なデジタル要素(プラグイン、サンプル、アルゴリズム)を「動く乱数供給源」として受け入れ、それらが織りなす音の生態系を育むという姿勢を意味します。プラットフォーム上での発信と評価の追求に過度に囚われず、自宅スタジオという「孤独」な空間で音と真摯に向き合い「制作に没頭」すること。そのことの価値を再認識することが大切だと思います。
そしてAIなどの新たな技術を、創造性を刺激する「動く乱数供給源」として積極的に取り入れつつ、AIには生み出せない人間ならではの「ズレ」や「ノイズ」、そして「物語」を音楽に織り込むことで、唯一無二の「庭」をガーデニングして創造し続けること、それがこれからのDAW作曲家には求められるのではないでしょうか。
そして豊かな創造性は他者の承認の外部に存在しており、それは自らの「庭」を耕し続けることによって育まれる──そう『庭の話』は語りかけているのだと思います。
関連記事