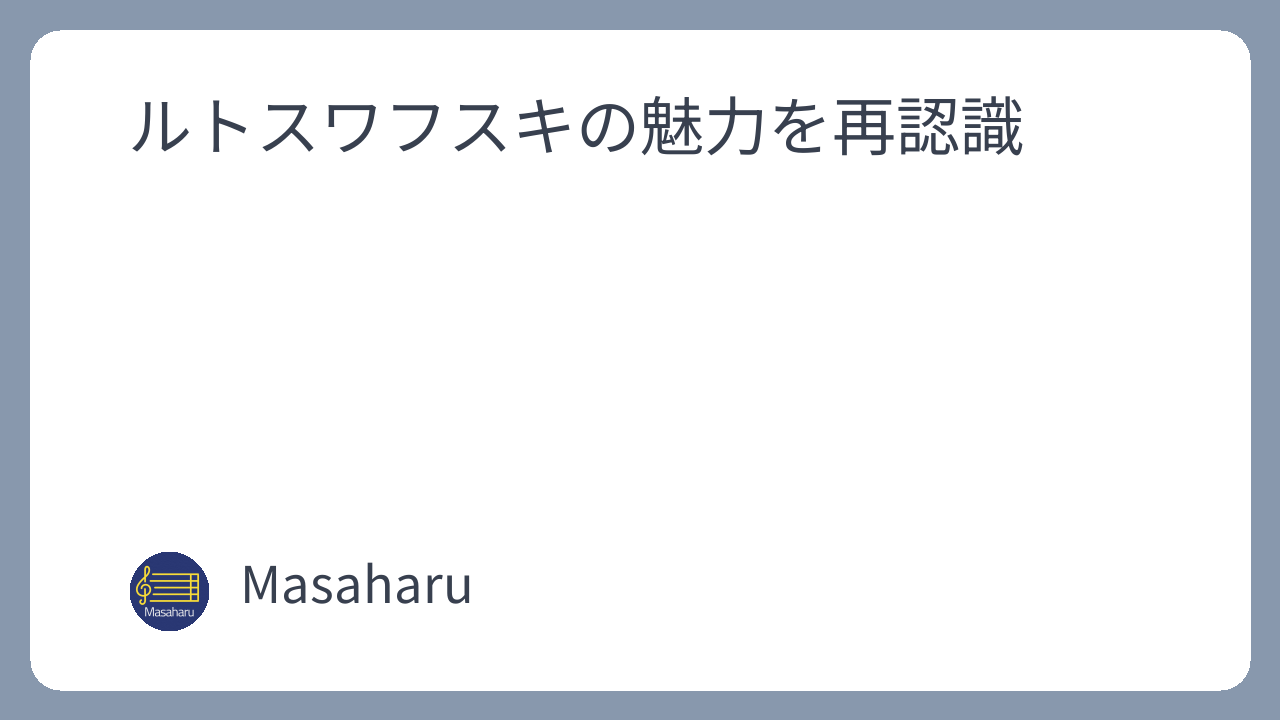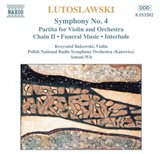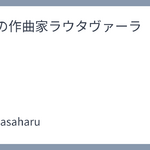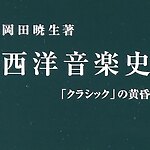(初出2006年6月14日)
ルトスワフスキ(Witold Lutoslawski 1913-1994)のNAXOS盤『Symphony No.4』より、『間奏曲(interlude)』を改めて聴く。
先日、ネオ・ロマン関連でラウタヴァーラを取り上げたことをきっかけに、手持ちのNAXOS盤を聴き直したりしています。そんな中、耳を惹いたのはルトスワフスキでした。
ルトスワフスキは、コントロールされた不確定性という手法によって音楽を生み出しており、『交響曲第3番』や『チェーン』シリーズ、『ヴェネチアの遊び』といった曲で有名な作曲家です。個人的には交響曲3番が好きです。
「ダダダダ!」というモチーフの迫力と唐突さがもたらす「つまずき、つんのめるような疾走感」。それを絡めた「コントロールされた不確定性」によって生み出される、「音の量感や、密度の質感の変容」。そして、聴き手の内に生じる緊張感をすら作者の手中に置き、グイグイと進めていくその構成の妙。これらには感銘を受けずにはおられません。
別の魅力としては、「ビターで冷たく、でも手触りはベルベットのようなきめ細やかさ」という、その独特の和声感覚があげられるでしょう。今回取り上げた「間奏曲(interlude)」では、その味わいをじっくりと楽しむことが出来ます。
「ゆったりとした響きの交代」を提示し続けるストリングスを曲の生地とし、そこへため息まじりの独り言のような断片的フレーズが、遠近感を伴いながら出入りします。
この遠近感の生み出し方が絶妙で、木管楽器による木訥とした表情が眼前に現れたり、弦の一群が遠く深いところに顔を出すかのように奏されたり、さらにはその逆(遠く深いところに顔を出す木訥とした木管とか)だったりと、渋い多彩さを持っています。
このスタイルはルトスワフスキの得意技の一つと言え、部分的な活用は様々な曲で見つかりますし、『3つのポストリュード第1番』などではそのシンプルかつ効果的な例を耳にすることが出来ます。
さて『間奏曲』についてですが、特筆すべきは3分37秒付近、ほのかに香り立つ弦の甘い響きとトロンボーンの下降音、そしてチューブラーベルの音へと連なるところです。ここをひとつの構成上の頂点とした後、穏やかに収斂と収束(文字通り構成音が減少)への道を辿り始めていきます。
この『間奏曲』は、演奏会において『チェーン2』と『パルティータ』をつなぐ曲として構想されたものなのですが、個人的にはむしろ単体で楽しむことをお薦めしたいところです。
薬学的な音楽聴取という視点からはあまりコメントしたくはないのですが、癒しとは違った「静かな覚醒」を聴き手にもたらす印象があります。そして何か、広く閉じた空間といった趣を感じさせるのです。
ちなみに、この曲の入っているCDはもともと『交響曲4番』を目当てに手に入れた物だったので、『間奏曲』は一回聴き流した程度でした。今回、ラウタヴァーラからの流れという耳で聴き返してみたところ、その音楽世界には溜め息が出ました。また、初回の聴取時に反応しなかった事実を通じ、聴き手の状態の変化や聴く姿勢の影響力を考えさせられもした一件でした。