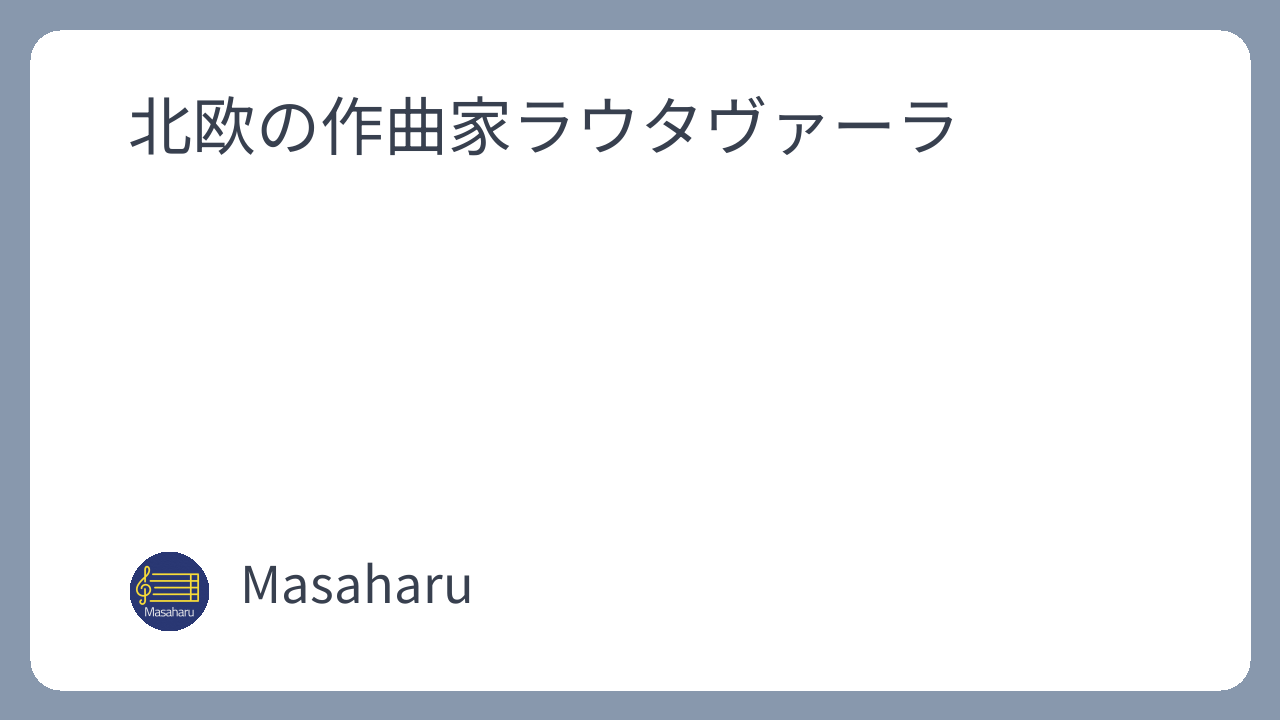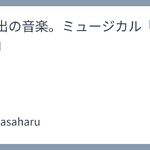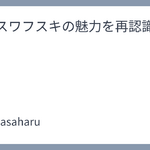(初出2006年6月9日)
ラウタヴァーラ(Einojuhani Eautavaara 1928- )の交響曲第3番&7番&8番、ピアノ協奏曲第2番&第3番などを聴く。
NAXOSのサイトには充実した試聴音源が用意されているので、未知の作曲家に出会え便利です。世間の評判を元に探りを入れるもよし、百科事典をランダムに開けるように聴きまわるもよしです。
そんなわけで、ネオ・ロマンやネオ・シンプリシティやミニマルを色々と聴いてみようと、最初はペルトやグレツキやアダムス辺りの情報を追いながら聴いていたのですが、そうしている内にラウタヴァーラに辿りつきました。
私の不勉強で、このラウタヴァーラは北欧出身の作曲家としては最も著名な方だということを知りませんでした。しかも響きの世界が結構、というか、かなり好みです。もっと早くに知りたかったと思うと同時に、ブームが苦手な私としては「交響曲7番のブームと距離を置けてよかった」と思ったりもして複雑な心境です。
あと、ネオ・ロマンやネオ・シンプリシティなどの音楽史の流れにおける位置づけのことよりも、ラウタヴァーラの音楽的個人史に興味を惹かれました。
70年代ごろにかなりロマンティックな作風に変わるのですが、初期の作品のセリー的な厳しい響きの中にも現在のラウタヴァーラ味のするハーモニーが感じられる辺り、良い意味で頑固な感覚を錬成されてきたのだなと思わされます。
ちなみに、以前スカルソープの曲を聴いたときにも感じたことなのですが、リリカルであったり個人的なロマンティシズムの表出を感じさせる作曲家を前にすると、その人の作曲の軌跡を辿りたくなります。これは私の切羽詰った音楽的な自己刷新願望から生じる欲求なのかもしれませんが。
これを機会に、ラウタヴァーラの他の多くの作品をはじめ、北欧の作曲家の作品に色々と触れてみようと思います。
追記:セリエルから調性へ~その根底に流れるもの
(2025年5月15日追記)
改めて、ラウタヴァーラといえば、鳥の声を取り入れたり、壮大で美しい響きを持った後期の作品で知られ、比較的親しみやすい現代音楽の作曲家というイメージを持つ人が多いかもしれません。
しかし彼のキャリアを遡ると、初期には十二音技法やセリー音楽に深く関わっていた時期があります。初期の作品と後期の作品とでは表面的な音楽語法が全く異なり、一見すると同じ作曲家が書いたとは思えないほどです。初期のセリエル作品(セリー音楽)は、ある種の厳密さや硬質さを持っていますが、後期の作品は明確な旋律や和音が登場し、抒情的で広大な響きに満ちています。
なぜこれほどまでに作風が変化したのか、そしてこの異なる二つの時期の作品の間に、何か共通する「ラウタヴァーラらしさ」は存在するのかについて考えてみます。
ラウタヴァーラの作風の変化は、ある種の「技術」や「理論」を、自身の表現のためにどう選択し、使いこなしたのかという視点で見ると、興味深い洞察が得られるのではないかと思います。
例えば、初期のセリエル期から後期の調性期への大きな転換の背後にある共通性として、以下の点が挙げられるでしょう。
A. 音響への強いこだわりとテクスチュアの構築力
セリエル技法とは、音高やリズムなどを数列に基づいて厳密に構成する手法ですが、ラウタヴァーラは初期の頃から、単なる機械的な操作に留まらず、そこから生まれる響きそのものに強い関心を持っていたように思われます。
独特の音の重ね方や楽器の組み合わせによって生まれるテクスチュアは、初期の頃から特徴的です。これは後期の作品でも同様で、明確な和音を用いながらもラウタヴァーラのオーケストレーションは常に独特で、透明感や深みのある音響空間を作り出しています。初期に培われた、音の粒子や層を緻密に扱う感覚が、後期の豊かなテクスチュアに繋がっているのではないでしょうか。
B. 形式への意識と作品全体の構成力
ラウタヴァーラの作品は、表面的な響きが異なる作品であっても、多くの場合、共通してそれらはしっかりとした形式感を持っています。彼の音楽は、ある種の「秩序」や「論理」に基づいて構築されていると感じられます。
セリエル期には音列がその論理を支えましたが、後期にはより自由な形式や、自身の内的な音楽の流れに沿った構成を選んでいます。しかし作品全体を破綻させず、一つのまとまりとして聴かせる構成力は、初期から一貫しています。これは、混沌とした響きの中から音楽的な必然性を見出そうとする、作曲家としての根本的な姿勢を示すものだと思います。
C. 「神秘性」や「超越性」への絶え間ない希求
ラウタヴァーラの作品を語る上で重要な要素の一つが、彼の音楽に共通して流れる神秘的でどこか超越的な雰囲気でしょう。初期のセリエル作品にも、単なる音響の羅列ではない、内省的で宇宙的な響きを感じさせる瞬間があります。後期の作品では、美しい旋律や壮大な和音が用いられることで、この神秘性がより直接的に聴き手の心に響く形で表現されるようになりました。
《カントゥス・アークティクス》での人間と自然(鳥)との融合、あるいはオペラ作品に登場する内省的かつ神話的な世界観など、そのテーマは多岐にわたります。技法がどうであれ、ラウタヴァーラは常に日常を超えた精神世界や、世界の根源に触れるような音楽を目指していたと言えるでしょう。
D. 旋律への潜在的あるいは顕在的な意識
セリー音楽では、伝統的な意味での「旋律」は断片化されることが多いですが、ラウタヴァーラの初期作品からは、音列から抽出される音程関係の中に独特の旋律的な「気配」のようなものを感じ取ることができます。
後期の作品ではこの旋律性が全面的に開花し、聴き手の耳に心地よく響く「歌」となります。しかし、その旋律は単に分かりやすいだけでなく、ラウタヴァーラ独特の浮遊感や予測不能な美しさを兼ね備えています。これは、初期の音程への鋭敏な感覚が、後期のユニークな旋律法に繋がっている可能性を示唆しています。
◇
──以上のように見てみると、ラウタヴァーラの作風の変遷は単なる流行や聴衆への迎合ではなく、彼自身の内的な音楽的なヴィジョンを実現するために、様々な技法を柔軟なツールとして選択してきた結果であるように思えます。セリエル技法も、調性的な語法も、彼にとっては自身の追求する「音響」「形式」「神秘性」といった音楽の本質を形にするための異なる手段だったのではないでしょうか。
ラウタヴァーラの作品は、作曲家が何を表現しようとしているのかについて、表面的なスタイルにとらわれず、その根底に流れる思想や美意識に耳を澄ませることの重要性を改めて教えてくれます。彼の初期と後期の作品を聴き比べることで、技法の違いを超えた作曲家の個性や、音楽が持つ多様な表現の可能性を感じ取ることが出来るのではないでしょうか。