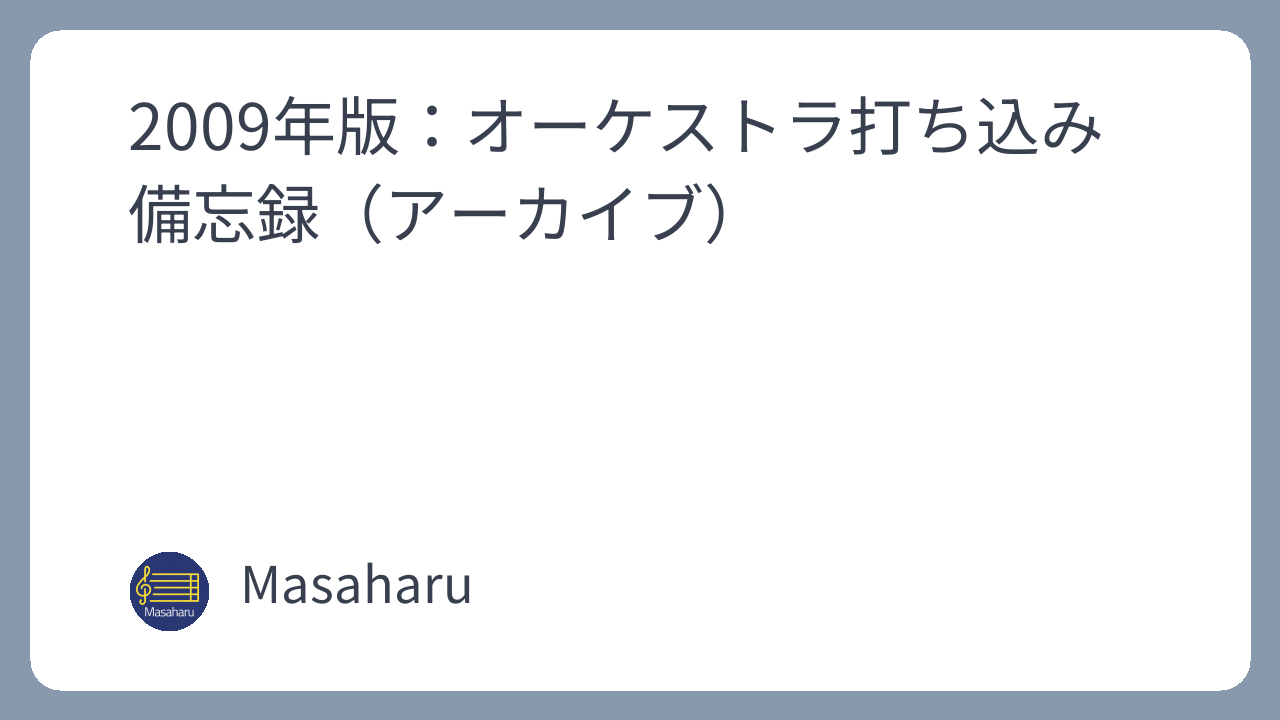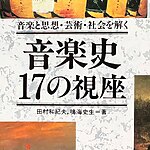※はじめに~注意書き
この記事の内容は、2009年当時のものです。
これは「当時の制作環境の記録・アーカイブ」として掲載しているものであり、現在の制作環境や状況とは異なります。
オーケストラ打ち込み備忘録(1)音源のこと
ここ数年、オーケストラサウンドを打ち込みで表現するための環境は大きく変化しました。中でもエポックメイキングな出来事だったのが「Vienna」と「QLSO」というオーケストラ音源の登場だったと言えるでしょう。
使用音源はQLSO Gold Complete
それらは巨大かつ大量の録音サンプルからなっており、発音の強弱はもちろん、各音階ごとに細かくサンプリングされているのが特徴です。そのため、それまでは困難だった「音域の違いによる音色変化」の表現が自然に行えるようになりました(さらにViennaに至っては、レガート演奏の際の音の連続変化(トランジション)も表現可能になっています)。
これにより、実際のオーケストレーションのノウハウを用いた際の効果もグッと高まり、以前と比べて飛躍的に豊かな表現を行うことが可能となりました。
私が使用しているのは、両者の中でもサウンドカラーが個性的なQLSO(Gold Complete)です。メーカーサイトのデモを聴くとお分かりのように、ハリウッド映画のサントラの様な派手なサウンドを得意に、というか、それに特化したかのような音が特徴の音源です。
そのフォルティッシモは力強く、金管楽器や打楽器などはギラ付いた輝きのある響きを聞かせてくれます。また、ピアニッシモの音も繊細でありながら存在感がしっかりとあるのが良いところです。例えば、ミュート付き弦楽器のベルベットのような響きや、ピアニッシモのトランペットでの透明感ある響きをはじめ、魅力的な音色が数多くあります。
他にも、ミュートトロンボーンによる低い音域での和音、イングリッシュホルンの柔和なビブラート、バスクラリネットの深く静かに鳴動する低音、他の楽器に明瞭なふくよかさを与えるティンパニのやわらかい一打、高域の弱奏フレンチホルンが生む凛とした音空間などなど、枚挙に暇はありません。
しかし逆に言えば、室内楽サウンドや丸く温かみのある表現を行ったり、デッドな(響かない)空間での演奏を表現したい場合には足かせとなります。ですが私の場合、まず第一にリッチなフルオーケストラの響きが欲しかったので、それらのマイナスを差し引いてもQLSOを選択するメリットがありました。
QLSOの設定
使用しているWindowsが依然としてXP、メモリが3GBという32bit環境であるため、フルオーケストラを用いる際には旧Kompakt版を使用しています。理由は、プリロード設定を最小にすることで大きな編成でも一台のPCで作業を完結できるためです。
しかし、細かい音符でのフルテュッティといった場面ではHDDストリーミング速度が追い付かず、発音が途切れるケースが出てきますので、適宜バウンスなどで対応する必要があります。
とは言え実際の制作作業においては、発音された音色が順次メモリにキャッシュされるため、編集再生を繰り返すほど発音切れが無くなっていきます。ですので、「特定の箇所を編集したら次の箇所へ」というプロセスで作業する分には音切れは大きな問題にはならないと感じています。
Kompakt版の便利な点は、一つのKompakt Player内で同一パッチを読み込む分には、いくつ読み込んでもパッチ一つ分のメモリしか消費しないことです。
つまり、例えばキースイッチパッチのホルンを四つ読み込んでそれぞれホルン1~4として割り当てても、メモリは一つ分で収まるということです。これにより、ひとつの楽器ごとの丁寧な表情付けが無理なく行えます。
私の場合、三管編成に相当する楽器それぞれに一つづつトラックを用意したものをテンプレートとして準備しています(ストリングスはディビジ用として2パートづつ)。
QLSOと言えばその濃厚な残響音が特徴であり、その一翼を担うのがリリーストレイルと呼ばれる「減衰音のみのサンプル」です。これがノートオフ時に付加されることでホールの残響を再現しているのですが、私の場合はこれをオフにし、改めてIRリバーブを掛けています。
その理由はいくつかあり、一つ目は、ホルンやクラリネットの一部などに、どうしても不自然な残響イメージの減衰音があるため、その対策としてリバーブを掛け直すという理由からです。
二つ目は、コラール的な演奏では素晴らしい響きを聴かせてくれるのですが、フォルテピアノなどの各種アクセントやロングトーンを徐々に弱めていく演奏などでは、残響音ごと同時にそのまま小さな音になっていく不自然さがあるため、これもまた改めてリバーブを掛け直したほうが良いという理由からです。
最後の一つは、スタッカート系音色の表現力を上げるためです。スタッカート系の音色にはリリーストレイルは用意されておらず、ホールの残響が含まれた状態で録音されており、初期設定だとノートオフのタイミングは指定できない(常に鳴らし切る)という設定になっています。
そのため、細かい(短い)ソリッドなスタッカートを表現しようと思っても、いつも同じ細かさ(長さ)のスタッカートになってしまいます。そこで、初期設定では極めて大きな値になっているリリースタイムを短く設定し直し、操作性を上げています。そのように修正した結果再生されなくなった残響部分を補うために、リバーブを掛け直す必要が出てくるわけです。
以上が基本的なQLSOの設定です。これらをベースにオーケストレーションを進めています。
オーケストラ打ち込み備忘録(2)DAWのこと
以前は長年に渡りWindows版のLogic Platinumを使用していたのですが、開発元の買収&撤退によってバージョンアップも既に止まっていたため、VSTの互換性などの面で支障が大きくなっていました。そこで、2007年にようやく重い腰を上げてSONARに乗り換えを行った次第です(この辺りの経緯について興味がお有りの方は「PCとシーケンサ(DAW)を一新した際の考察」をご覧下さい)。
一般にオーケストラ音楽の打ち込みには、リアルタイム入力、スコア画面(楽譜)入力、ピアノロール入力といった方法がありますが、私の場合は部分的にリアルタイム入力を行いつつも、基本的にピアノロール画面で入力と編集/調整を行っています。
シーケンスソフト(DAW)はSONAR
SONARはVer.7以降、ピアノロールでの編集機能が向上しており、その点が乗り換え時のポイントの一つでもありました。ピアノロールでの編集アクションを自分で自由にキーアサイン出来るため、Logicでの操作体系をそのまま持ち込むことが可能だったのです。
ピアノロールでよく行う操作は、ベロシティ調整、デュレーション(音符長)変更、タイミング微調整、そして各種コントロールチェンジ情報の入力/編集です。
表情付けのキモとして膨大な量のCC11(コントロールチェンジNo.11)を入力するわけですが、その際にはマウスでの直線&自由曲線入力と併せて、MIDIキーボードのホイールでのリアルタイム入力も行っています。
ちなみに、SONARには「CAL(Cakewalk Application Language)」というスクリプト言語が実装されており、これを用いることで煩雑なノート編集を自動化したり、よく行う編集をテンプレート化して適宜適用させることが可能です。
私は主にノートタイミングのランダマイズ(ごく僅かに散らす)とレガート(前後の音をデュレーション100%にしてつなげる)に使用しています。個々のスクリプトの実行を任意のショートカットに当てはめられるのが便利なところです。
オーケストラ曲用テンプレート
オーケストラのように編成の大きな音楽を制作するに当たっては、自分なりのテンプレートファイルを用意しておくことが重要です。私の場合、キースイッチパッチを中心に1パートずつトラックに立ち上げた、三管編成+編入楽器のテンプレートを用意しています。
各楽器ごとの表情付けに際してなるべく制約を設けないように、例えばホルンの場合、4(6)パート各々とセクション全体の演奏用として、キースイッチパッチとスタッカート系と特殊奏法のパッチを立ち上げてあります。
ただ、このまま各パートと奏法別にトラックを割り当ててしまうとあまりにも数が増えてしまうので、実際にはMIDIデータでのチャンネル情報を用いてパッチを切り替えるという前提でトラックを用意しています。
例えば、CH(チャンネル)1にソロホルンのキースイッチパッチ、CH2にソロホルンのスタッカートパッチ、CH7にセクションホルンのキースイッチパッチ~としておき、ひとつのMIDIトラック上でノートごとにCH情報を割り振っていくわけです。
こうしておくと一つのトラック内でソロとセクションなどを扱えるので見通しがよいです。その結果、現在のフルオケ用テンプレートは全体で100トラック弱に抑えられています。これは丁度、使い勝手の良い大きめの白紙の五線紙を用意しておくことに等しいです。
テンプレートで大切なのは、それら各パッチ間の音量バランスです。木管、金管、弦、打楽器それぞれのバランスと、ソロとセクションとのバランスを調整するわけですが、簡単な手順としてはff(フォルティッシモ)の全合奏フレーズを用意し打ち込んでバランスを見るのが良いでしょう。その際のお手本としては、CD演奏を参照するのが妥当と言えます。
ffでのバランスが良ければ、弱奏時のバランスは比較的容易に取れます。このとき、音色によってはベロシティカーブを緩く(変化幅を狭く)してやる必要があるかもしれません。
QLSOの場合、ベロシティレイヤーの最弱音色がベロシティ値70以下あたりに設定されているため、pp(ピアニッシモ)の全合奏においてはベロシティ値の調整で収まるケースが多いです(例。弦のpp=Vel.50の時、オーボエのpp=vel.65など)。
以前、この調整を行っていた際には、全合奏におけるff金管の圧倒的な存在感のことや、木管が目立つ時というのは音量の大小の結果というより音色の個性が浮かび上がっているためである等、改めて気付かされる点も多かったです。今もなお、そういったことを踏まえながら一曲ごとにテンプレートの修正/更新を重ねています。
※2025年追記
当時、QLSOを使用して制作した作品からいくつか紹介します。
QLSOは、舞台作品の制作でも活躍しました。その際はミックスのやりやすさもあってスピーディーな制作が可能でしたし、サンプル音の残響成分やサイズ感が上手く収まる限りにおいて、QLSOはその実力を存分に発揮してくれました。
以上、「2009年版:オーケストラ打ち込み備忘録(アーカイブ)」という形で、当時の記事を再掲しました。