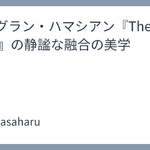タイトルチューンの『Phantom Gleam』(原題『幻の輝き』)では、曖昧模糊としたドローンサウンドやエフェクティブなリズムが幾重にもレイヤリングされ、それらがクロスフェードされながら進んでいく。そこへ加えて、タイトルに示されている「輝き」を象徴するように、ぎらついたシンセ音が明るく高らかにハーモニーを奏でる。しかし常にその背後にあるのは、必ずしも輝きを全肯定しようとしない、一筋縄ではいかないリズムとドローンサウンド群である。
一度は世界を明るく照らしたその「輝き」は、夜空の花火が消えゆくように去っていく。その後、音楽の前景に戻って来るのは、気だるさと重さ、そして言葉に出来ない不安を表すようなリズムとドローンサウンドであり、シンセによる輝かしいハーモニーは単純にそのようには受け取れなくなってくる。
『Phantom Gleam』からは力強さや、リズムのキレを感じさせる瞬間もあるが、全体を覆っているのは鬱屈したエネルギーから発せられる鈍い叫びのような、リスナーの心をざわつかせる独特の不安と緊張感といえるのではないだろうか。
作者は『人の内面世界を象徴するものを創作する際には、単純なラベリングで捉えられるような形としてではなく、多面的・多義的かつ不分明な状態そのものを具現化させることに興味がある』と述べており、もしリスナーが「ある種の寄る辺なさや割り切れなさ」とでもいうような感触を感じるならば、それは作者の意図通りと言えるだろう。
続く『Twilight Chant』(原題『黄昏の詠唱』)は、金属打楽器でアクセントを添えられたドローンサウンドと、トラディショナルな女声合唱によるコラールによって、独特の浮遊感のある世界を描出する一曲。
特徴的な女声合唱は、バロックや古典派の合唱曲ような対位法に則ったポリフォニーではなく、ひとつの旋律に対してジャズのボイシングが施されている。テンション・ノートを含む各声部が密集配置によってハーモナイズされており、クラシカルなコーラスの形態でありながらジャジー(Jazzy)なサウンドを響かせているのが分かる。
作者曰く、この合唱パートは独立したものとして作曲された後、いくつかのパートに分割・再構成され、最終的には他のリズムやドローンなどのサウンドパーツと共にコラージュ手法によってまとめ上げられた。いうなれば「女声合唱と落ち着いた16ビートのリズムとのコール・アンド・レスポンス」という形で、大きな呼吸を繰り返すようにうごめき流れる音楽になっている。
極単純な通奏低音のように一貫して同じ響きを奏で続けるドローンサウンドは、合唱パートとハーモニー的には多くの時間において整合した響きを生み出しており、それ以外の時間でも微妙で繊細な「付かず離れず」の関係を維持し、豊かな音楽的響きを演出している。このことが本曲の独特の浮遊感の要因のひとつと言えるだろう。
三曲目の『Echoing Solitude』(原題『こだまする孤独』)では、広い空間の中で低くうなるドローンとエフェクティブなギターや効果音、そしてシンセパッドらが互いに呼びかけ合いながら、一つの空間を満たしていく。
すべての音素材が広い空間を意識させるように加工されていることもあり、リスナーは意識を集中させればさせるほど寄る辺無さを感じさせられると同時に、タイトルにも示されているように孤独を想起させられ、その孤独は静かに押しては引くようにこだまする。
例えるなら、ベクシンスキーの絵画を見たときのような不安と怖れ、そして静謐さをもたらすような世界でもあり、時間の止まった「広大な幻想空間」に閉じ込められたような印象を抱かせる。
この音楽的空間は、終盤に到達したところで「時間のほころび」のように響く効果音が繰り返され、その反復が徐々に緩やかになり、やがて停止することで終わりを迎える。それまでは寄る辺ない孤独のこだまの中に佇んでいたリスナーは、こうして結果的に無音のなかに取り残されてしまい、そこで最も大きな孤独を感じることになるのだろう。
三曲とも重みやうねりを感じさせるドローンサウンドから始まり、初めの二曲では明瞭なリズムやハーモニー、合唱といった要素が前景に立ち現れてくるが、三曲目ではそういった要素が目立ってこない。三曲を続けて聴くと、前述した『Echoing Solitude』の特徴がより一層実感させられ、そのタイトルの意味するところを幾ばくかの精神的な肌寒さと共に理解することになるだろう。
このように三曲の姿は一見どれも異なって見えるが、そこには通底するものがあることが分かる。そしてその特徴がもつ力はリスナーを安全地帯にとどめておかず、一時的に居心地の悪い場所へと引き出してくる。それは「感性的な自己対話への誘い」と言えるのかもしれない。