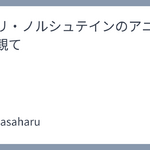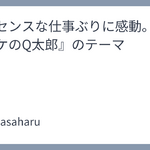タイトルチューンである一曲目『Warmth of Stagnation』は、ゆったりとしたアルペジオがリズムパターンと和音を微妙に変化させながら反復していくシンプルな曲だ。浮遊感のあるゆらめくシンセ音によって、リズムやハーモニーが溶融するような曖昧な印象を聴き手に抱かせる。
一聴してミニマル的なアンビエントミュージックを思わせる始まりを見せる本曲は、しばらくするとアルペジオパターンが伸縮し始め、和音も微細だが明確な変化を見せるようになる。
そんな中、アルペジオのトップノートだけは一定の音程を響かせ続け、うごめくように変容し続ける和音をつなぎとめるかのように屹然とそこに在り続ける。そのトップノートは、ときに大きく、ときに囁くように控えめに、反復されるアルペジオに対してまるで何か配慮しているかのような表情を見せるのが興味深い。
タイトルにもあるように、基本的には劇的変化と呼べるようなものは訪れず、文字通り停滞し滞留するかのような安寧をそこに感じさせる。
しかし変わらない日常の中にも個人的で内省的な揺らぎや変容が訪れるように、本曲の後半から終盤にかけて、和音の色彩とアルペジオのリズムにこれまでとは異なるうねりが生まれ始める。
この小さく内省的な物語のひとつのピークと呼べるのは、4分42秒からのアルペジオで始めて見られるトップノートの半音下降だろう。
これまでアルペジオの和音とのおぼつかない調和を保ってきたトップノートは、ここで苦み走った音程を一瞬響かせた後、まるでそれを嫌うかのように(もしくは恥じ入るかのように)、半音下がる。それを切っ掛けにアルペジオは崩れるような下降パターンを描き、それまでの形を維持することをやめ、静かな終焉へと向かい始めるのだ。
曲の冒頭から存在感を示してきたアルペジオのトップノートは、果たしてこの停滞に閉じ込められた主人公であったのだろうか。
物語的な音楽時間を構成することを意識する作者らしく、ミニマルで反復的なアンビエント音楽にも独自の構成感覚を持ち込み、リスナーを濃度の高い音楽体験へと誘う。本曲はその点で、作者の音楽的コンセプトがシンプルな音楽素材によって表現されたものとして、印象的なモデルケースだと言えるだろう。
カップリング曲の『Radio and the Moon』は、単一の音色で奏でられるシンセ音こそ前曲と似た印象を感じさせるが、その音楽は古いオルゴールのようなほの暗いセンチメンタルさをはらんでおり、曲から感じられる雰囲気は大きく異なる。
メロディーと伴奏が明確に存在しているため、一見すると分かりやすさが感じられる。しかしそのメロディーは曲中で明確に反復されることが無く、変奏とも即興ともつかぬメロディーラインが時間の中をたゆたっていく。
そしてここでも特徴的なのは、構成された音楽時間のその濃度の高さであろう。この僅か2分ほどの音楽に込められた時間構成の技術とそれによる効果は、用いられている音色が単一であることによって、より一層明瞭に感じることが出来るはずだ。
それはまるで短編小説を読み終えたような充実感をもたらし、ふんわりとした曲想による印象と同時に堅牢な構築感や凝縮感も聴き手に与える──といえば言い過ぎだろうか。
今回の2曲はどちらも単一のシンセ音色によって奏でられており、サウンド面での劇的効果は避けられている。そのため音楽の構成面での特徴を捉えやすくなっている。その点からも、作者の物語的な構成感覚の一端を知り理解する入り口として、それに相応しいラインナップとなっている。