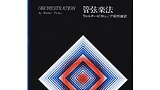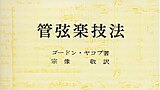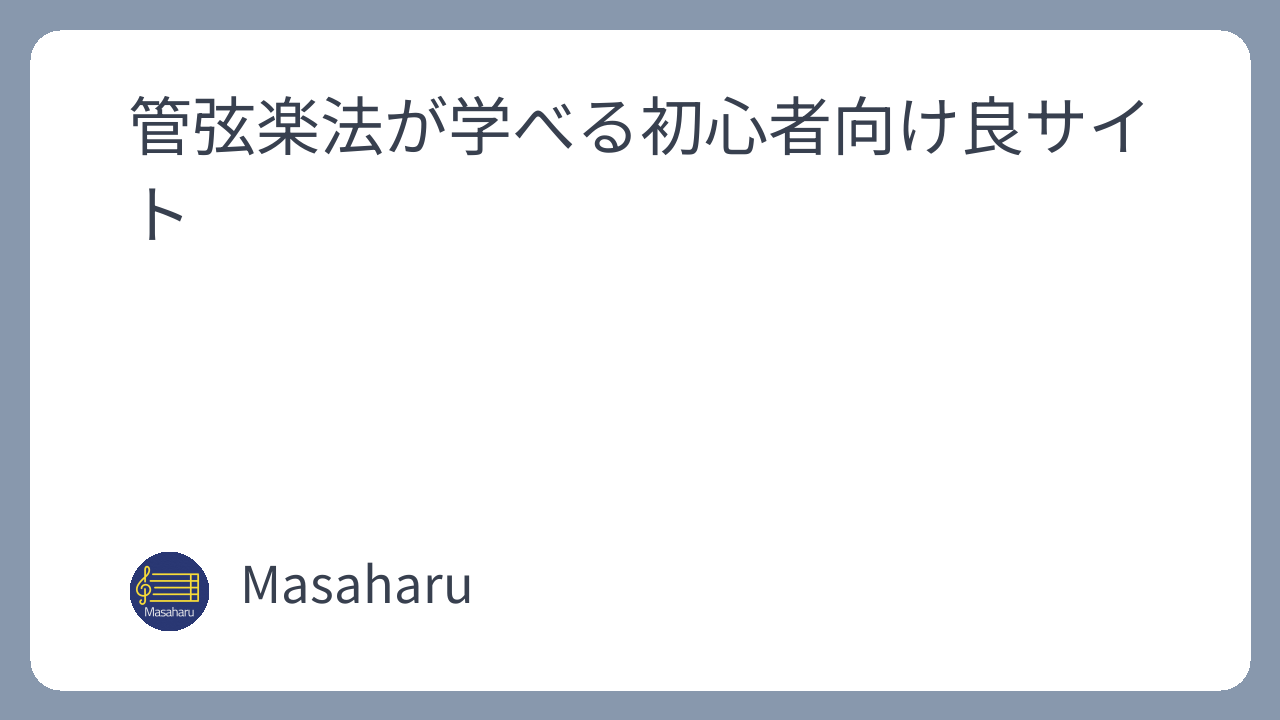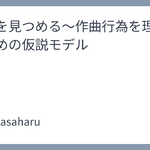ソフトウェア音源で本格的なオーケストラ・サウンドを使いたい、でも具体的な方法が分からない、勉強したい。──そんな初心者に役立つサイトを二つご紹介します。
カンタン・オーケストレーション
一つ目は「カンタン・オーケストレーション」というサイトです。「最低限の勉強で、オーケストラっぽいオーケストレーションを」というスローガンのもと、各楽器の特徴から実際のオーケストレーションまで、参考音源を豊富に用いながら平易に解説されています。
作者自身、「自分が仕事をしていく上で『こういうことを最初に知りたかった』ということを中心に書いた」と述べられているように、最初の一歩を踏み出すための道案内として要点がシンプルにまとめられているのが素晴らしいです。
初心者向けサイトは雑多なものになってしまうか、ただ易しいだけでポイントが押さえられていない、という辺りに陥ってしまいがちですが、このサイトはそんなところが見られません。
OTO×NOMA オーケストレーションカリキュラム
二つ目は、音楽学習ポータルサイト「OTO×NOMA(オトノマ)」のオーケストレーションカリキュラムです。

動画セミナー以外の記事は無料で読むことが出来ます。
オーケストラを構成する各楽器の基礎知識に始まり、本格的なオーケストラサウンドを実現するためのアレンジテクニック、さらには、リアルな打ち込みを実現するモックアップテクニックまで、オーケストレーションに必要な一通りの知識が網羅されています。
特徴は、オーケストレーションの実践テクニックについて、実際の手順に沿って詳しく解説されている点です。オーケストレーションの際に大切な二つの視点のことや、楽器同士の相性、各楽器群の音量バランスなど、押さえておくべき要素について丁寧に解説されています。
リムスキー=コルサコフ著『管弦楽法原理』について
過去には、Principles of Orchestration On-lineという良サイトがあったのですが、残念ながら現在は運営を停止しています。このサイトは、リムスキー=コルサコフ著『管弦楽法原理』の内容をガーリタン・パーソナル・オーケストラ(GPO)というソフトウェア音源を使って演奏・解説したものでした。
しかし有難いことに現在、『管弦楽法原理』は日本語訳が公開されており、下記のサイトで全文を読むことが出来ます。
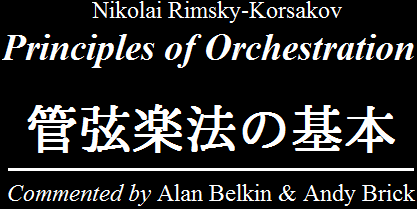
Amazonで書籍版も入手可能です。なお第2巻『譜例集』は訳出されていませんが、上記サイトから原著の第2巻をダウンロード可能です。
コメント
ものごとの修練において必ず言及されるのが「守破離」ですが、管弦楽法においてもそれは強く該当すると言えます。歌舞伎の世界では、最初から我流で行こうとしたり曖昧な学びに甘んじて行ったりしたものは、“型破り”ではなく“形無し”である──そんな風に言われています。
一見すると遠回りでも、まずはオーソドックスな書法を用いて作品をつくってみる経験が、その先のステップアップの土台として大きく生きてくるはずであり、上記ふたつのサイトはその助けになると思います。
オーケストレーションの一つの到達点として常に名前の挙がるラヴェルですが、その管弦楽法をいきなりモデルとして取り入れようとしても、「それはあの独特の和声感とフレージングという独自の作曲スタイルと不可分なものなのだ」という事実を突き付けられることになるでしょう。
管弦楽法は結局のところ、個々人それぞれの作曲スタイルと密接に関わってくるものなので、ある段階以上の習熟レベルにおいては、自分の音楽を練り上げ表現する上で不可分な要素として磨いていく、そんな意識が大切になってくると思います。
オーケストレーションの対象となるのは最終的には自らの「これから表現しようとしている内的音楽」である、とも言えるかもしれません。
ともあれ、ここでご紹介したサイトを通じて一歩を踏み出した後は、スコア(打ち込み)と実際の演奏・音とをつなぐイメージ力を豊かにし、鍛えていくことに尽きると思います。注意深く多くの作品を聴き、自分の手でトライ&フィードバックを繰り返していきましょう。
参考記事
オーケストレーションを学ぶのに役立つ管弦楽法の書籍について、以下の記事で解説していますので、参考にしてください。