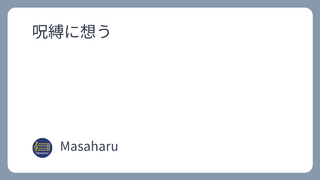 エッセイ
エッセイ 呪縛に想う
(初出1999年10月22日)過去、私が作曲をしていて思い煩う事が多かった呪縛と言えば、「表現したいことがあるのか」というものでしょう。これはどういうことかと言いますと、まず頭の中に明確なイメ...
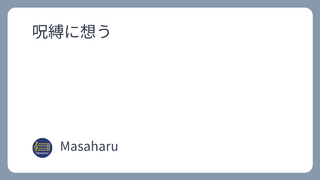 エッセイ
エッセイ 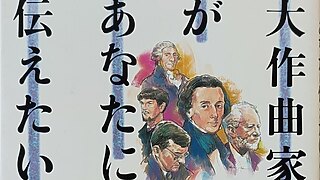 エッセイ
エッセイ  エッセイ
エッセイ 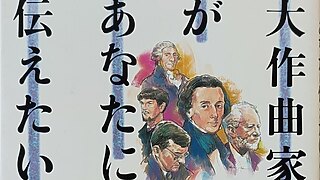 エッセイ
エッセイ 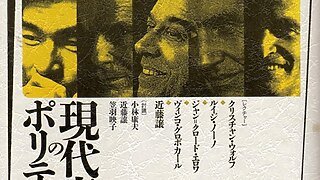 エッセイ
エッセイ 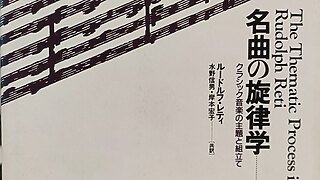 エッセイ
エッセイ  エッセイ
エッセイ 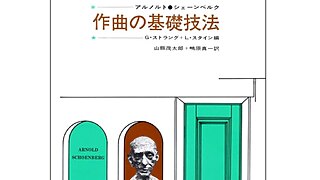 エッセイ
エッセイ 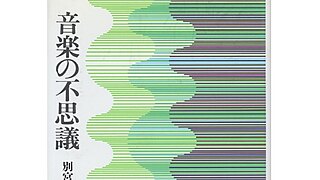 エッセイ
エッセイ 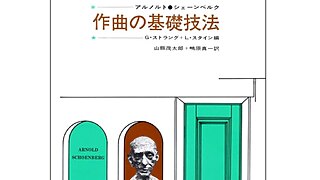 エッセイ
エッセイ