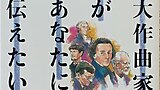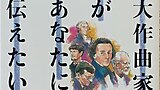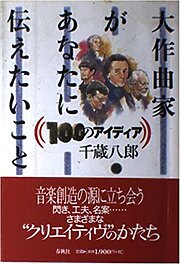(初出2002年4月8日)
物事には何でも始まりがあります。では、作曲行為にとって「始まり」とはどういったものなのでしょうか。最初の音が選択、決定されて、曲が姿を見せ始めるまでには、どういったことが起こっているのでしょう。作曲家のルトスワフスキは、インタビュアーの「何から書きはじめるのか。基本的な楽想からか、楽想の萌芽からか、あるいは作品の総体的な構想からか」との問いに次の様に答えています。
私は、いつも若い仲間たちに言うんですよ。作品の総体的な構成からだけ取りかかるのは不可能だとね。(中略)しかし手がかりになる考えを持たないで、仕事をはじめるわけにはいきません。あなたが、もし重要な音のグループを持ったとすれば、それを私は主題とは考えていませんが、その音はどんな特別な意味を持たないにしても、作曲家にとってはなにかを意味しているかもしれません。そのときに、私達は仕事をスタートさせることができるのです。 (p188)
ルトスワフスキは作曲を始めるに際して、これから完成させようという音楽全体を、つまり総体的な構成を決めることは不可能だと言っています。つくり出す時点で、作曲家の内にその音楽が明確にある訳ではないということです。何らかの「音のグループ」のインスピレーションが沸いた時、そしてそこに作曲家が意味を見出した時に作曲がはじまるのだと言うのです。ちなみに、その「音のグループ」と呼ぶものは、主題と呼べる程に明確なものではないそうです。
何の変哲も無く見える(聞こえる)音のグループ、第三者にとっては単なる音の羅列でしかないような、そんな音に「何か」を感じた時、作曲家にはその先の音楽が聞こえて来るということでしょう。同じく作曲家のストラヴィンスキーは、その意味する「何か」を「食欲」という言葉で語っています。
すべての創作行為というものには、ある種の食欲というものが前提にあります。この食欲は、これから発見しようとしていることを、前もって味わうことによって引き起こされるものです。創作行為におけるこの前もって味わうというのは、まだ当の本人には知られていない作品への直観的な把握ということを伴います。(中略)この食欲は、私の注意をひいた音楽的要素を秩序立てようと考えるだけで、私のなかに起こってくるもので、インスピレーションのような偶然的なものではまったくなく……(後略)。 (p142)
つまり、まず何らかの音楽的要素、例えば音のグループがひらめいたり、憑依的に選択されたりした時に、それに対して「なにか意味があるように感じる」とか、「おいしそう(可能性を確かに感じる)」と思ったならば、それが作曲のスタート地点なのだということです。素朴な言い方をすれば、「これは面白そうだ」という予感を作曲家が感じ、その予感を信じてつくり出すのだということです。
その先は、作曲家個々人のテクニックや感性や様々な音楽性が関わっていく「作曲行為の混沌」と言えるような世界に入っていくことになるのでしょう。ストラヴィンスキーも「食欲はまだ予感にすぎないもので、実際の作品に仕上げられるには確かなるテクニックが必要」と語っています。
例えるならば、正体の分からない化学薬品を何かの拍子に手に入れたとき、「何となく面白そうだ」と感じ、それを自らの化学知識やテクニックを用いて様々な実験を行うようなものかもしれません。そして、その実験の結果のレポート、つまり出来あがった曲を人々が楽しむことで、作者が味わった楽しさや驚きを追体験できたり、レポートの仕上がり具合に感嘆の声を上げたりするのだ、と捉えられるのかもしれません。
「作曲家の頭には完成された音楽が現れ、ただそれを記すのみだ」という見解が一方にはあり、それが真実である側面も当然存在すると思います。しかしその別の側面には、ここまで示してきた様な「作曲家も、知らない音楽の姿を期待しつつ創っていく。むしろ全てを想定することは不可能だ」という作曲行為があると言えるでしょう。
関連記事