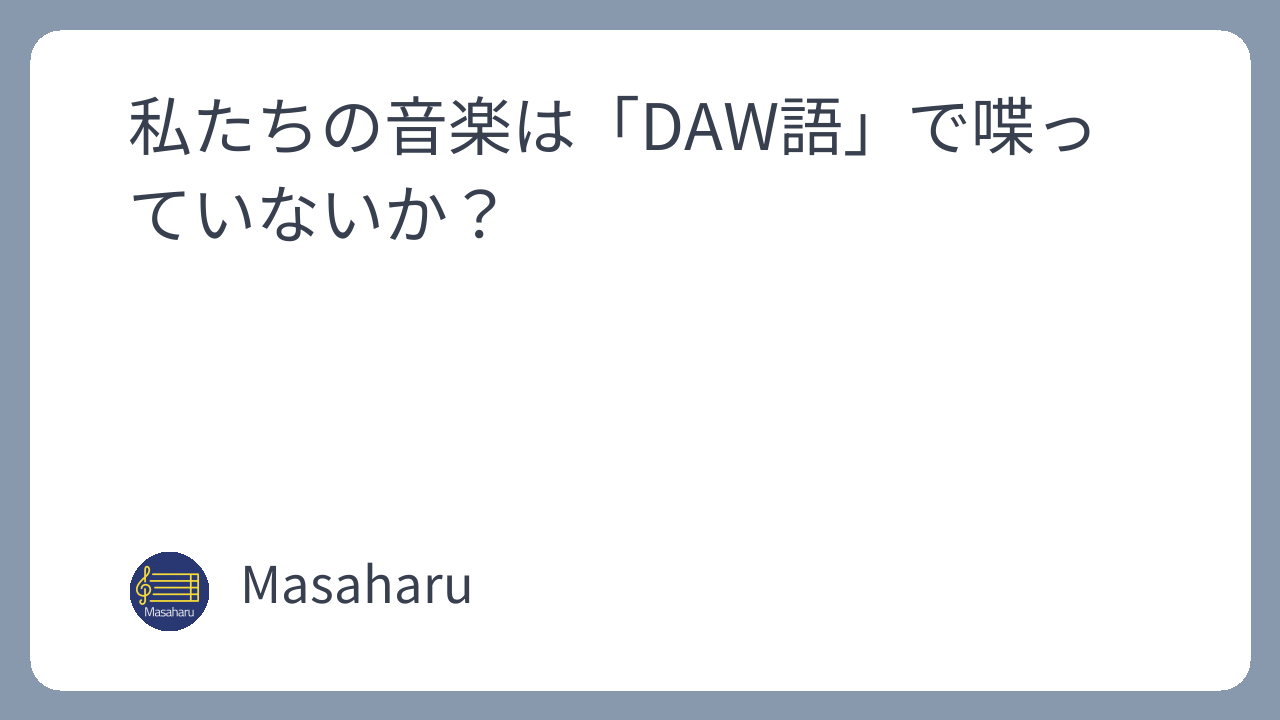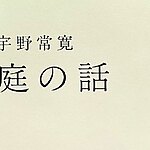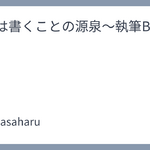DAWという制作環境の盲点
DAW(Digital Audio Workstation)は、気が付けば私たちの音楽制作に欠かせない存在となりました。多くの創り手にとって、それは広大な自由を約束し、無限の可能性を秘めた魔法の箱のように映るかもしれません。しかし私はこの一般的な認識に、どこか見過ごされている「盲点」があるように感じています。
DAWという環境は、絶対的な自由を与えてくれるわけではありません。むしろ、シーケンサーの黎明期から今日に至るその進化の道のりを辿れば、それは常に不自由な状況と向き合い、それを日進月歩で改善しようと試みる、まさに「不自由からの脱却プロセス」の具現化であったと捉えることができるでしょう。
そして、この飽くなき改善の過程で、DAWは独自の傾向を持つ「巧妙な制約」をその身に纏い、ある意味で非音楽的ともいえる特質を孕んだ制作空間へと進化・変貌を遂げたと考えられます。
もしそうであるならば、このDAWという制作空間には音楽とはまた別のコミュニケーション言語が存在しており、言うなればそれは「DAW語」と呼べるようなものではないかと思います。
ここでいう「DAW語」とは、DAWが持つ独自の編集操作体系を「ことば」や「文法」に例えたものです。これが知らず知らずのうちに私たちの音楽的思考を方向付ける「ことばの訛り(なまり)」のようなものとして働く結果、私たちの音楽制作に無意識の内に影響を与えているのではないかと考えられます。
さて、私たちは本当にDAWを「使いこなしている」と言えるのでしょうか。それとも、いつの間にかDAWに「使われている」状態に陥ってはいないでしょうか。
この記事では、DAWというメディウム(=思考や知覚に影響を与える「媒質」)が、まるで抗いがたい重力のように私たちに強いる無意識の制約に気づくことや、その上で、それを逆手にとって「遊び戯れる」ことは、私たち制作者に果たして可能なのだろうか──という問いを考えてみます。
「DAW語」の文法と訛り~見えない制約の具体像
DAWが持つ「DAW語」の文法は、私たちの音楽的思考の奥底にまで深く浸透しているように見えます。例えば、DAWを開けばまず目にするデフォルト設定の4/4拍子、テンポ120、そしてグリッド分割。これらは、まるで「このリズムで、この拍子で音楽を紡ぎなさい」と、DAWが私たちに語りかけているかのようです。
正確無比なテンポとグリッドという背景は、生身の奏者によって自在に伸縮する、あの有機的な音楽的時間の喪失を伴います。初期のシーケンサーが厳格なタイミングを強い、その厳格さを背景としたQuantize機能が生まれた結果、私たちは意識的に「揺らぎ」を導入しない限り、音楽を均質化された時間の中に閉じ込めてしまうことになります。
また、カット&ペーストなどの編集機能がもたらす「反復・繰り返しへの強い誘因力」も、DAW語の顕著な特徴と言えるでしょう。
同じフレーズのコピペ(反復利用)、あるいはループ素材の多用は、特定の音楽ジャンル、例えばミニマルやテクノ、ヒップホップなどの様式を強化する一方で、「在り得たかもしれない他の多くの音楽」の芽を摘んでしまってはいないでしょうか。これは、DAWが提供する「自由」の裏側に隠された、実に巧妙な制約であると感じられます。
ピアノロールや各種MIDIエディタ、波形エディタ、トラックウィンドウといった視覚的なインターフェースも、音を「視覚的」「数学的」に配置する思考様式を強化し、時に聴覚的な直感を鈍らせてしまう側面も持ち合わせているように思えます。
こうした「見えない巧妙な制約」の具体例は数多く挙げられるでしょう。
更には、DAWやプラグインに組み込まれた「AI機能」を、その利便性に誘引される形で無自覚・無意図のまま用いることもまた、新たなDAW語として同様の「制約」になり得る可能性があるでしょう。
私たちの音楽制作において、これらのDAW語の文法や訛りが、知らず知らずのうちに音楽を特定の方向へと導いてはいないでしょうか。一度、立ち止まって考えてみる価値があるかもしれません。
「透明なメディウム」の錯覚と「内なる声」の自己検閲
DAWの進化は、私たちに「自由」を与えてくれたという錯覚を抱かせます。DAWは制作者と音楽を媒介するものであり、制作の自由をもたらす自明の存在として受け入れられていますが、「DAWは透明なメディウム(媒質)である」というその錯覚こそが、最も巧妙な罠なのかもしれません。
DAWの操作に慣れれば慣れるほど、私たちはDAW語から遠く離れた「内なる声」――直感的で、グリッドや反復の誘惑には収まらない、もっと自由なアイデア――を、無意識のうちに自己検閲してしまうことがあります。
それは例えば、「こんな面倒なことはDAWではやりにくい」「このアイデアは、DAWのリソースを割いてまで追求する価値に乏しい」と、まるでDAWが発するDAW語が絶対的な基準であるかのように自身のアイデアを却下してしまう、一種の自己欺瞞に陥る心理的な罠として表れます。
そして、DAWやプラグインの「AI機能」の利便性に誘引されるがままに用いることもまた、同様の心理的な罠になり得るものと言えるでしょう。
AIによる編集や出力に対して「そう、これがやりたかったことだ」と後知恵バイアスのように無思慮・無自覚に受け入れることは、自由なアイデアの芽吹きを自ら妨げることに繋がりかねません。これは今後、生成AIの発展によってより一層大きく、捉えづらい罠となる可能性があるでしょう。
DAWが「透明なメディウム」であると錯覚することで、こうした内なる声の抑圧は往々にして見過ごされがちになります。
デジタル・テクノロジーによる最高の制作環境を整えることが豊かな音楽制作へ通じる道だと信じ、さらにはそれ自体が目的となり、その結果DAWというメディウムが発するDAW語に無意識に従ってしまうことで、私たちは自身の内なる声を聞き取れなくなるという、なんとも皮肉なジレンマに陥っているのかもしれません。
私たちの心の中には、DAWの便利さを優先するあまり、いつの間にか諦めてしまった音楽のアイデアが眠ってはいないでしょうか。そして、その内なる声は、本当に「リソースを割く価値に乏しい」ものだったのでしょうか。
「DAW語」からの解放、あるいは「訛り」の活用~制約を遊びに変える「戯れ」の精神
では、私たちはDAWに「使われている」のか、それともDAWを「使っている」のか?
この問いに対する答えを見つける第一歩は、DAW語の存在に気づくことに他なりません。その巧妙な制約を深く理解し、それを逆手にとることで、私たちの創造性はさらに豊かな深みへと深化するのではないでしょうか。
失われたであろう「有機的な音楽的時間」や「在り得たかもしれない音楽」を回復させるために、例えばDAWの「グリッドからの逸脱」や「意図的な不完全さの導入」などを試みることは、予想外の意義深さをもたらす行為になる可能性があります。
また、繰り返し機能を始めとした「DAWの編集機能」の誘惑を意識的に捉え、時にはそれを乗り越えたり、いなしたりして、偶発性や非線形性を追求することも、新たな表現の地平を拓くことにつながるでしょう。
「内なる声」の自己検閲という罠から脱するためには、DAWの言語としての特性を深く自覚し、その訛りや文法を意識的に破る勇気が必要となるかもしれません。それは、DAWとの対話において、作り手が「使われる側」から「使う側」へと主導権を取り戻す「戯れ(遊戯)」の精神であり、「音楽的アイデアの予感・予兆」を再び捉える行為となり得ると思うのです。
DAWという完璧に整備された制作環境の中に、偶発性や予測不能な要素を許容する「受容性」を意識的に育むこと。そして、DAWという制作環境を「絶対的な中心である」として思考停止せず、時には環境外部の素材や体験を制作プロセスに取り入れることで、それが新たな視点やインスピレーションを得ることにつながる可能性があります。
こうしたことの重要性、言うなれば複数の制作視座から生じる「共振」が、私たち独自の訛りを生み出す鍵となるのではないでしょうか。
DAWという目に見えない媒質=重力の存在に気づき、それを調整したり逆手に取ったりすることで、私たちの音楽は今までよりも自由に「飛行」できるのだと思います。
DAWとの新たな関係性へ
DAW語の存在を自覚し、その特性を深く理解すること。それが、私たちを豊かな創造へと誘う確かな鍵となるでしょう。DAWを単なる道具としてではなく、その言語としての特性を意識的に捉え、対話することで、より深い個性的な音楽表現の扉が開かれるだろうと思います。
そもそも、道具とは単なる中立的な媒介物ではありません。それを生み出した人間の思想や、その操作性が規定する思考様式は、使う側の表現そのものに深く影響を及ぼします。
これは「道具が持つ思想性」として知られる概念であり、ハイデガーが「技術の本質」において論じたように、技術は単なる手段を超え、世界を特定の様式で「現前させる」力を持つのだという視点です。自らの音楽制作を俯瞰する上で、この「道具の思想性」を理解することは、ひとつの重要な要素となるでしょう。
DAWというメディウムの重力を認識し、その上で、使いこなすことの真の意味を問い直すこと。この探求によって私たちの音楽制作の可能性は、さらに切り拓かれていくのではないでしょうか。