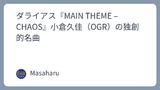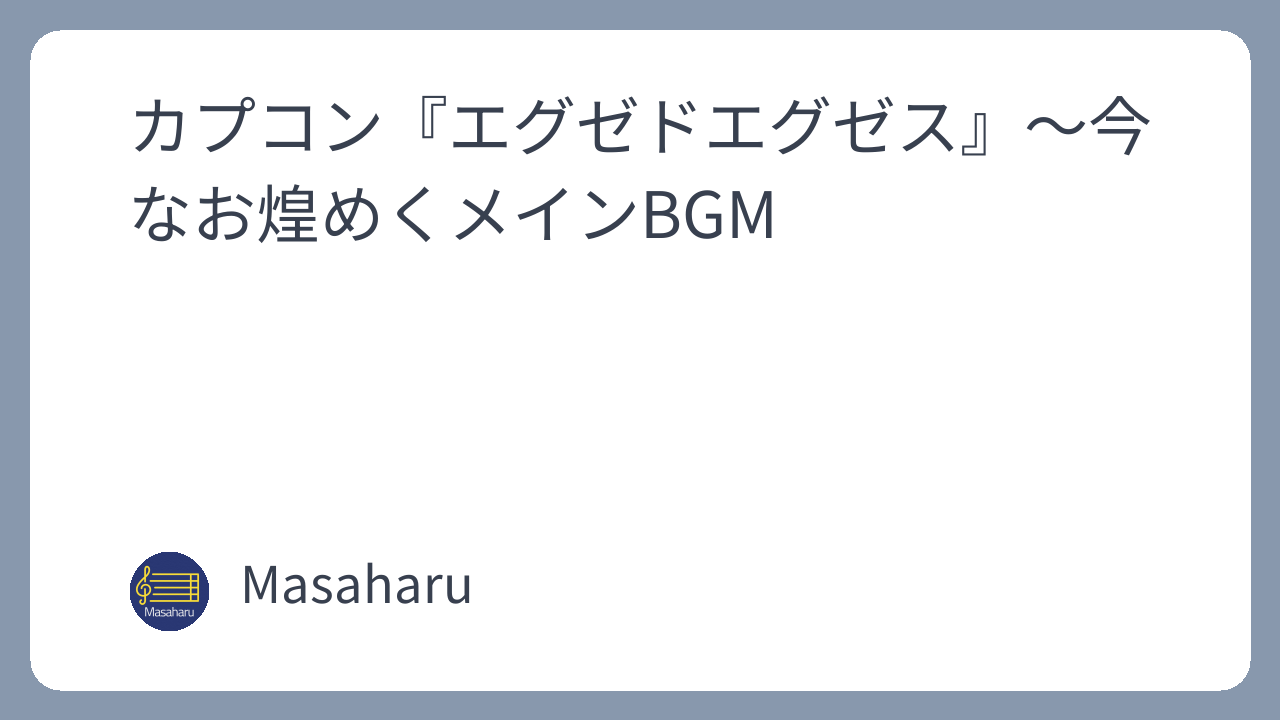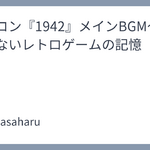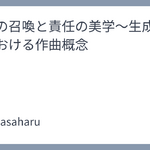前回ご紹介した『1942』に続き、当時大好きだったゲーム音楽について、その特徴と魅力を詳しくお話していこうと思います。
この記事では、1985年2月に登場した、カプコンの『エグゼドエグゼス』のメインBGMを取り上げます。
独自の特徴と世界観を持つ『エグゼドエグゼス』
敵キャラのデザインは昆虫がモチーフとなっており、まるでハチの巣を思わせる「六角形で埋め尽くされた大地」というフィールドデザインと共に、その乾いた不気味さを抱かせる「独特の異世界感」はとても個性的なものでした。
そして各ステージのクライマックスで登場する巨大な浮遊要塞は、その弾幕の激しさと、緊張感や威圧感をもたらすBGMとが合わさって、当時のプレイヤーに強烈なインパクトを与えました。
本作は、当時としてはまだ珍しい協力型の2人同時プレイが可能で、従来のシューティングゲームにはなかった「共闘の楽しさ」と「攻略法の深み」が生まれたことも、特筆すべき点でしょう。
「佐吉」というアイテムを消費して画面上の敵弾を全て消去する、「クラッシュ」という防御システムも大きな特徴です。これは緊急時の弾幕回避を可能にするシステムであり、後のシューティングゲームにおける「ボム(爆弾)」の原型の一つと見なせると思います。
「Pow」というアイテムを取ると、画面上の敵がボーナスアイテムの「フルーツ」に一変し、得点稼ぎのチャンスとなるのも特徴的で、リスクとリターンのバランスを追求する「ハイスコア文化」を促進したと言えるでしょう。
魅惑的に煌めくメインBGM
さて、このゲームを初めて目にした私は、スピード感のある多重スクロールの背景や、メタリックな質感と昆虫をモチーフにした生命感といった、その独特の世界観に強く心惹かれました。
そして何よりも、そこで奏でられるメインBGMの魅惑的な美しさに、一聴して虜になってしまったのです。
透明感のある音色によって半音程を伴いながら非機能的に下降していく、その印象的なアルペジオパターンは、私の好みにズバッと刺さり、忘れられないものとなりました。
まずは下記の動画で実際のBGMをお聴きください。
4つの和音がそれぞれ2小節ずつ繰り返されるシンプルな構成のなかに、浮遊感を感じさせるハーモニーが構築されており、そこには不思議な儚さや、繊細な抒情性が感じられます。
コード進行は以下の通りで、一般的な和声機能をはぐらかすような連結になっており、主和音が見えづらいコード進行になっています。
I△7→ VII7→ ♭VII△7→ ♭VI△7
IV△7→ III7→ ♭III△7→ ♭II△7
全体が分散和音のアルペジオ(ルート+3度+7度)で構成されているため、スケールを厳密に特定することが出来ない上、機能和声的なケーデンスも見られないため、調性を一意に特定できません。
これらの響きに耳をそばだててみると、そこにはフランス近代音楽(印象主義音楽)や、そこから派生したジャズハーモニーとの類似性を感じ取ることが可能だと思います。
一般的にシューティングゲームのBGMにおいては、敵弾を避けながら敵を破壊するというゲームの性質上、プレイヤーのアドレナリンを引き出すような、勇壮さや攻撃性の昂ぶりを喚起する音楽が用いられがちです。
しかしエグゼドエグゼスでは、それとはまったく異なる、繊細でエレガントさすら感じさせるアルペジオが奏でられており、そのシューティングゲームらしからぬ美麗な響きをもったBGMは、従来とは一線を画すものとして特筆に値します。
そしてこのBGMが、作品の世界観を音響面から際立たせる役割をしっかりと果たしているのは、見事という他ありません。
冒頭に述べた、本作の「乾いた不気味さを抱かせる異世界感」は、シューティングゲーム的な音楽とは異なる美意識を背景にして生まれた、このBGMがあってこそ成り立つものだったと言えるでしょう。
『ゼビウス』という先達の姿
当時、このメインBGMを聴いたときに思ったのは、「これは『ゼビウス』のBGMへのオマージュなのではないか?」というものでした。
ナムコの伝説的名作であるゼビウスは、本作にさかのぼること2年前、1983年の1月末に登場しました。近未来の南米を舞台に侵略者ガンプと戦う、謎に満ちた世界観が魅力の傑作縦スクロールシューティングゲームです。
ゼビウスのBGMの「クリシェライン(半音下降)を内包する4つの和音」によるアルペジオパターンが無限ループする形式と、そこから受ける表面的な印象は、エグゼドエグゼスと共通したものを感じさせます。
しかし、エグゼドエグゼスで鳴り響くハーモニーが聴き手に抱かせるイメージは、ゼビウスとは全く異質なものです。
言うなれば、ゼビウスのBGMのイメージが「無機的・神秘的」とするならば、エグゼドエグゼスのメインBGMは「透明的・夢幻的」とでも言い表せるかもしれません。
さらには作曲者である河本圭代氏は、ゼビウスの「SF・戦闘」からエグゼドエグゼスの「幻想・異世界」へという、新しいシューティングゲームBGMの方向性を提示しようとしていたのかもしれない──そんな想像も浮かんできます。
もしそうであるならば、これは単なるオマージュを超えた、ゲーム音楽史における「様式的な応答(レスポンス)」であり、ミニマルBGMの系譜を意図的に継承し発展させようとする試みであったと言えるかもしれません。
ミニマル系BGMのマイルストーンとしての『エグゼドエグゼス』
目立ったメロディーが無く、音楽的展開も無いか控えめで、シンプルなフレーズの反復によって構成される「ミニマルなBGM」は、この年代のゲームには散見されるものでした。
ゼビウス登場からエグゼドエグゼスまでの1983~1985年頃に限ってみても、タイトーの『ちゃっくんぽっぷ』、アイレムの『ジッピーレース』『スパルタンX』『ロットロット』、ナムコの『ディグダグ2』『モトス』など、ミニマルでコンパクトな印象を与えるBGMは色々とあります。
これらの作品とエグゼドエグゼスとを比較することで、本作の特徴があぶり出されてくると思いますので、いくつかのゲームを取り上げ、各メインBGMの特徴を見ていきましょう。
『ちゃっくんぽっぷ』タイトー(1984年)
『ちゃっくんぽっぷ』のメインBGMは、極めてシンプルな音型で主和音と属和音が繰り返されて出来ており、ファンシーなゲームの雰囲気を一層強める効果を生み出しています。
過剰や余剰を一切排して切り詰められた、その「俳句のようなBGM」は、最初期のゲーム音楽への先祖返りともいえる素朴さと完成度の高さを感じさせます。
『スパルタンX』アイレム(1984年)
『スパルタンX』のメインBGMでは、ブルース進行を土台としたコード進行のもと、ベースのリフパターンとリズム音だけが延々と反復されます。
メロディーや華やかな伴奏を一切排した、文字通りスパルタン(厳しく剛健)なスタイルとなっています。
『ディグダグ2』ナムコ(1985年)
『ディグダグ2』のメインBGMは、その音楽的な印象はまったく異なるものの、ベースパートがゼビウスと同様の構造的特徴を持っているのが興味深い点です(パターンは若干異なりますが、どちらも半音下降のクリシェラインをもっています)。
これら二つの作品は、どちらも作曲者が慶野由利子氏であることから、何らかの仕掛けや遊び的な意味が込められていたのかもしれません。
『モトス』ナムコ(1985年)
『モトス』のメインBGMでは、ベースの刻みパターンの上に緊張感のある和音とアルペジオが配され、調性感の希薄な音楽空間が生み出されています。
一聴すると、足元の危うさを感じさせるような浮遊感や不協和感を抱かせますが、ベースラインは基本的に動かず一定で、ベースが変化する際は四度(転回すると五度)音程という強固な関係を維持しており、全体として絶妙なバランスを保っています。
こうした音楽的要素が、「落とすか落とされるか」というゲーム内容にマッチしているという点で、レトロゲームのBGMの秀逸なお手本とも言えるでしょう。
『エグゼドエグゼス』メインBGMの成し得たもの
取り上げてきたレトロゲーム作品たちは、どれも当時の開発上の制約のなかで最善を尽くし、アイデアを注ぎ込んで生み出されたものであり、ミニマル系のBGMが意図的かつ効果的に用いられていることが分かります。
そうしたことを踏まえた上で見てみても、やはりゼビウスのBGMの独自性と先進性、そして何よりも、エグゼドエグゼスの美麗で個性的なBGMの洗練性が、改めて浮かび上がってくるのではないでしょうか。
既述のようにエグゼドエグゼスでは、それまでのシューティングゲームとは異なる美意識を背景に制作されたBGMによって、「乾いた不気味さを抱かせる独特の異世界感」を音響面から生み出し、支え、際立たせています。
そしてゼビウスとの関連でいうならば、それは単なるオマージュを超えた「様式的な応答(レスポンス)」であり、ミニマルBGMの系譜を意図的に継承し発展させようとする試みであった──という可能性の存在も、ひとつの興味深い注目点だと言えるでしょう。
このような観点から、エグゼドエグゼスのメインBGMは、この年代の「ミニマルなBGM」における、ひとつの洗練された到達点であり、マイルストーン(節目となる重要な出来事)だったといっても過言ではないと思います。
『エグゼドエグゼス』の思い出
私が初めてエグゼドエグゼスをプレイしたのは、地元のボーリング場にあるゲームコーナーでした。
騒がしい場内でも、その特徴的なメインBGMははっきりと耳に届いていたのですが、他のBGMは上手く聞き取れなかった覚えがあります。
特に、ボスを倒した後のファンファーレが、なぜか低音ばかりが大きく感じられるなか、リズムが強調されて鳴り響いていました。そのため当時の私は、「なんだか得体のしれない凄みと威圧感のあるハーモニーは、まさにボス破壊後にぴったりだ…!」と、おののいていました。
その後、あらためて別の場所で聴いたとき、「あれ?こんなファンファーレだったっけ…」と戸惑うことになったのですが、今でも最初に聴いた時のイメージは「自分だけの心の名曲」として、おぼろげながらも今も在り続けています。
関連記事