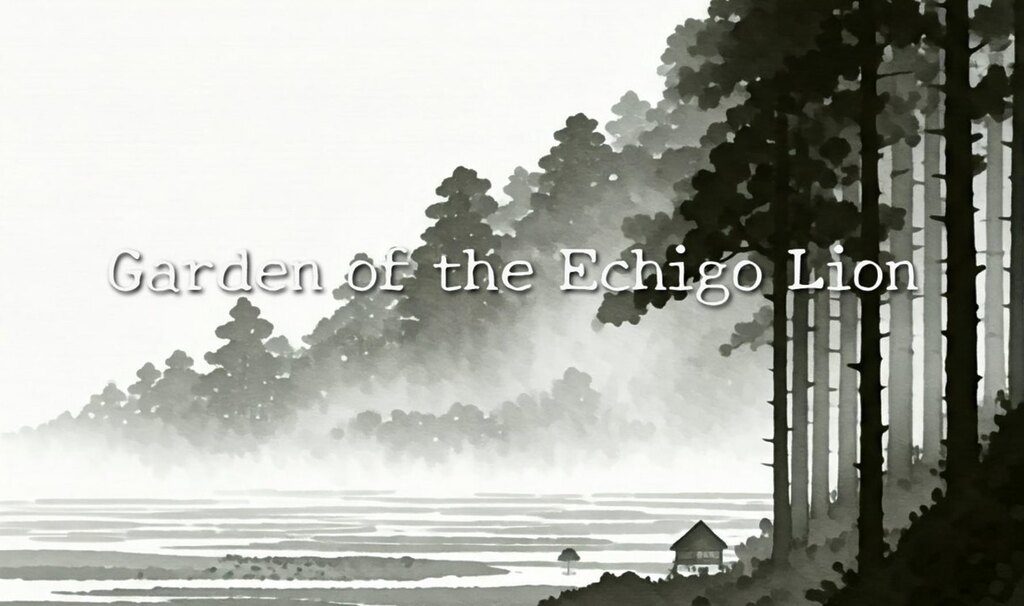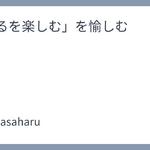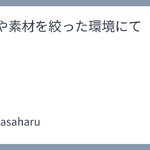全編にわたって即興的な演奏を続ける三味線パートと、停滞と変化を不規則に繰り返すリズムパート。それらが折り重なるように奏でられるこの『Garden of the Echigo Lion』(原題『越後獅子の庭』)は、日本的でありながらもどこか無国籍風な印象を感じさせる。
作者は次のように語る。
『この曲は、三味線の変奏とリズムパートとの絡み合いを通じて、自分流の時間構成を模索してみた曲です。いわゆる「イントロ~Aメロ~」や「3部形式」といった既存の形式枠に囚われないよう、自分の時間感覚と向かい合うことを念頭に置きました』
自らの時間感覚と向き合うアプローチとして選択されたものの一つが「明瞭なメロディーを出現させない」というものだったことが、この曲を一聴して分かる点であろう。
三味線や笛といった楽器は、それぞれメロディーを奏でそうな期待を抱かせるものの、曲中の一部の三味線パートを除いてただひたすらに即興的な演奏が続けられていく。また打楽器類とベースによるリズムパートは多くの場面で特定のパターンを繰り返しており、意図的に変化に乏しい状況を生み出している。
さらには曲が始まってしばらくの時間は和声的な変化も見られず、ひとつの和音の響きの中に留まったまま時間が流れていく。そしてそこには明瞭なメロディーは無く、リズムパターンの変化も無い。
このようなアプローチの結果、聴き手は特定の旋律やリズムパターンではなく「全体のムードの変化や移ろい」に着目していくように誘導されていくこととなる。
開始後40秒で最初の変化が訪れる。それまでのリズムパートが鳴り止み、代わりにエフェクティブな効果音を主体とした浮遊感を感じさせるリズムがその場を支配する。そこで奏で続けられる三味線は、まるで取り残されてしまったかのような足元のおぼつかなさを感じさせるが、しばらくすると三味線を助けに来たかのように唄のパートが参入してくる。
基本となるリズムパターンと、それと対になるエフェクティブな効果音主体のリズムパート。これらが時に場面を切り替えるように、また時に重ね合わさってグラデーションを形成することによって、音楽的な時間の背景を構成していく。そしてその背景を背負う格好で即興的に鳴り響く三味線の音。
さて、曲も中盤を過ぎた4分40秒からは、スッと空気が変わるように三味線と唄がそろりと旋律を奏で始める。
両者は対位法的というよりは「つかず離れず」といった風に寄り添いながら旋律を響かせていくが、それもつかの間、我に返ったかのように再び即興的でリズミックな流れの中に帰っていき、曲の終焉へと向かっていく。
そして曲の最後では全体が急停止し、ふわりとしたシンセ音で空間が満たされ、これまでとは全く異なる雰囲気を感じさせる和音の響きが垣間見えた瞬間、唐突に断ち切られるかのようにして曲は終わりを迎える。
一見捉えどころがないようにも感じられる本曲は、全体のムードの変化や移ろいに注目することによって独特の音楽的な時間感覚を体感することが出来るものだといえよう。
この点について、作者はいみじくも次のように述べている。
『作曲中に想定していたのは、月を見上げながら歩いたときに感じる「月が自分に付いてくる感覚」のような停止感(滞留感)と「目を下ろして周りを見渡したときの景色の変化」というギャップ(断絶感)についてでした』
この意図が作品に反映されているのならば、何者かに付き添われながら遠くまで来てしまったことにふと気づいたときのような驚きをこの曲からも感じると共に、ある種の不安や怯えのような戸惑いも想起させられるかもしれない。
タイトルにある「Echigo Lion」とは、日本の新潟の郷土芸能である少年獅子舞のことを指している。江戸時代、飢饉などで身寄りを亡くした子供たちが獅子舞の大道芸を仕込まれることで生きる糧を得ていたのである。
そうした言葉がタイトルに付されていることを知ると、月を見上げる者の姿や「気が付けば遠い所へ来ていた」という事実が示す意味が、より深いものとして感得されるのではないだろうか。
このように、音楽が直接伝えてくるものに対してタイトルの意味を補助線として引くことで、この曲の独特な時間体験をより一層深く味わうことが出来るように思われる。