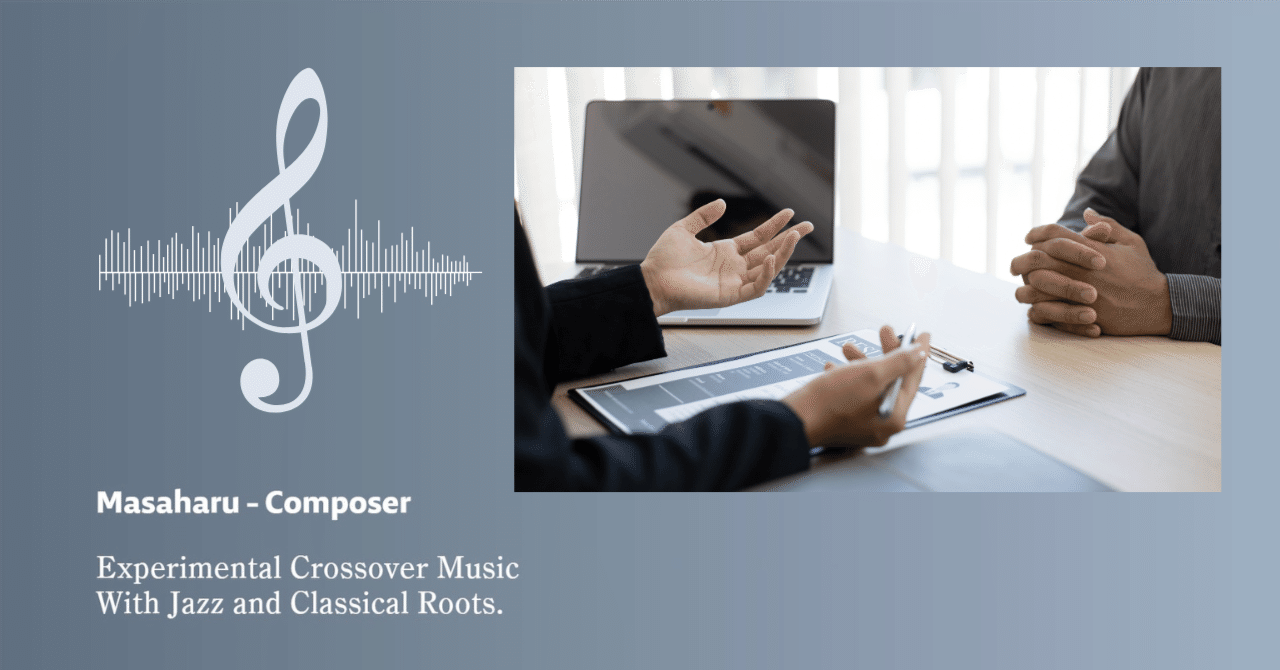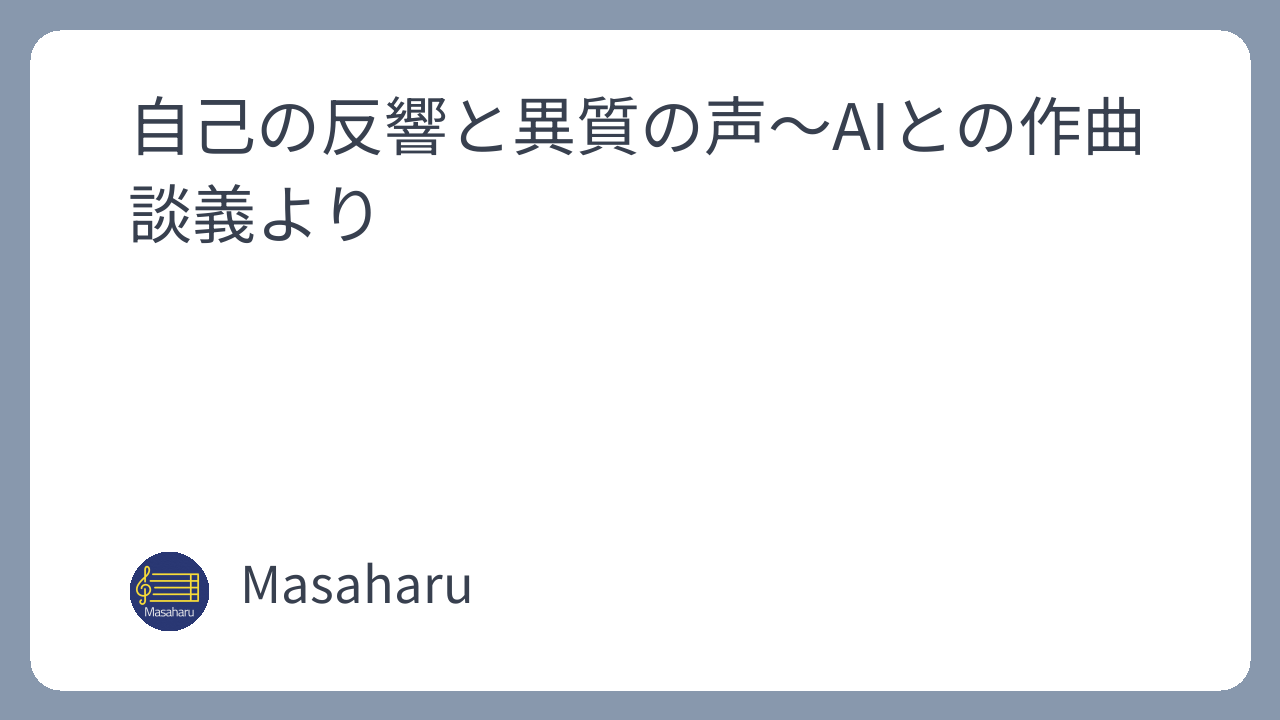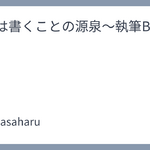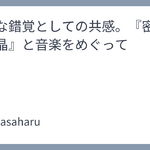AIによる作曲が急速に普及する中で、私たち作曲家は、その新しいツールとどのように向き合うべきか、日々自問しています。今回は、AI作曲が「作曲する者としての私」にもたらした思索プロセスを紐解きながら、考察を進めていきたいと思います。
この思索においては、AI(Gemini)を議論の相手に据えて考察を進めていきました。AI作曲のことをAIと語り合うという、人間側としては不思議な感覚を覚える環境でのやり取りになりました。
AI作曲は「作曲」なのか?~素材と感性の対話
SunoなどのAI作曲ツールを初めて使ったときに感じたのは、「これは作曲というより、音楽をディグる(探索する・探し出す)行為に近い」というものでした。
自分の手で音符を一つひとつ紡ぎ出すというよりは、AIが提示する無数の作品の中から、心惹かれるものを探し出す感覚。そこには、音楽市場の膨大な作品の中からお気に入りの一枚を見つけるレコード・ディグのような、発見の楽しさがあるように思えました。
この体験は、私の中で「作曲」という行為の定義を問い直すきっかけになりました。そもそも作曲とは、ゼロからすべてを創造することだけを指すのでしょうか。
その問いへの答えを考える中で、私自身は作曲行為の大きな側面として「構築すること」を重要視しているという点、つまり「素材と音楽的な対話をすることによって構成・構築(コンポジション)しているのだ」という事実を再認識しました。
AIが生成する「完成品」の音楽をはじめ、断片的なフレーズやリズム、和声・コード進行などに対し、それらを一律の「素材」と捉え、それをどのように配置し、どんな文脈を与えるかを考えること──それが私の自然な作曲行為のひとつということになります。
例えば、AIによる楽曲の特定パートに対して、ポリモーダリティーを感じさせるようなハーモニーとメロディーをレイヤリングし、新たな和声空間を構築することが挙げられます。それによって、もとの「AI作曲による完成品」がもっていた音楽的文脈(特定のジャンルや時代性を志向するメッセージやストーリー性)が異化される結果を生み出すことでしょう。
このようなプロセスは、素材と感性との対話だと言えます。その対話を通じて、新たな音楽的な意味や物語が生まれていくわけです。
その意味で、AIは単なる「技術」ではなく、私自身の創作活動における新たな「対話相手」と言えるかもしれません。
このように「感性との対話相手としてのAI」という姿を見てみると、それは何も特別な存在ではなく、過去の音楽史上にも見られたものだと気付きます。
古くはモーツァルトのサイコロ作曲法、20世紀においてはジョン・ケージのチャンス・オペレーション(偶然性の音楽)、ヒップホップのサンプリング文化など──いずれも外部から訪れる「予測不可能な要素」との邂逅です。作曲AIはその現代的変種であり、偶然性を統計的に再構築する存在だと言えます。
作曲する者の外部から訪れる「他者としての素材」との「感性の対話」という構図において、AI作曲の登場自体は、音楽史的には特別な異常値や特異点ではなく、こうした現代的なバリエーションに過ぎないという側面も見えてくるのではないでしょうか。
音楽の実存をどこに求めるか
さて、作曲における音楽的な対話相手としてのAIの存在は、私自身の音楽観、つまり音楽の実存を「客観的条件」ではなく「主観的条件」に求めるスタンスと関連しています。言い換えると、「音楽は聴き手の感性の内に存在している」という立場を取っているということです。
作曲AIが提示する音楽素材は、膨大なデータの統計的処理の結果に過ぎないかもしれません。しかし、私がその素材の中に主観的な美を見出すことで、そこに「音楽」としての意味が立ち現れます。
ここで議論相手のAIから、「対話」を成立させるために作曲AIにはどのような資質が求められるのか、という問いが提起されました。
例えば、単に多様な素材をランダムに生成するだけでなく、私の音楽的な嗜好を学習し、より「対話」が弾むような応答を返してくれるAIを期待すべきなのか、あるいは、私とは全く異なるロジックで動く異質な存在である方が、偶発的で新鮮な創造を得るためには好ましいのか。
私は、どちらにも大きな可能性を感じると考えています。やはり重要なのは、AIが何を生み出すかではなく、私がその素材に何を見出すかという点にあります。
さらにAIは問います。
- もし作曲AIが、作者が見出した主観的な美を統計的に学習し、「作者が美しく感じるであろう音楽素材」を、より予測可能なレベルで生成するようになったとしたら?
- それはもはや対話ではなく、自分の声が壁に反響して返ってくるだけの空間に閉じ込められてしまっているのではないか?
- そのとき、ただの「自己の反響」──すなわち「自閉的で自己完結した音楽」を聴いているに過ぎないのだと、虚しさを感じることはないだろうか?
この問いに対し私は、「自己の反響」に価値を見出すかどうかもメタな意味で主観的判断として扱える、という考えを伝えました。
そのような純度の高い「自己の反響」の存在に対してある種崇高な美すら感じながら、創造のひとつの形としての「自閉的な完成形」という創作物に至ることもまた、魅力的なことではないか、という考えです。
こうした「自己の反響」が創造的であるためには、それが意識的に選び取られた閉鎖(閉塞)であることが重要となるでしょう。無意識の惰性による反復は停滞や退嬰に繋がりかねないですが、意図的な閉鎖は形式の純化となり得る可能性があると考えられるからです。
運動体としての作品(群)
そうした私の考えに対し、「自閉的な完成形と、創造的な停滞や退嬰とをどう区別するのか?」という問いがAIから提起されました。
それに対して私は「そもそもその区別が必要なのだろうか」と、問いの前提そのものに立ち返って考えてみました。
そして、個々の作品の良し悪しではなく、それらすべてを「作者の歴史」という一つの実践の流れ、つまり「運動体としての作品群」として捉える視点から、この問いに向き合うことを選びました。
作曲AIとの対話を通じて生まれた音楽作品たちが、どのような軌跡を描いてきたのかを俯瞰することで、私は自己の内面がどこに向かっているのか、その「純度(自閉)の程度」を観測することが出来るはずです。
この「運動体」としての作品群を眺めることは、自己の成長や変遷を客観的に見つめ、次の創作への方向性を定める上での、不可欠なメタな自己評価となることでしょう。
感想
以上のようなAIとの議論と思索を経ることによって、私と作曲AIとの向き合い方について、ひとつの側面の言語化が進んだ感があります。
AI作曲は、単に便利なツールとしてだけではなく、自らの創作哲学を問い直し、自己の内面を探求するための「新たな鏡」となる可能性を持っているというのが、今回の一先ずの感想です。
そしてその「鏡」はある意味、作者にとって当たり前過ぎるものでありながら、しかし明瞭には言語化されてこなかった、そんな「盲点」に向き合わせてくれるものだと思います。
最後に補足として、生成AIについては、ここでは触れなかった既存の問題(生成AIの学習元となったデータの素性と著作権のことや、生成AI否定論のことなど)が種々あるわけですが、現在の私の手には余るものと思われたので、今回のようなテーマ設定と考察に至った次第です。
※もとになったGeminiとの対話は、下記のnoteでご覧になれます。