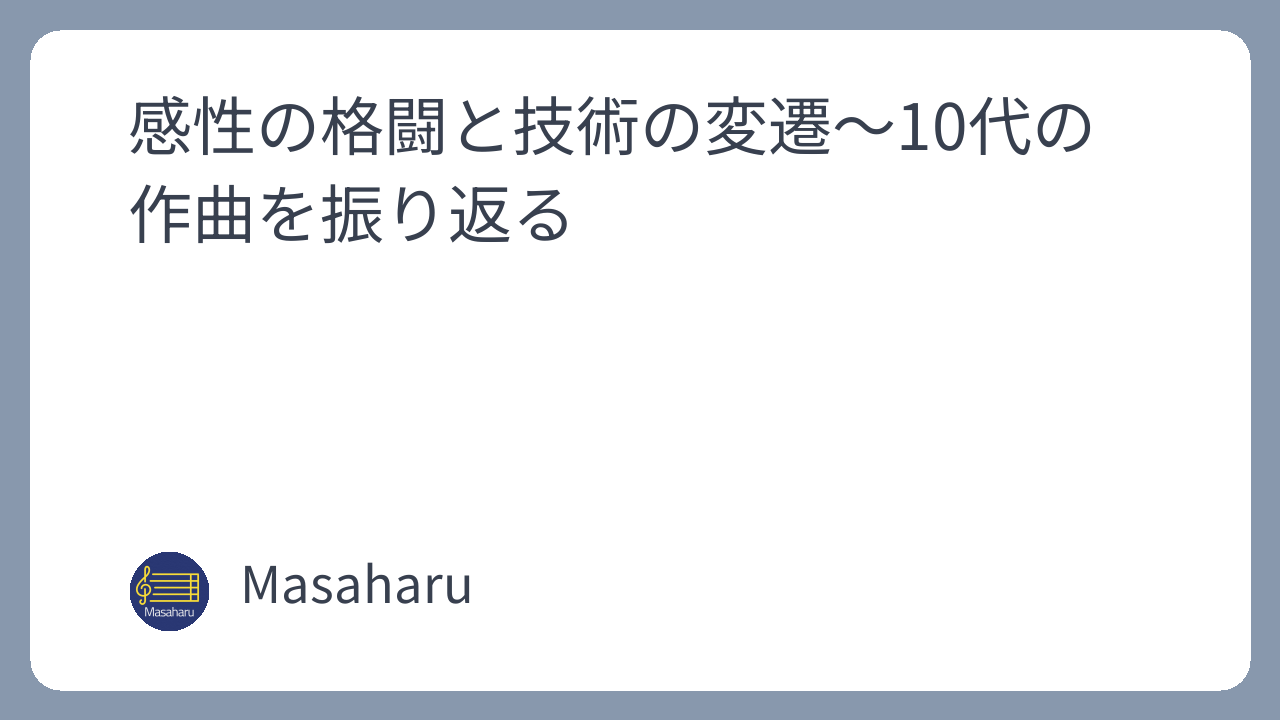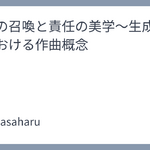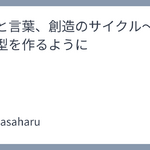この記事では、私が10代の頃に作曲した作品を聴き返しながら、当時の作曲スタイルや創作姿勢といったものを顧みていこうと思います。
個人的で懐古的な内容になるかと思いますが、当時、作曲を始めて間もない人間が、どのような音楽を、どのような背景の元で、どんな思いで作っていたのかについて書いていきますので、よろしければお付き合いください。
最初の一曲目のこと(1987年作曲)
最初に自分の音楽作品を完成させたのは1987年の冬で、14歳の中学二年のとき、NECのパソコンPC-8801FHで、MML(Music Macro Language)という音楽用のプログラミング言語を用いて作曲しました。
残念ながら音源は残っていないのですが、その曲はFM音源による「余韻の長いベル系の音色」のみで奏でられたもので、あたかも弦楽合奏のアダージョのように響く曲でした。
曲中では、静寂から響きの頂への過程が描かれ、再び静寂へ帰っていくという構成になっていました。鐘を突くようなゆったりした流れの中で、徐々に音量を上げていき、シンプルなカデンツと、上昇を感じさせる転調を繰り返しながら、少しずつ進んでいく──そんな数分間の曲でした。
子供の頃から、音楽のハーモニー(和声や転調の響き)に対して敏感に反応していたのを覚えていますが、自分で作った最初の曲にも自然とそうした「好み」が織り込まれていたのが分かります。
その後もPC-8801FHとX68000を使い、FM音源(+PCM音源)をMMLで操作して、オリジナル曲やゲーム音楽のコピー演奏を作成していました。
そして16歳のときに、念願だったMIDI楽器を入手し、本格的な音楽制作(打ち込み音楽)の世界に足を踏み入れることになります。
現在手元に残っている作品は、MIDI楽器で音楽制作を始めた1989年、16歳のとき以降のものです。
ということで、ここからは、16歳から19歳にかけて作曲した音楽の中から、特徴的なものを5曲取り上げて、当時の音源を聴きながら振り返ってみたいと思います。
なお、掲載している音源には、EQとコンプレッサー等で若干のマスタリング処理を施してあります。
『Icy Hands』(1989年作曲)
これは16歳(高校二年)のときの作品で、当時発売されて間も無かったKORG(コルグ)のM3Rを使って制作されました。シーケンサー(今でいうDAW)は、MIDI拡張ドライバーがインストールされたX68000のMML環境を使用しています。
その頃に好きだったゲーム音楽やフュージョン音楽に感化され、模倣しながら、自分なりの「好き」を形にしようとした、そんな曲のひとつです。
リズムはメタルロックから借り、ハーモニーはマイナー調をベースに「勇壮でヒロイックなゲーム音楽」をイメージしながら、拙いながらも頑張って紡ぎ出しています。
セクションごとに転調していく構成と、その転調のギャップ感をメロディーラインで吸収しようとするアプローチからは、当時の「模索の姿勢」と「己の感覚に従う素直さ」の両方が感じられて、現在の自分から見ても興味深いものがあります。
この頃は、コード理論を学び始めたばかりだったので、作曲に活かしたり分析に用いたりといったことは、まだまだ出来ていませんでした。ですがその分、自分の感覚と真剣に向き合いながら作曲することに集中できていたと言えるでしょう。
この後、音楽理論や各種技法に熟達していくに従い、初期のこうした「感性との格闘」とも呼べるせめぎ合いが、一時、音に表われなくなっていきました。
この曲はスタイリッシュでもなければ洗練されてもいない、ごつごつと無骨な手触りを感じさせますが、この時代のこの年齢だからこそ出来た作品だったと感慨深くなる、そんな思い出の一曲です(この曲のサビが気に入っていたため、後年『Behind』でも再び用いています)。
ミックスは典型的な「風呂場リバーブ」の状態になっていて、その初心者ぶりに我ながら苦笑してしまいますが、当時は、リバーブを使うと音響がリッチになるのが嬉しくて、過剰に使ってしまっていた覚えがあります。
この作品はそこまでではないのですが、この時期の曲のタイトルには可笑しなものが散見されるのも特徴的です。例えば、同時期の曲に『Kink Nail』という作品があるのですが、タイトルを直訳すると「ねじれた爪」となります。
これは、自分のイメージに忠実なタイトルをつけることへの気恥ずかしさから、敢えて意味のよく分からない言葉にしたという背景があり、当時の心境を思い起こすと微笑ましく感じられます。
あと、この後もしばらく使い続けることになる「コルグのスネアドラム」が懐かしさを掻き立てます。この時代のMIDI楽器に詳しい人ならば、誰でも「あ、コルグのあの音だ」と分かるくらい、特徴的で印象に残るスネアドラムでした(コルグのピアノも特徴的な音でした)。
ちなみに、このスネアドラムは、X68000版のゲーム『ボスコニアン』のPCMドラムにも使われていて、X68000ユーザーにもお馴染みの音だったはずです。
『Final Takeout』(1990年作曲)
これは17歳(高校三年)のときの作品で、『Icy Hands』の数か月後に、同じくKORG(コルグ)のM3Rを使って制作されました。
前曲で述べた「タイトルへの照れ」は、この曲でも同様に見られます。これはセガのゲーム音楽の『Final Take Off』という曲名をもじったものなのですが、いくら何でも『最後のお持ち帰り』はないだろうと思ってしまう、そんな若気の至りを感じさせる曲名です。
さて本曲では、ハーモニーが一気にスッキリとしたものになりましたが、これはコード理論の学習の影響で、良くも悪くも手慣れてきたことを示しています。
曲の構成もポピュラー系を土台に、フュージョン系のインストゥルメンタル音楽でよく見られた構成を踏まえながら、サビのリフレインからのフェードアウトで閉じられます。
明るい長調のイントロから、陰りのある短調のAメロへとスッと入っていき、Aメロの終わりで再び長調へ戻るかと思いきや、再び短調で進んでいく──という具合に、曲全体に渡ってメジャーとマイナーの陰影をくっきりと色づけることで、聴き手の印象を深めようとしていたことが伺えます。
同主短調からの借用和音やピカルディ終止、クリシェラインなど、自分なりに使い慣れて来た技法を織り込んで作曲されていますが、習熟のバランスがコード理論に関するものに偏っていたため、一聴すると、編曲を施される前の「コードとメロディーだけの譜面」のようにも感じられます。
これは当時の限界を示すものであり、アレンジ技術がすっぽりと抜け落ちていたと言えます。と同時に、その頃の私は、まさにその「コードの響きの移ろい」の虜になっていたのであり、当時の自分に言わせれば「むき出しの和音が響く姿を聴いていたかったのだ」ということなのでしょう。
そうした面でこの曲は、当時の作曲の姿勢を端的に表すものとして特徴的なものと言えます。
『Hard Worker』(1991年作曲)
これは社会人になった18歳のときの作品で、X68000の内臓FM音源、Roland(ローランド)のMT-32とU-220、KAWAI(カワイ)のK4r、そしてM3Rを使って制作されました。シーケンサーはX68000のMML環境が用いられています。
この頃になると、フュージョン系の音楽を明確に志向し始め、ゲームミュージックからの影響を織り交ぜながら、自分なりのバンドサウンドを打ち込みで表現しようと試みていました。
特にこだわっていたのがベースで、ベーシストの鳴瀬喜博氏によるチョッパーベースに心酔していた当時の私は、多くの作品でチョッパーベースを登場させており、この曲でも冒頭からチョッパーのフレーズを響かせています。
メロディーやアドリブフレーズは、好みのゲーム音楽にインスパイアされながらも、センス良く形にすることはなかなか叶わず、泥臭さが残るものになっているように感じます。
しかしこれもまた、この時期の自分にしか書けなかったものであり、紛れもない自分の音楽の姿だったのでしょう。
当時、こうして好きなように作曲していながらも、ぼんやりとしたマンネリ感が生じていたのも事実です。
この曲を作曲していたときも、悪い意味で「簡単に作れている」という実感があり、形は整っていても「熱量や熱さ」が感じられないと思っていました。
見方によっては、こうした音楽の「テンプレート」と呼べるものが出来上がりつつあったとも言えるわけですが、そういった不全感が背景にあったため、この方向性を突き詰めて突破していくということにはならず、しばらくの期間は行きつ戻りつしながら足踏みをするような状況が続くことになります。
また、この時期の作品に見られる傾向として、アレンジ面での「押し引き」が乏しいという点が挙げられます。
言い換えると、いつも全てのパートが同じように奏でられていて、メリハリがついていないということであり、どのパートもいつも頑張って演奏していて、結果として誰も目立っていない状態になりがちだったのです。
これは、「音数が少ない状況に耐えられない」という強迫的な気持ちのせいで、全体の音響的な粗密の起伏への配慮を怠ってしまっていた結果だろうと思われます。
曲名に関しては、この頃には命名への気恥ずかしさや照れが消えてきて、ストレートに表現出来るようになっていたようです。
その理由は、作曲する者としての自負心が芽生え始めた結果、照れ隠しのおふざけそれ自体が「みっともないこと」であり、リスナーを軽んじる無責任な行為であるという、そうした自覚が生まれたからだったと思います。
『Suita Junction』(1991年作曲)
これは18歳のときの作品で、前曲の『Hard Worker』と同じ楽器構成と打ち込み環境で制作されました。
フュージョン系音楽への志向は一層強まり、「生演奏を打ち込みで再現する」という方向性が明確化されていった、そんな時期に作曲された曲です。
そのせいもあってか、以前までのような「コード理論偏重によるアレンジの平板さ」 は、やや解消されてきた感があります。しかし依然としてハーモニーを設計することに囚われていた結果、本来そこにあったであろう創造的な可能性を活かせていなかったようにも思われます。
ポジティブに捉えるならば、ある制約条件の下(ハーモニー偏重)に自らを置くことで、思わぬ創造性を発現させやすくしていたと言えなくもありません。
ともあれこの曲では、アレンジ面での平板さの傾向が若干抑えられており、生演奏を感じさせるフレージングを用いながら、スペース(空間)や響きの厚さにメリハリをつけようとしている様子が伺えます。
今思うと、当時の自分もアレンジ面について色々と葛藤を感じていた、ということでしょうか。無闇に音を重ねたり音数を増やしたりするのではなく、フレーズが本来もっている説得力で音楽を満たそうと試みていたのかもしれません。
ちなみに、この曲のタイトルは大阪府にある「名神高速の吹田ジャンクション」からとったもので、当時の有名な渋滞箇所での車の往来のイメージが念頭にありました。高速道路の大規模なジャンクションが醸し出すムード、すなわち「鉄の脈動」とでも呼ぶべきものに、当時の私は強く惹かれていたのでしょう。
『Behind』(1992年作曲)
最後に紹介するこの曲は、19歳のときの作品で、前曲の『Suita Junction』と同じ楽器構成に、EMU(イーミュー)のProcussionを加えて制作されました。
前曲でも使用されていた、Rolandの拡張カードSN-U110-07によるギターサウンドが、本曲でもリードギターとして全面的に用いられています。
この頃、一世を風靡したDTM音源のCM-64をご存じの方なら、この拡張カードの存在も覚えておられるのではないでしょうか。
当時、打ち込みでディストーションギターを再現するには、ギターパートをパラアウトして何らかの外部エフェクターを通す必要があり、それは一般的なDTMユーザーには敷居の高いアプローチでした。かといってMIDI音源のプリセット音色には、満足のいくディストーションギターは用意されていませんでした。
こうした状況下、拡張カードとして登場したこのディストーションギターは、当時としてはクオリティの高いものとして歓迎されたという経緯があります。
そんなアイテムを手中にすることで、私の「生演奏の再現志向」は益々高まり、自己流フュージョンバンドの演奏の再現が、もはや目的化していきました。
ある種の技術的なフォーマットに則って、そこに自分なりのフレーズを当てはめていくような形の作曲に、知らず知らずの内に収まっていったのかもしれません。いうなれば、無自覚な「オリジナリティ喪失」の状態に陥りつつあったと言ってもいいでしょう。
その頃、ある音楽仲間からは、「これでは、ただの普通の音楽みたいだ。以前のほうが面白い音楽だった」と指摘されたのですが、今振り返ると彼は慧眼であり、率直で的確な意見をくれていたのだと分かります。
とは言え、この「生演奏の再現志向」によって得られたものや学べたことが多くあったのも事実です。
楽器と奏法への理解の深まりは当然のこととして、パソコンから作曲の世界に入ったことによる、「音楽の身体性」への自身の無理解と距離感のことを、こうした生演奏の再現を通じて痛感し学んだことは、音楽的視野を広げることにつながる貴重な経験となりました。
総括と感想
以上ここまで、10代に作曲した作品の中から特徴的なものを5曲紹介してきた訳ですが、今の自分から見ると、そこには現在にまでつながる本質的な傾向が既に胚胎されていたのだと分かります。
それは、ハーモニーへのこだわりであったり、音楽的な時間構成を設計することへの関心であったり、さらにはそれ以外の要素をそれら「ハーモニーや時間構成」に従属させがちであったり、といったものです。
技術的な巧拙や、表現方法の変化はあれども、その内奥では当初からそういった傾向が表れていたように感じられます。
こうした傾向は、作曲を始めた当初から「パソコンに演奏情報を直接入力するスタイル」で実践していたことも無関係ではないと思います。
10代の頃は、作曲に際してピアノなどの鍵盤を一切使っていませんでした。頭の中でメロディーやコード進行を考え、それをMMLの文法に沿って逐一パソコンに入力していたのです。
そもそも当時は、まだ鍵盤が弾けませんでしたので、ちょっとした試奏をするときも、いちいちMMLを入力して演奏させるというプロセスを辿る必要があり、これは今思い返すと何とも回りくどく、まどろっこしい方法だったと思います。
ですが、こうした体験を通じて、「目の前の音をよく聴く」という姿勢が磨かれた側面が確かにありましたし、さらには、楽器演奏の手癖に引っ張られることのない環境下で、脳内のイメージを丁寧に具現化するスキルも身に付けることが出来たと実感しています。
以上、思い起こせるままに述べてきましたが、これらの内容が少しでもお役に立てば幸いです。