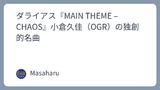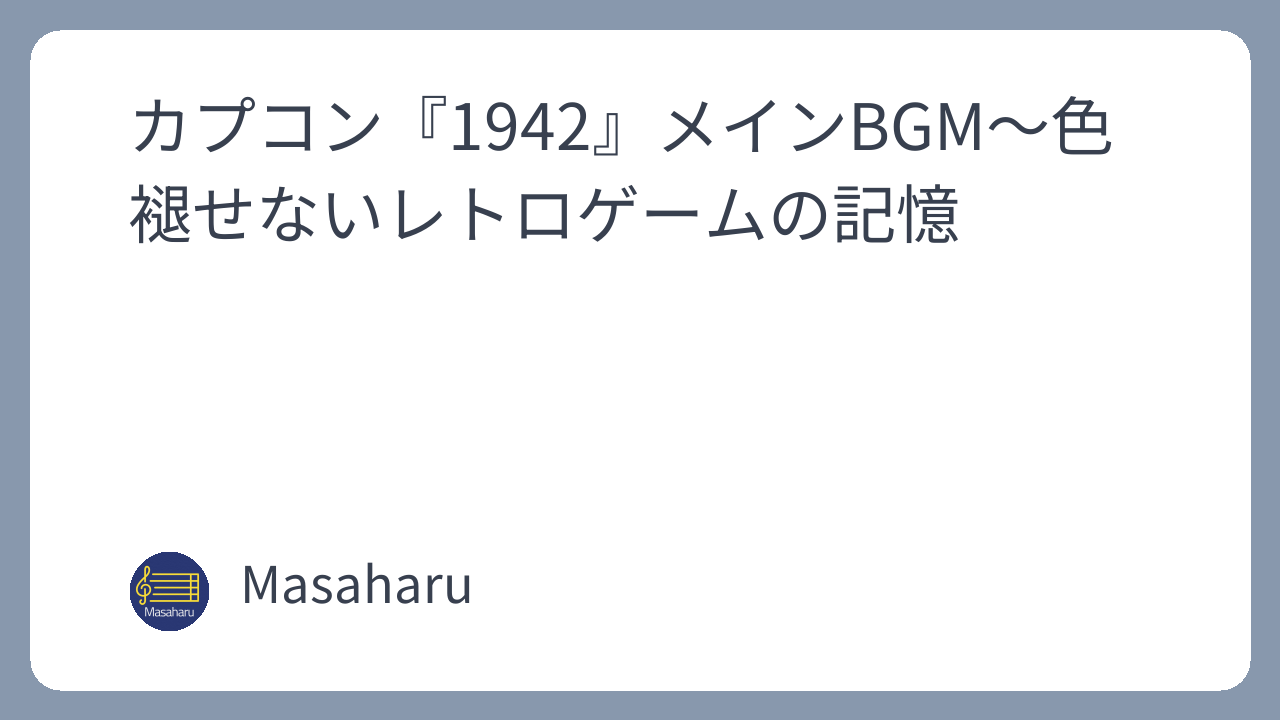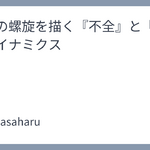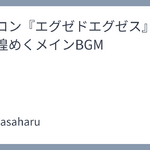子供だった1980年代、私はどっぷりとゲームにハマっていました。スーパーやデパートに設置されていたアーケードゲームに、なけなしのお金を投入して遊んでいたものです。
子供の頃から音楽が大好きだった私は、それらのゲームから鳴り響く音楽にも、たちまち魅了されてしまいました。
当時大好きだったゲーム音楽は色々ありますが、そのなかでも、なぜか印象的で耳に残っているのが、カプコンの『1942』のメインBGMです。
カプコン初期の名作『1942』
『1942』は、1984年に登場した縦スクロール型のシューティングゲームです。第二次世界大戦(太平洋戦争)をモチーフとしており、プレイヤーはアメリカ軍の戦闘機「P-38 ライトニング」を操作して日本軍と戦い、最終ステージとなる沖縄を目指します。
無敵になって敵を回避できる「宙返りシステム」や、各種パワーアップ&お助けアイテムの「Pow」といったゲームシステムは、当時、新鮮な驚きをもって迎えられました。
本作は、カプコンのアーケードゲーム第1作『バルガス』、そして『ソンソン』『ヒゲ丸』に続く第4弾であり、同社を一躍有名にした初期の名作の一つです。この成功により、カプコンはゲーム業界における地位を確固たるものにしたと言われています。
その後もシリーズ化され、『1943 ミッドウェイ海戦』『1943改』など、後に「19シリーズ」と呼ばれる人気シリーズの原点となりました。
『1942』の個性的なメインBGM
さて、レトロゲームに詳しい方なら、「1942に音楽らしいBGMってあったかな?」と思われたかもしれません。
そうです。確かにメインBGMは、いわゆる「メロディーと伴奏」というような普通の曲のスタイルをしていません。
実際には、「ノイズによるスネアドラム」と「ホイッスルの音」によるリズミックなフレーズが延々と奏でられています。
古い戦争映画の「勇ましい場面のBGM」のような、軍隊行進のマーチを思わせる、そんな曲想が『1942』の世界観に上手くマッチしています。
また、フレーズには3連符が巧みに組み込まれていたり、拍子がひっくり返ったりすること(「字足らず」のような効果)によって、コンスタントなビート感に微妙な変化が加えられているのも印象的で、そうした結果、独特の中毒性の高いBGMに仕上がっています。
それだけに、ボーナスステージのクリア時やプレイ再開時のファンファーレは、ゲーム展開の区切りとして効果的に機能していましたし、「富嶽」や「亜也虎」というボスキャラ登場時のBGMは、想像以上の緊迫感をもたらしました。
ちなみに、各ステージクリアの際に撃墜率が表示されるのですが、ここでタイプライターの音が効果的に用いられており、細やかに時代感を演出しているのが印象的です。
今でこそ、ゲーム内での音響演出への高い意識は当然のこととして扱われていますが、まだゲーム黎明期から初期の発展期に差し掛かった辺りの当時においては、技術面や環境面の制限から、トータルな世界観の実現はハードルが高いものだったように思えます。
そんな状況のなか『1942』は、統一された世界観を巧みに構築しており、この成功は後の『戦場の狼』『魔界村』などへ引き継がれていくこととなりました。
当時の思い出エピソード
さて、『1942』は難易度がそこまで高くなかったこともあり、ワンコインで割と長時間遊べたということも手伝って、当時の私は一時期、ゲームコーナーでは必ずと言っていいほどプレイしていました。
使えるお小遣いが乏しかったため、「いかに長く遊べるか」というコスパ意識でゲームを選んでいたようなところがあったので、その点で『1942』は理想的なゲームのひとつだったのです。
ゲーム好きの友人とゲーム筐体を挟んで向き合って座り、延々と『1942』ワールドに浸って楽しんでいたのは、いい思い出です。
今思い返すと、いささか単調ともいえるゲーム内容なのですが、このシンプルで特徴的なBGMと相まって、不思議な没入感を味わえる個性的なゲームでした。
関連記事