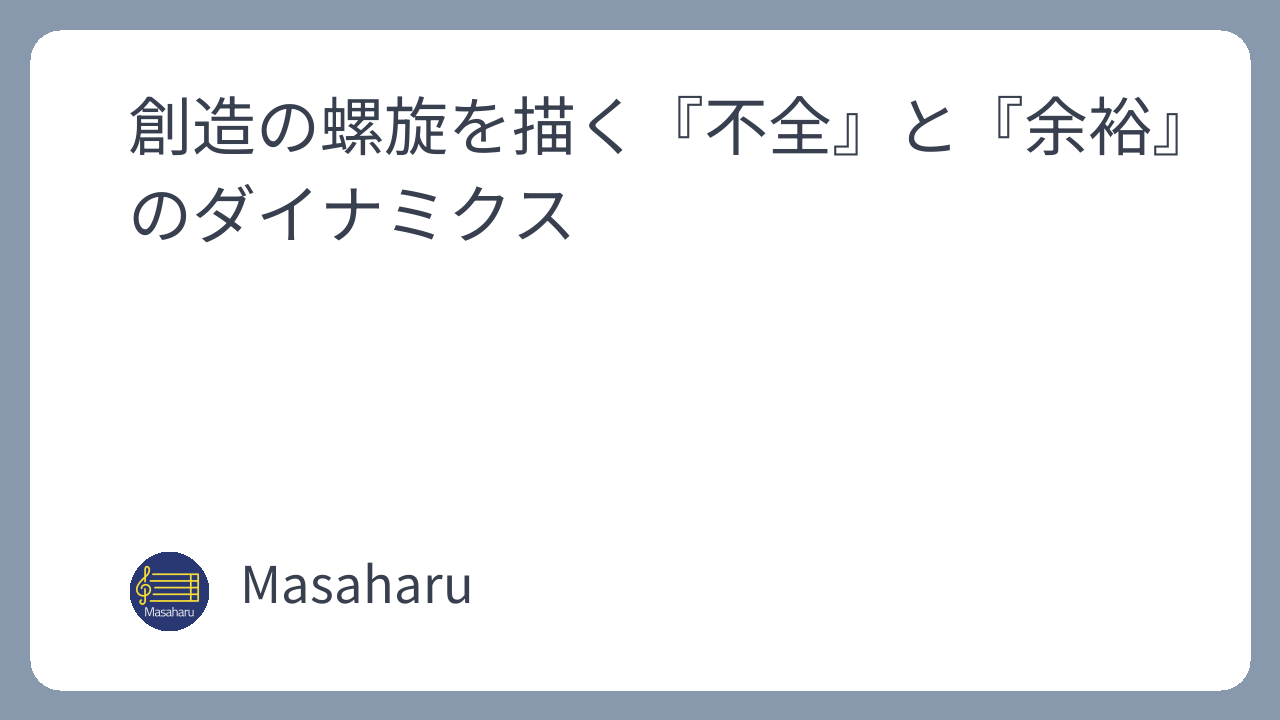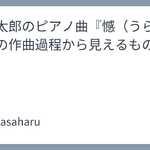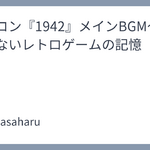私自身も含め、多くの作り手が、無意識のうちに「必死さの呪縛」に囚われているように思われます。音楽制作というものを、一瞬たりとも気を抜かず、脇目も振らずにゴールへと向かうマラソンのようなものだと捉えてしまっていないでしょうか。
もしそうだとすれば、それは「必死で一生懸命に取り組み続けること」が作品の質に直結するという、ある種の思い込みから来ているのかもしれません。
とは言え、この「必死さ」を、一概に否定すべきものとするのは早計ではないか、という思いもあります。
むしろ必死さは、創造のサイクルにおいて不可欠な、ある一時期の「不全」の表出であり、その後に訪れる「余裕」と相互に作用し合うことで、より高次の創造へと至るダイナミックなプロセスを構成しているのではないかと思うのです。
そこでこのエッセイでは、必死さの根源にある「不全」の時期を「創造の吸気」として捉え、対として生まれる「余裕」を「創造の呼気」として定義してみます。そして、これら二つの状態が織りなす『創造の螺旋』のダイナミクスについて、内省的な視点から考えてみます。
『不全』という吸気──音楽的真実への没入
作り手における創造のサイクルは、まず「不全」という感覚から起動すると思われます。
ここで言う「不全」とは、単なる能力の欠如を指すのではなく、「いま目の前にあるもの(現在の自分)」と「理想として思い描くもの(未だ見ぬ音楽)」との間に存在する、埋めがたい知的・感性的な隔たり、あるいは満たされない渇望のことです。
新しい音楽的着想や、未だ見ぬ音楽のフォルムに挑む際、作曲者は必ずと言っていいほど、自己の能力の不十分さや、構想が現実の音として結実しないことへの焦燥感を覚えます。この内面的な状態こそが、私たちが音楽制作に「必死」になる瞬間の核心を成しているのではないでしょうか。
「必死さ」は確かに精神的な負荷を伴いますが、同時に、私たちを次の段階へと押し上げる推進力として機能するものだとも言えるでしょう。「未だ見ぬ音楽」を求める渇望に突き動かされ、音の羅列の向こうにある音楽的真実を探求する──そんなプロセスの背景には、こうした「必死さ」が伴っているものなのでしょう。
こうした「不全」の時期は、音楽的な「吸気」と呼べると思います。
外部からの様々な要素を貪欲に取り込み、内側へと蓄積していくこと。それは、ハーモニーにおける一つの和音が持つ多義性を探ることや、フレーズの表情付けにおける感情の最も精確な表現を求めること、そしてリズムの微細な揺らぎに生命を吹き込むことなど、それらに向けられた徹底した内向的集中を意味しています。
この「不全」な探求の時期を経なければ、私たちは新しい知覚や、独自の音楽的表現に辿り着くことは難しいのではないかと思います。
『余裕』という呼気──統合と客観的な眼差し
必死な探求の時期を終え、一度作品から距離を置くことで、作り手は内面に「余裕」というスペースを生み出すことができます。この「余裕」こそが、バラバラだった断片を有機的に結びつけ、一つの音楽的フォルムへと昇華させる力になると思います。
例えば、この「余裕」を生み出すためのプロセスの一つとして、かつて私が「作曲中の曲と遠足へ行く」と表現したような時間の過ごし方があります。これは、制作環境から一時的に離れ、別の視点を得ることで、内省を深め、作品に対する客観的な視点を取り戻しつつも、より深く作品と向き合う──というアプローチです。
他にも、散歩に出たり、全く別の芸術に触れたりする、そんな一見無駄や遠回りに思える時間が、実は内面の「余裕」を育み、作品全体に新たな風を吹き込むための「呼気」として機能するのではないでしょうか。
この「余裕」の時間は、単なる休息や逃避ではありません。それは、制作中に意識の前面に現れなかった断片的な知識や経験が、水面下で統合されるための知的スペースです。
創作の熱狂から一歩引いて全体像を眺めたり、手を止めて制作中の作品と改めて対話することによって初めて、「音と音の間に存在する沈黙」や「表現の余地」といった、必死な状態では見えなかった「余白」の価値に気づくことが出来るように思われます。
そして、この「余裕」の極地にあるのが、「人間の有限性を認めること」や「完全や理想に到達できないことを理解した上で、なお努力を続ける姿勢」といった思いを背景とした、ある種の諦念とでも呼べるものではないでしょうか。
それは言うなれば、完璧な作品を求める呪縛から静かに解放される態度です。
「この作品は完璧ではないが、今の自分が出し得る最善である」と判断し、作品を世に出す健全な姿勢。この「諦め」は、決して創造性の放棄ではなく、作品を過剰に神聖化することなく、次の創作へと向かうための新たな出発点となるように感じます。
『創造の螺旋』を描く
結局のところ作り手にとって創造とは、「不全」という吸気と、「余裕」という呼気という二つのフェーズを繰り返す、螺旋状のダイナミックなプロセスなのかもしれません。
私たちは、「不全」な状態の中で新しい知や技術を貪欲に吸収し、その後に訪れる「余裕」の中で、それらを統合し、客観的に評価するのでしょう。
このサイクルを繰り返すことで、私たちは単に技術を向上させるだけでなく、内面の知的・感性的な成長を遂げ、より深みのある作品を生み出すことができるのだと思います。
このプロセスは、終わりなき高みへと向かう螺旋のように、目には見えなくとも着実に続いていくものなのでしょう。
関連記事