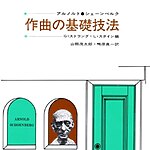(初出2002年4月8日)
監修者曰く、本書は「テクノロジーと表現、テクノロジーと文化、テクノロジーと人間や社会との共時的、通時的な関係を、音楽をモデルとして横断的に探求することを目的としたアンソロジー」とのことです。なにやら取っ付き難そうな印象を与えそうですが、その内容は「テクノロジーは、社会における音楽にどの様な影響を与えて来て、またどの様に変化させて行くのか」を俯瞰しようとするものです。
音楽というものはテクノロジーに大きく依存した表現だと言えます。特に現在のポップ、クラブシーンで聴かれる音楽が百年前に成立し得たかどうかを考えると、録音技術や再生技術、また流通機構のテクノロジーはもちろんのこと、その作曲の方法自体がテクノロジー無くして生まれ得なかったことに気付きます。
本書の論考のひとつ「私にとっての機械仕掛けの神、または単なるツールボックス」の執筆者であるイオス・スモルダースは、次の様に言います。
われわれが置かれている環境の中でさまざまな手助けをしてくれる機械に、われわれは以前にも増して依存する様になっている。機械は、構成と制作を手助けしてくれるだけではなく、結果にも影響を与えている。新しい道具は、新しい生産物を生むのだ。 (p188)
なおかつ、音楽というものは原則的には聴くことなくして存在し得ず、その聴くという行為にもテクノロジーの影響が色濃く現れているのです。今でこそ「持ち運べる音楽」は当たり前ですが、本書の言葉を借りれば「百年前には演奏者が前にいないと音楽が聴けなかったというのは信じがたい」というくらい、聴くことのスタイルはテクノロジーによって変化しています。
それから又、音楽を集団性・イベント性といったものを剥奪した形で、つまりレコードやCD等のパッケージとして個人が享受するようになったのは最近のことであり、それはテクノロジーの存在無くしては有り得なかったことです。そして、そのことによって音楽の意味の多くが「差異」に取って代わられ、商品化されて行くことに繋がって行くのですが、この話しは別のコラムにて。
さて、話しを作り手側に戻しましょう。かつてはピアノの改良と弦の材質の変化によって、ピアノ曲の表現が変化したという歴史がありました。鉄が多く使われ、弦の張力に耐え得る構造となることで結果として音量・ダイナミクスが増大し、表現の幅が広がったのです。これも広い意味でのテクノロジーの影響と言えるでしょう。
しかし、現代におけるテクノロジーの影響は、作曲スタイルそのものに大きく及んでいます。例えば、80年代に現れたブレイク・ビーツを基調とするハウス・ミュージックは、コンピュータの発達に伴うデジタル録音&波形編集のテクノロジー無くしては生まれ得ず、それらテクノロジーは現在の音楽制作の基本技術のひとつとして、もはや欠くことの出来ないものとなっています。スモルダースの言う依存の対象とはこういったものです。
ここで重要なのは、録音や編集というテクノロジーそのものの是非ではなく、それが作曲行為と渾然一体となっているということです。つまり、どの様な音を出すのかを波形レベルでコントロールするということが、ある種の音楽においては作曲に含まれる様になったのです。任意の時間の切り貼りを行って、録音の対象が元々持っていたコンテクストを解体し、その結果を直ちに耳で検証しながら新たな加工を行ったり、そもそも音をゼロから生成したりすることが作曲そのものとなったのです。
これらのテクノロジーの基本自体は、実はその数十年以上前から現代音楽の分野において、電子音楽作曲と言う形でコンセプチュアルに取り扱われ実践されてきたものでもあります。しかし、当時はそれら機材を誰もが利用することは叶わず、広く人々の創作意欲にアピールすることが出来なかった上に、そもそもテクノロジーが未熟でその先の可能性が見え難かったことが、一般化しなかった理由でしょう。そしてそのことが、テクノロジーと音楽との関係を反対側から照らし出している様にも思います。
パーソナルに、お手軽に、新種のハサミを試してみる様に、テクノロジーを手段として(その明確な自覚を伴わずに)扱えるようになって来た現在、改めて作曲への視点を再検証することが価値あることなのだ、とスモルダースは語っている様に思います。
関連記事