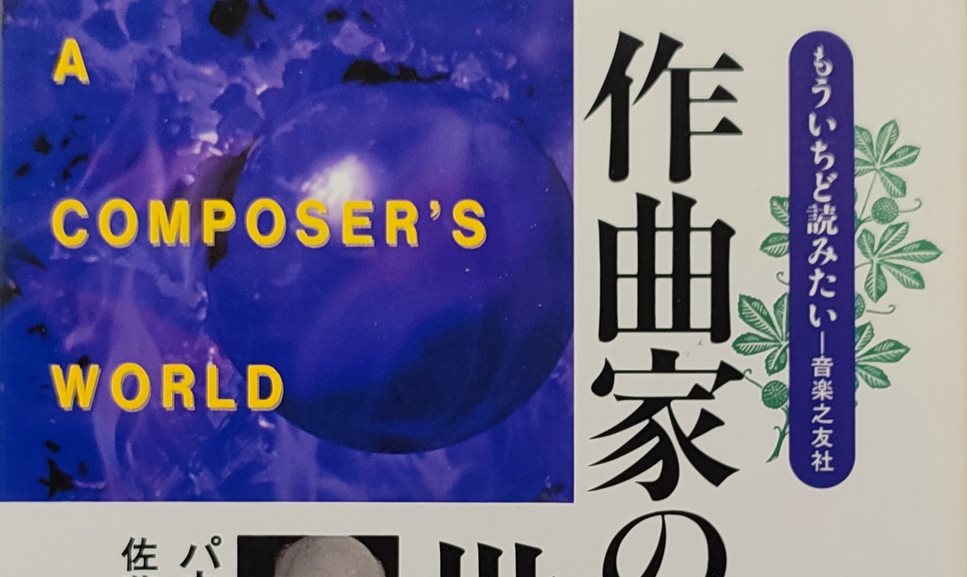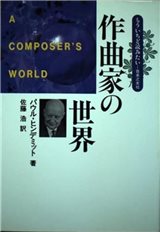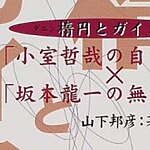(初出2002年4月9日:追記2025年5月31日)
ドイツの作曲家ヒンデミットによる、自らの音楽論・作曲論を自伝的な要素も含めつつ書かれた一冊です。原書は1952年に英語版として出版されたもので、ハーバード大学での講義録をもとにして書かれました。時代背景などの面で古さを感じさせる面もありますが、作曲する者としての思いが書かれたその内容は大きな価値を持っています。
作曲家にとって音楽的霊感とは何なのか、作曲の素材の持つ意味とそれがもたらすものについて等、音楽の哲学的基盤から作曲家の倫理的責任、そして実践的な作曲理論に至るまで、かなり踏み込んだ部分まで作曲の内実について語られています。
本書自体が日本国内で再版されたものであり文章が翻訳調で硬く、また当時の音楽産業や思想哲学のことなどの背景知識もある程度必要とされるため、初心者にはお勧めしにくいですが、今なお一読に値する一冊だと思います。
◇
著者のヒンデミットは、作曲家として残した数多くの作品と共に、教育者としての活動が思い起こされます。自らの信じる音楽の姿を追い求め、またそれを広めようと腐心した人生だったと言えるでしょう。当時の音楽を取り巻く状況に対する強い危機感と、音楽が本来あるべき姿への回帰を願う彼の切なる想いがありましたが、それは当時の世間とはズレが生じてしまう結果を生みます。
著者が生きた20世紀前半は、彼から見ると、音楽が大量生産され、商業的な成功や安易な娯楽へと傾倒していく時代として映りました。彼は、そのような風潮が音楽の本質を蝕み、作曲家の地位を貶めていると感じていたのです。
いうなれば「音楽の麻薬的側面(快楽的享受)」ばかりを追い求める世間の風潮に対しては、さぞかし苦々しい思いをしていたことでしょう。そして現代に著者が現れたとしたら、その風潮がある種のジャンルにおいては純化され、独自の音楽スタイルとして存在していることに驚いたのかもしれません。
また、音楽が専門化し、作曲家と一般の聴衆との間に溝が生まれていたことも、著者が問題視していた点です。著者はその溝を埋め、聴衆が音楽の創造過程を理解し、音楽をより深く享受できるようになることを意図すると共に、作曲家の側からアマチュア演奏家へ向けた作品作りを通じて芸術としての音楽を広く伝えていくことが大切だと訴えます。
著者は、作曲家がなすべきこととして「絶え間ない娯楽への渇望がもたらす害悪を確信させることで、消費者をより高いレベルに引き上げる」ことを主要な目的として厳しく定義しています。この主張の背景には、当時の音楽言説や音楽消費のあり方に対しての強い批判的意識があったと言えます。そしてその厳しさは、音楽が単なる娯楽産業の一部として消費される現状への警鐘の表れであり、作曲家が果たすべき社会的・倫理的責任を強調するものと捉えられるでしょう。
さて本書では、そんな著者の苦々しさと希望の双方が顔を見せながら、作曲行為の内実と言えるようなものについて言及しています。そこでは「インスピレーションあふれる神秘的な作曲」という甘い幻想のベールを剥ぎ取るような勢いが感じられ、とても興味深く思えます。そこで示される著者の音楽哲学は、実践的かつ根源的であり、音楽を深い精神的な営みとして捉えていることが伺えます。
「第一章 哲学的考察」では、ボエティウスやアウグスティヌスといった歴史上の学者たちが音楽をどのように定義したかを論じています。ヒンデミットは、アウグスティヌスとボエティウスの思想を「音楽の基本的な、不変の価値」として自身の音楽哲学の基盤に据えています。
そして、ボエティウスの思想からは「音楽の力、その倫理力(エートス)が私たちの心に作用する」ことを、アウグスティヌスの思想からは「私たちの心が音楽を吸収し、それを道徳的な強さに変える」ことを取り上げて強調しています。これは著者が、20世紀の多様な音楽スタイルや実験性の中で、音楽の持つ普遍的かつ不変の価値を再確立しようとする試みと言えるでしょう。
著者は、音楽が「感覚的なものを精神的なものへ、人間的なものを神的なものへ」と変容させることを追求すること、そしてそのために「最も精妙で目に見えない素材」を用いると論じています。この主張は、音楽を単なる娯楽や知的な活動の域を超え、精神的、道徳的な高揚をもたらす力として位置づけていることを示していると思われます。
さらには、音楽の創造において「知的作用」と「情的反応」が密接に結びついていると説き、感情の動きを音楽の創造の源泉として認めつつも、それが無秩序に表出するのではなく、論理的な思考と技術的な規律によって統御されるべきだと主張します。
また「第二章 音楽における知的作用」で著者は、作曲家も演奏家も聴衆も、技巧や成功や快楽の奴隷になってはならないこと、その上で彼らが音楽の上で立派に自らの目的を達しながら、しかも地上のすべての業の空しさを知ること、その時にこそ彼らは音楽の不朽の価値に貢献するにふさわしい者となるのだとし、これこそが音楽に対する真の知的態度だと語ります。
続く「第三章 音楽における情的反応」では、音楽が引き起こす感情は、直接的な感情そのものではなく、「感情の記憶」であると述べています。これは、音楽が感情そのものを「表現」するのではなく、聴き手の内面に存在する感情の「イメージ」や「記憶」を呼び起こすという、著者独特の音楽観を示しており、その音楽哲学の核心の一つと言えるでしょう。
ヒンデミットのこうした音楽哲学は、技術的な側面だけでなく、作曲という営みの本質について改めて考えさせられるきっかけになるのではないでしょうか。
書籍情報
『作曲家の世界』の目次
- はしがき
- 第一章 哲学的考察
- 第二章 音楽における知的作用
- 第三章 音楽における情的反応
- 第四章 音楽的霊感
- 第五章 作曲の素材
- 第六章 技術と様式
- 第七章 演奏家
- 第八章 楽器について
- 第九章 教育
- 第十章 実際面
- 第十一章 環境
- 訳者解説/新装版によせて
著者について
パウル・ヒンデミット
世界的に有名な作曲家であって、1895年にドイツのハナウで生まれた。彼は間もなくドイツの第一流の若い作曲家として認められたが、それにも拘らず、非ドイツ的な作品を書いたという理由で、公に弾劾された。彼は管弦楽、吹奏楽、合唱、独唱、室内楽、バレエ、及び歌劇のための作品を書いている。彼はまたドイツ語及び英語の何冊かの楽理書の著者である。現在(*当時)彼はイエール大学の楽理教授であるが、同時にスイスのチューリッヒ大学の音楽教授として隔年に講義を行っている。(本書より引用)