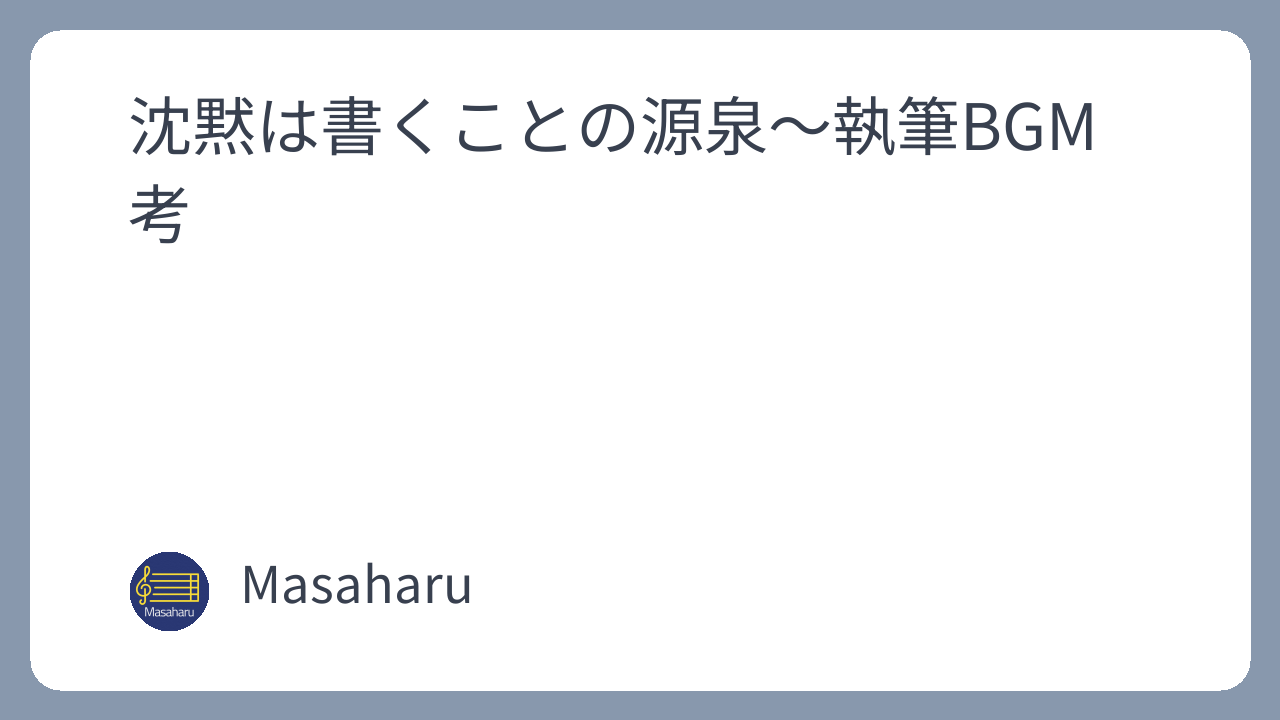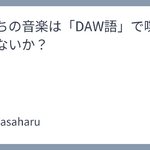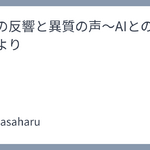自分と向き合って文章を書くときには、私は音楽(BGM)を流しません。イヤホンもせず、ただ部屋の静寂の中に身を置くことが多いです。
特に「歌詞のある音楽」を避けていますが、これは、言葉を紡ぐという行為が、別の言語体系、すなわち歌詞という「意味」と干渉して思考のチャンネルを混乱させてしまう──そんな個人的な実感があるからです。
しかし、この「BGMのない静かな環境」で執筆するという選択は、単にノイズを排除する消極的な行為ではありません。むしろそれは、これから書かれるべき文章の「音楽」を聴くための、とても能動的で、そして不可欠なプロセスであるように思うのです。
少々大げさに語るなら、執筆時の部屋に満ちる沈黙は、単なる「音の不在」ではないということです。その沈黙は、これから生まれる文章の「旋律やリズム」、そしてまだ言葉にならない「予感やひらめき」を聴き取るための、特別な空間だと言えます。
ジョン・ケージの『4分33秒』という作品があります。演奏家は4分33秒間、一切の楽器を演奏しないという、センセーショナルな作品です。
この作品が示唆したのは、無音という「音の不在」そのものではなく、その時間の中で聴衆が耳にする周囲の環境音や、あるいは自分自身の心臓の音、呼吸の音といった「内なる音の存在」であり「聴くことの能動性」でした。
このようにケージは、沈黙を通じて私たちに「聴くこと」を再認識させました。
私の執筆における「沈黙の環境」も、これと相似した機能を持っているのではないかと思います。
書くという行為は、誰かに語りかけるための言葉を作り出す(探し出す)だけでなく、自分自身の内側から湧き上がる声に耳を澄ます営みでもあります。
思考の断片、記憶のざわめき、感情の揺らぎ。まだ論理的な構造を持たないそれらの「ノイズ」の中から、文章の核となるべき「旋律」を拾い上げる──。このプロセスは、まるで未だ見ぬ音楽の断片を探して戯れる作曲家のそれとよく似ています。
私は以前、『作曲を見つめる~作曲行為を理解するための仮説モデル』のなかで、創作におけるひらめきを「創造性の種(たね)のようなもの」と書きました。それは言うなれば、まだ具体的な音符にはなっていないが、何かを形にしたいという漠然とした衝動、あるいは「こうあるはずだ」という確信めいた感覚といえます。
執筆の場においても同様、この「たね」は言葉として表現される以前の、より根源的な「意味」の断片であり、執筆のすべての出発点になり得るものです。
言うなれば執筆時の無音とは、この「内なる音楽」と、これから紡がれる文章の「輪郭」や「響き」を感じ取るための、優れたレコーディング・スタジオなのかもしれません。
執筆時に音楽(BGM)を避けるのは、この「内なる音楽としての言葉」と「外から聴こえてくる音楽」、そして歌詞のある音楽ならば「歌詞が持つ意味と構造」とが、互いに干渉し合うのを防ぐためです。
本来なら、私にとってこれらは異なる意識のチャンネルで処理されるはずのものです。しかしBGMという「外から侵襲してくる音楽世界」(及びその歌詞という「言語世界」)によって、これらは混線してしまうわけです。
そんな状況において沈黙は、「言語」が持つ純粋な響きを取り戻すための、一種の「リセット」機能として働きます。それは言葉の海へ漕ぎだす前の、静かな準備と調整の時間なのです。
沈黙は、決して空虚なものではありません。それは創作において、自己の内奥に深く潜り、まだ音になっていない「音楽」を聴き、まだ言葉になっていない「文章」の予感(創造性の種)を受け取るための、特別な空間です。
このように、執筆を始めるときに無音の中で佇むこと──それは、新たな文章が生まれる前の静寂であると同時に、これから始まる文章という「音楽」の、最も重要な第一音を聴くための時間なのだと言えます。
私たちの心の中には、常に「創造という音楽」が鳴り響いているのだとするならば、執筆という行為は、その内なる音楽を言葉という形で可視化する試みとなります。そして、その試みは沈黙という舞台装置があって初めて、その真価を発揮するのだと思うのです。