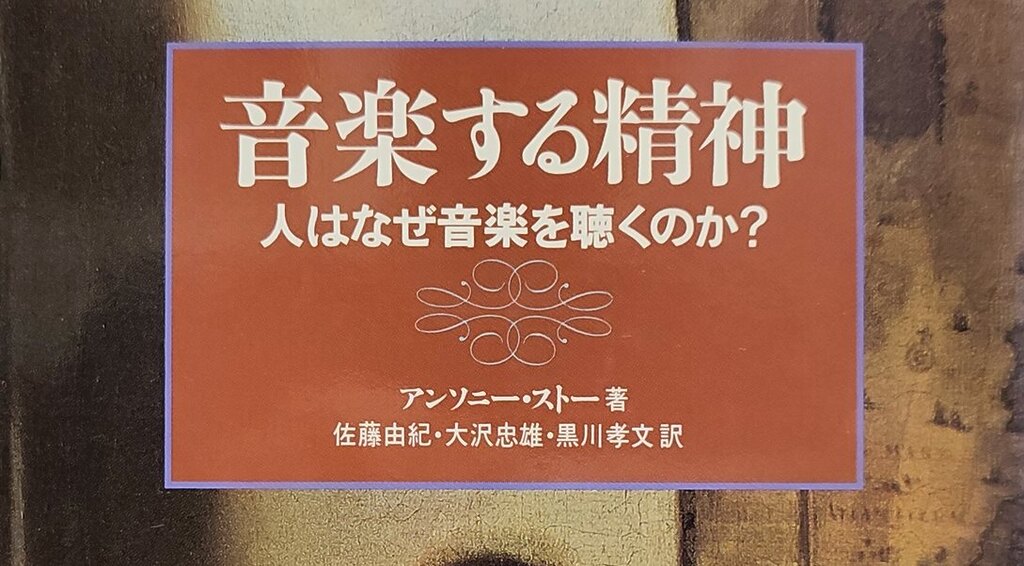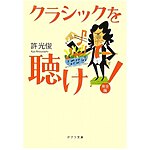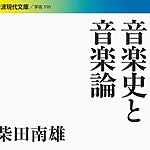(初出1999年12月8日)
世の中には自然指向と言える様な、人工ではなく自然から生まれたものの方が価値があるとする見方があります。そして、音楽の世界にもその価値体系があります。厳密には「自然現象に依拠したものに価値があるとする」と言うべきでしょうか。それは「自然倍音列」を中心とした価値体系のことです。
楽典や理論書を開けば、その冒頭には大抵、自然倍音列による和音の発生根拠や、五度の優越性といったことが記されていると思います。これは、逆に言うならば、自然倍音列という「音に自然と備わる性質」に依拠した西洋音楽システムというものはその成り立ちからして自然の法則を顕わした素晴らしいものであるということを、自然現象によって立証しようとしているとも言える訳です。
自然は偉大なものであり、そこから導き出された(発見された)ものに対して畏敬の念を抱くことは人間として「自然な」感覚だと思います。ですが、西洋音楽が果たして自然現象に依拠したものなのかということについては、多いに疑問の残るところです。
例えば、第七倍音の捉え方の問題がありますし、ハーモニーとしての三度音程の響きの一般化は人類の歴史から見て「けっこう最近」だという事実もあります。また、今日において純正律の長三度は人工的な12平均律に慣れた耳には調子外れに聞こえるという、言うなれば「人間の耳が自然に反している」かの様に見える問題等など、自然という視点から見ると次々と疑問点が浮かび上がってきます。
この様な問題に対して、何とか整合性を取ろうとする立場もある様ですが、事態の説明という域を出ていないと思われます。しかし、音楽にとって自然の法則であるかどうかということは、そもそも重要なことなのでしょうか。
音楽は音から出来ています。物理現象としてはそうです。そこで、音を調べれば音楽の秘密に迫れると考えたとしても無理はありません。当然、音は自然現象ですから、そこから様々な法則が発見されて行きます。
しかし、音楽とは物理的に客観的に存在するものではなく、聞き手の内に発生するもの(私は”聞き手の感性の中に在る”と捉えています)だと考えると、「音の法則や性質」と「音楽現象」との間には直接何らかの法則を介して関係しているのではない様に思えてきます。
つまり、音楽が人の外側に物理現象として在るのなら、音を調べることが音楽を知ることに繋がるでしょうが、音を聞いて音楽だと感じるかどうかが聞き手に委ねられているのならば、音という現象と、音楽という現象とはその現われ方において異なっていると考えられないでしょうか。
音(空気の振動)は自然から生まれましたが、音楽(と感じる現象)は、人が(即物的に言うならばは脳が)もしくは心が生み出したのだと考えられないでしょうか。例えば、言語が概念の表現・伝達・共有を目的としてコミュニティー内で発展・発達していく様に、音楽も「何か」の表現・伝達・共有を目的として或るコミュニティー内で発展・発達してきたのではないかという訳です。
ちなみに、違うコミュニティー間においては、言語通訳の様な困難はあってもそれなりの音楽的理解は可能だと思われます。しかし、本質的「気分」は伝わってきても、それを意識する段階で違ったものに感じるのかもしれません。このことの例としては、東南アジア音楽に触れた西洋人のことを想像してみると良いのではないでしょうか。
さて、この様に考えてみると、そもそも、ひとつの理想の存在(自然性)への距離を問題視することの目的は何処にあるのか、ということを見つめ直した方がいいように思えてきます。西洋音楽のこの傾向に対して、著者で精神医学者のアンソニー・ストー氏は次の様に語ります。
自然が根源的であり、かつ良いものであると信じている人にとって、その人を育み豊かな経験を与えてきた音楽システムが、そのほかでもない自然により密着して派生したと確信することは満足を与える。これは自然を神の地位にまで引き上げる。それはまるで敬虔なキリスト教徒が、なるほど神は存在するのだという証拠を見出しただけでなく、キリスト教の神に対する考え方が唯一正しいということを立証する証拠まで示すことが出来たようなものである。
音楽という音(空気の振動)を観察した結果の説明としてそれらの法則が適用出来ても、聞き手の内の音楽現象には適用し得るものなのでしょうか。「音楽は自然の法則か」という表題に答えるとするならば、まず「音楽が自然の法則である必要があるのか」と問い返すことから始めねばならないのではないでしょうか。
音楽がその表現上、音として聞き手の耳に届く以上、作り手は音の法則や性質の影響を受けることから逃れられません。しかし、その音をどう感じるかが音楽現象なのだとすれば、その先において音の法則は「ものさし」以上の意味を持たなくなってしまうことになるでしょう。合理的な説明は可能であっても、それはどこまでも「音としての音楽」の説明に留まるのではないでしょうか。
関連記事