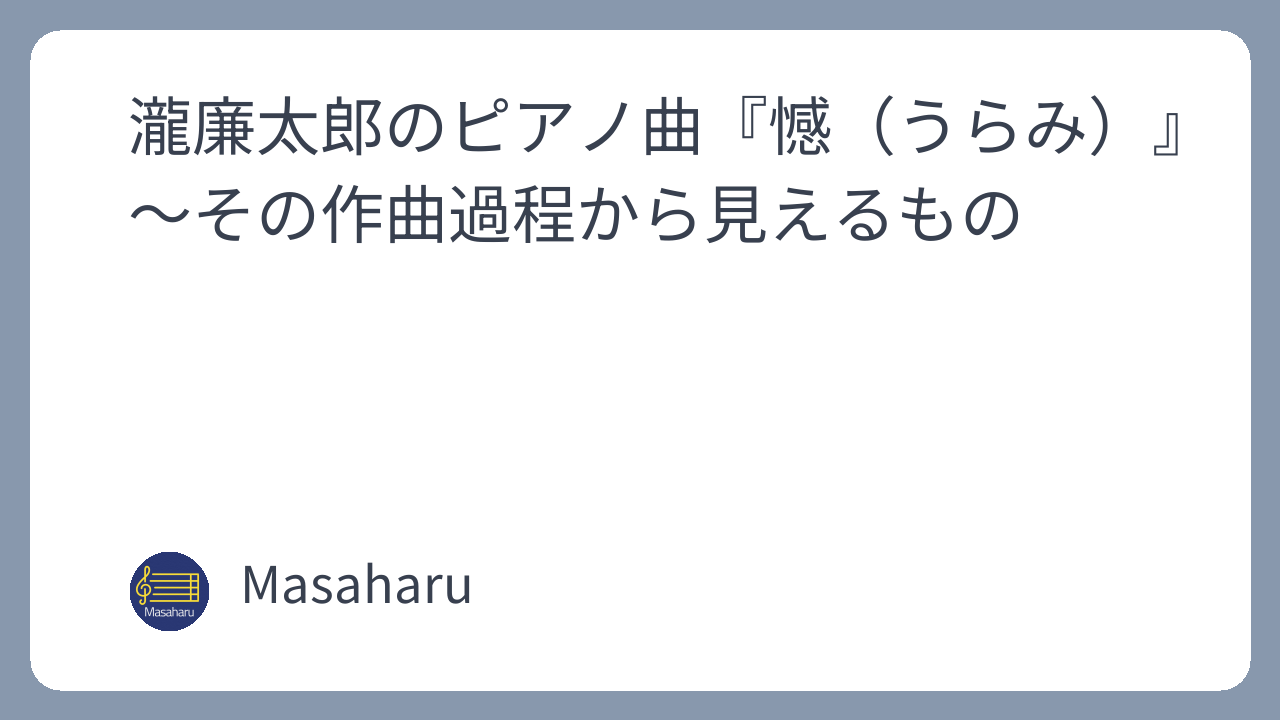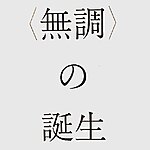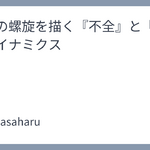瀧廉太郎は、音楽の授業で耳にしたこともある『花』『荒城の月』『箱根八里』などを作曲した、日本の西洋音楽の黎明期における代表的作曲家です。
瀧は、留学先のライプツィヒ滞在中に発症した結核によって、23歳という若さで亡くなったのですが、当時の結核についての一般認識とその偏見のためか、残念ながら多数の自筆譜が焼却されてしまったそうです。
そんな中、現存している作品の多くは歌曲ですが、2曲だけピアノ曲があり、そのひとつが『憾(うらみ)』です。
留学先からの帰国後に作曲されたこの作品は、その無念と嘆きの思いを背景に書かれたものと言われています。
『憾』は、日本人が作曲した本格的なピアノ曲として、また、留学経験を持つ瀧が、西洋の作曲技法を駆使して書いた最晩年の作品として、日本のピアノ音楽史の出発点の一つと見なされています。
ピアニスト清塚信也氏による演奏をお聴きください。
無念さ、痛切さ、悲嘆、さらには諦念。どのような言葉をもってしても尽くせない瀧の思いが、音楽作品として表現されていることが伝わってきます。
絶筆となったこの曲には、23歳の若き瀧の感性と持てる技術のすべてが注ぎ込まれているのだと思うと、襟が正される気持ちになります。
『憾(うらみ)』の自筆譜が発見される
2019年、大分県で『憾(うらみ)』の自筆譜が発見されたというニュースが流れました。東京音楽学校時代の滝廉太郎の親友、鈴木毅一氏の遺品のなかに、その自筆譜はありました。
この発見は、単に失われた資料が見つかったというだけでなく、作曲家としての瀧廉太郎の創作プロセスに新たな光を当て、彼の人物像をより深く理解する手がかりとなりました。
見つかったのは、『憾』の異なる3つのバージョンを含む自筆譜です。これらの自筆譜からは、瀧がどのように音を構築し、作品を完成させようとしたかという、その過程が浮かび上がってきました。
そこで見えてきたのは、病に蝕まれて負の感情の赴くままに書くのではなく、論理的かつ技術的に音を組み立て、己の求める美しい響きの世界を生み出そうとしていた姿でした。
この発見された自筆譜について、ピアニストの喜多宏丞氏による分析動画が公開されています。
この分析動画では、エンディング部と中間部において、自筆譜に記された日付をもとに、実際に瀧が推敲したプロセスを追いながら『憾』の魅力に迫っています。
また、瀧がピアニストでもあったことが伺える、そんなピアニストならではの繊細な推敲も取り上げられており、最終稿では冒頭の和声の厚みが若干増やされていることが明らかにされています。
更に詳細な分析は、喜多氏によって論文としてまとめられており、下記リンクから読むことが出来ます。
さて、この『憾(うらみ)』というタイトルは、一般的に「無念」や「心残り」といった悲劇的な文脈で解釈されてきました。しかし、自筆譜が明らかにした緻密な推敲の跡は、この解釈に新たな視点を提供するものと思われます。
瀧は単なる悲嘆に暮れていたのではなく、自身の内にある複雑な葛藤や感情を、西洋音楽の技法を用いていかに表現するかという、そんな「芸術的な課題」に最後まで向き合っていたと考えられます。
これは、彼の音楽が単なる西洋の模倣ではなく、日本人としての情感を西洋の形式に昇華させようとする、とても能動的な探求であったことを物語っているのではないでしょうか。
そして、分析動画で喜多氏が述べているように、「よい音楽を創りたい」という音楽家としての在り方の前では、自身の無念の境遇とその嘆きの感情すらも音楽表現の題材としてしまう、そんな冷徹な強さを、瀧は若くして持ち得ていたのだと思われます。
瀧を語る際には常に言われることですが、この才能が病に襲われずにいたならば、その後どのような音楽が生み出されていたかに思いを致さずには居られません。
現存するもうひとつのピアノ曲『メヌエット』や、歌曲『月』、無念の帰国後すぐに作曲された『別れの歌』『水のゆくへ』など、瀧の才能と可能性を感じさせる曲の数々に、あなたも触れてみて下さい。