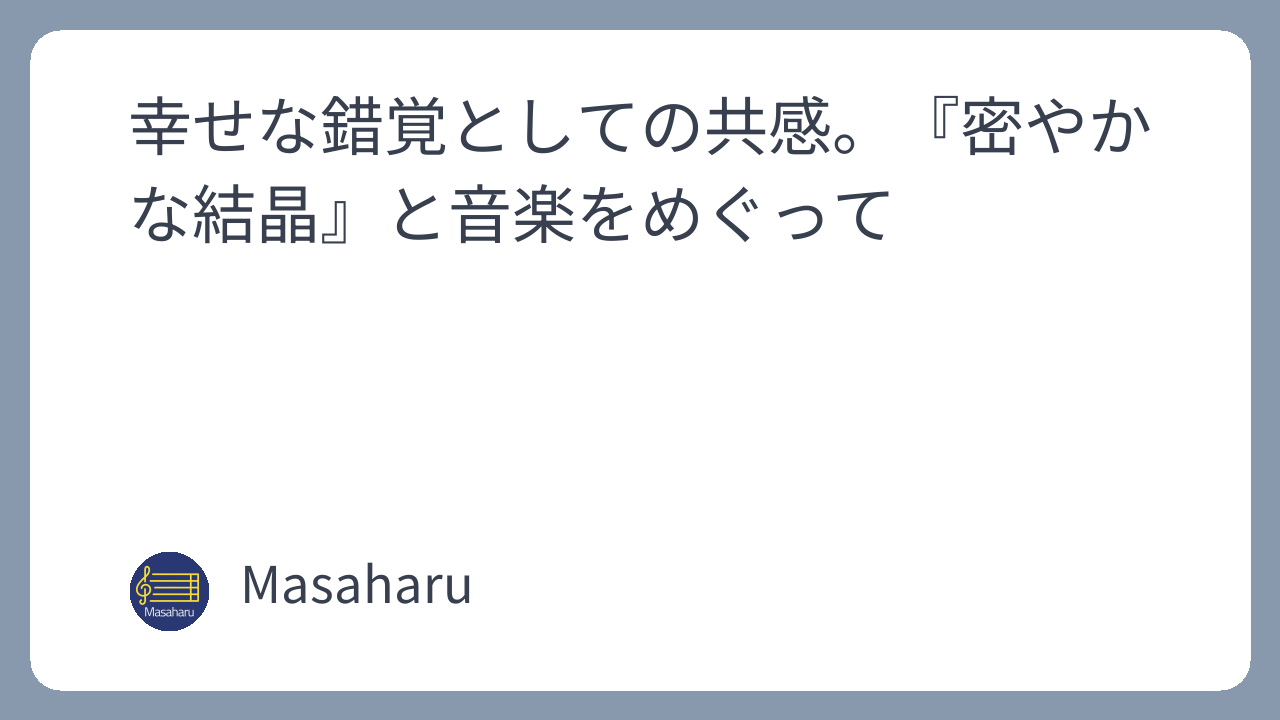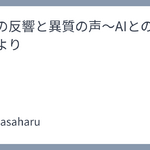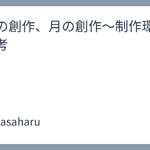先日、小川洋子氏の『密やかな結晶』を読み終えました。
その読後感は、私にとって少し特別なものでした。物語の人物に強く感情移入したわけでも、情景を鮮やかに描き出したわけでもなく、ただ淡々とストーリーを追うことに夢中になった――そんな静かな体験でした。
それでも満たされた気持ちになったのは、最後のページを閉じたときに「この物語世界の全貌をつかめたような気がした」からです。いうなれば「静かな確信」を覚えたのです。
しかし、それはおそらく「幸せな錯覚」に過ぎないでしょう。なぜなら、この物語の登場人物たちでさえ決して完全には理解していないであろう世界を、第三者である読者が完璧に把握できるはずがないからです。
思い返してみると、私が感じた「全体像」とは、作者から与えられたものというよりも、自分自身の記憶や経験、感情が物語の断片と共鳴し、補い合うことで浮かび上がったものだったのだと思います。
いわばそれは、私の心の中に密やかに結晶した像です。その瞬間に生じた満足感は、私自身の内面が関与したからこそ得られたものだったのでしょう。
この読書体験は、私が思い描いている「音楽における共感のメカニズム」(※関連記事参照)と響き合うものがあるように思います。
一般に、音楽の共感とは「作曲家の感情や意図を、聴き手がそのまま追体験すること」だと理解されがちですが、しかし実際には、作曲家の完全な意図を知ることはできませんし、それを確かめる方法もありません。
それにもかかわらず、私たちは音楽を聴くとき、自分なりの全体像を描き出し、そこに共感を見出します。
音楽は時間芸術であり、その全貌を瞬時に把握することはできません。しかも、楽曲の中にある「休符」や「余韻」といった空白は、リスナーに能動的な想像力を促します。もし音が途切れることなく隙間なく詰め込まれていたら、それは情報の奔流となり、もはや意味を持たないノイズに近づいてしまうでしょう。
そして、音が途切れる瞬間、私たちは自らに問いかけます。「次に何が現れるのか」「ここにどんな意味を見出すのか」と。そのとき私たちは、自らの感性を用い、そして環境音や過去の記憶さえ呼び起こしながら、自分だけの音楽の像を結晶させていきます。
この過程は、小説の行間に「見えない言葉」を読み取ろうとする営みにも似ています。作曲家が意図的に、あるいは偶然に残した余白が、リスナーの感性を呼び覚まし、リスナー自身の手で「全体像」が再構築されるのです。
こうして成立した像は、厳密にいえば作曲家の設計図そのものではありません。しかし、それを「私にとっての真実」として受け入れるとき、私たちは確かに共感を経験していると言えます。
それは錯覚と言い得るものかもしれませんが、むしろその「幸せな錯覚」こそが、芸術を体験する醍醐味のひとつではないでしょうか。
私は『密やかな結晶』を読み終えたときの「静かな確信」を、そんなふうに理解しています。作者の意図を完全に理解したのではなく、作品に触れることで自分自身が意味付けを行い、その結果として「自分にとっての全体像」が結晶したのです。だからこそ満足感が訪れたのだと思います。
そして、これは作曲においても同様です。素材を選び取り、配置し、音楽としての流れを形づくること。その過程には作曲家自身の感性と意思が介在しています。そうして立ち現れたものは、リスナーの側においてまた別の「全体像」となり、両者の関係性の間で新たな共感が生まれるのだと言えるでしょう。
結局のところ、読書も音楽の鑑賞も、そして創作も、すべては私たちが「意味を与えたい」という根源的な欲求に突き動かされた営みなのかもしれません。そして、その営みが(幸せな)錯覚であるにもかかわらず、人と人とをつなぎ、作品を時代を超えて生き続けさせる――それは、芸術の不思議で尊い力なのではないかと思います。
関連記事