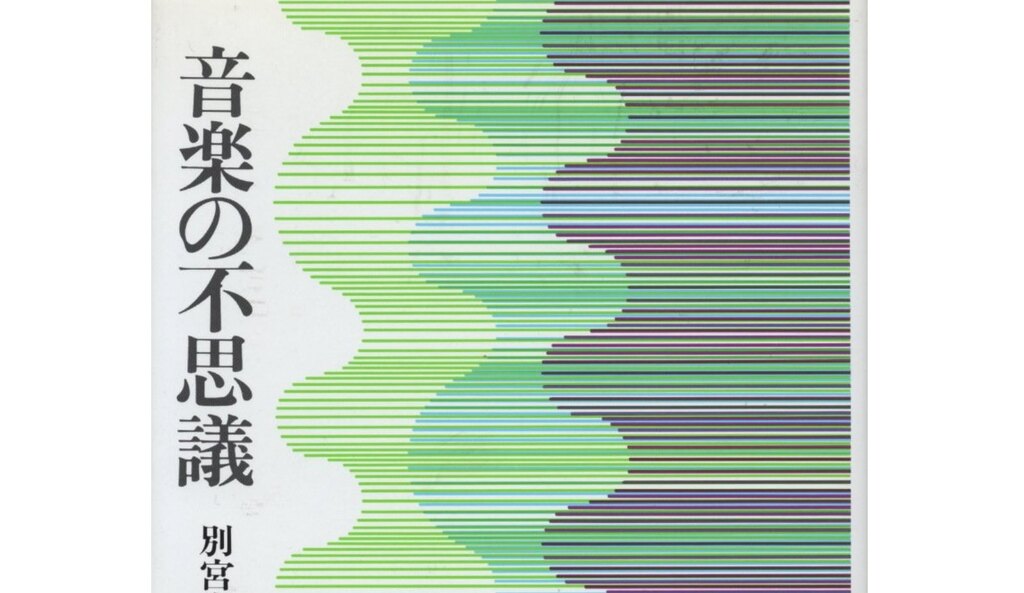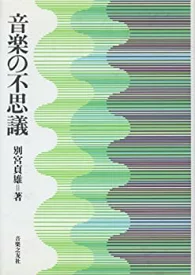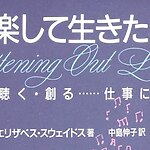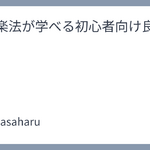(初出2002年4月9日)
『私は、ただ音楽をつくるだけでなく、同時に、「一体音楽とは何なのか」「自分は何のために作曲をするのか」等々、考えなくてはいられないたちであり、そのような発言をし、また文章に書いてきた』──自らそのように述べる著者による音楽評論の名著です。
その中の印象的な一節を紹介します。「(個性/独創性の追求がもたらす問題に対し──)芸術にとってまず大切なのは、普遍的な美であり真実であって、個性を通じてしかそこに到達できないのは、われわれ人間が肉体をもって、個々の人間にわかれているためにおこる宿命的に必要なことに過ぎないのである。それなのに個性を究極の価値の如く思い誤ること、これが『解決』をさまたげている原因なのだと私は思う。」
本書は1971年に出版されたものですが、当時の前衛音楽への著者の懐疑的な姿勢が見て取れる文章もあり、時代の証言として貴重なものになっています。著者自身、シェーンベルクたちの天才性を認めつつも、ウェーベルンを教祖のごとく崇める作曲家たちの作品に見られる「思弁的傾向」や「知的遊戯の傾向」には全く同感できないと述べており、さらに軽井沢で開催された現代音楽祭で登壇した討論会の様子を通じて、芸術としての音楽への思いが描かれています。
そんな著者の価値観が伺える一文として、次のようなものがあります。「芸術家は、とかく芸術を社会的な事象からはなして純粋なものと考えたがるものであり、孤高をたもって妥協を嫌うものではあるが、根本において芸術は社会と離しては考えられないものだと私は思う。」そして、さらに芸術をコミュニオンに模して捉えながら、(宗教的な意味を持ち得るとするならば)創作というものが単なる物づくりではなく、人間の芸術創作は神の世界創造の一端を担うこととさえ考えられなくもない、と述べています。
◇
不躾な物言いで恐縮ですが、別宮貞雄という人は音楽に対して本当に真摯で正直な人なのだと思います。別宮氏の音楽を聴いたときに思ったことなのですが、そこには作者が聴いている音楽世界を偽ることなく表現しているような、ある種の純粋さを感じさせるものがあったのです。
本書の語り口も同様に、いたずらに難解な表現や、言葉のための言葉、概念のための概念という悪癖に陥ることなく、終始平易です。作曲経験のある読者は、まるで昼下がりにお茶を飲みながら会話に花を咲かせているような、そんなリラックスした印象を本書に持たれるかもしれません。
私も、「別宮さんもそう思っているのですか。私もそう思っていたのです」という無言の会話がよく交わされたものでした。本書が永らく版を重ねてきた理由の一端を垣間見る思いです。ですが、最近の出版業界の事情からか、取り扱わなくなった書店が増えているのが残念です。
書籍情報
『音楽の不思議』の目次
- 第一部 音楽の不思議
- 第一章 絶対音感と相対音感(上)
- 第二章 絶対音感と相対音感(中)
- 第三章 絶対音感と相対音感(下)
- 第四章 音階(上)──旋法──
- 第五章 音階(中)──ピタゴラス音階/音名と階名──
- 第六章 音階(下)──十二平均律──それは合理主義の産物か
- 第七章 調性の確立とその行方
- 第八章 音色
- 第九章 ピアノの音色
- 第十章 リズム
- 第十一章 空間的表象化──テンポというもの──
- 第十二章 構造(上)──その造形美──
- 第十三章 構造(下)──その静力学と動力学──
- 第十四章 音楽は何かを表現するか
- 第十五章 情報理論──電子計算機による作曲──
- 第十六章 音楽とスポーツ
- 第十七章 付随音楽と劇音楽
- 第十八章 何によって人の心を動かすか
- 第十九章 個性 独創性 民族性
- 第二十章 作曲家 演奏家 聴衆
- 第二十一章 私
- 第二部 音楽を求めて
- 自然科学志望者より / 師ダリウス・ミヨー / ヨーロッパで学んだこと / 私の音楽美学ノート / 軽井沢現代音楽祭──道場破りの記── / 電子音楽についての疑問 / 蕩児は帰郷するであろう──私の現代音楽観── / オリヴィエ・メシアンにおける人間の研究 / 芸術と科学──音楽の場合── / 批評の倫理 / 芸術における模倣と想像──模倣の効用と限界── / 現代日本人にとっての宗教音楽 / 現代日本における作曲諸様式の運命について
著者について
別宮貞雄(べっく さだお)
1922年東京に生まれる。1946年東京大学理学部物理学科卒。1950年同大文学部美学科卒。1951~54年パリ留学、ダリウス・ミヨーに師事。毎日音楽コンクール第一位、毎日音楽賞、尾高賞、芸術祭賞などを受賞。現在中央大学教授、桐朋学園音楽部講師。(本書より引用)
関連記事