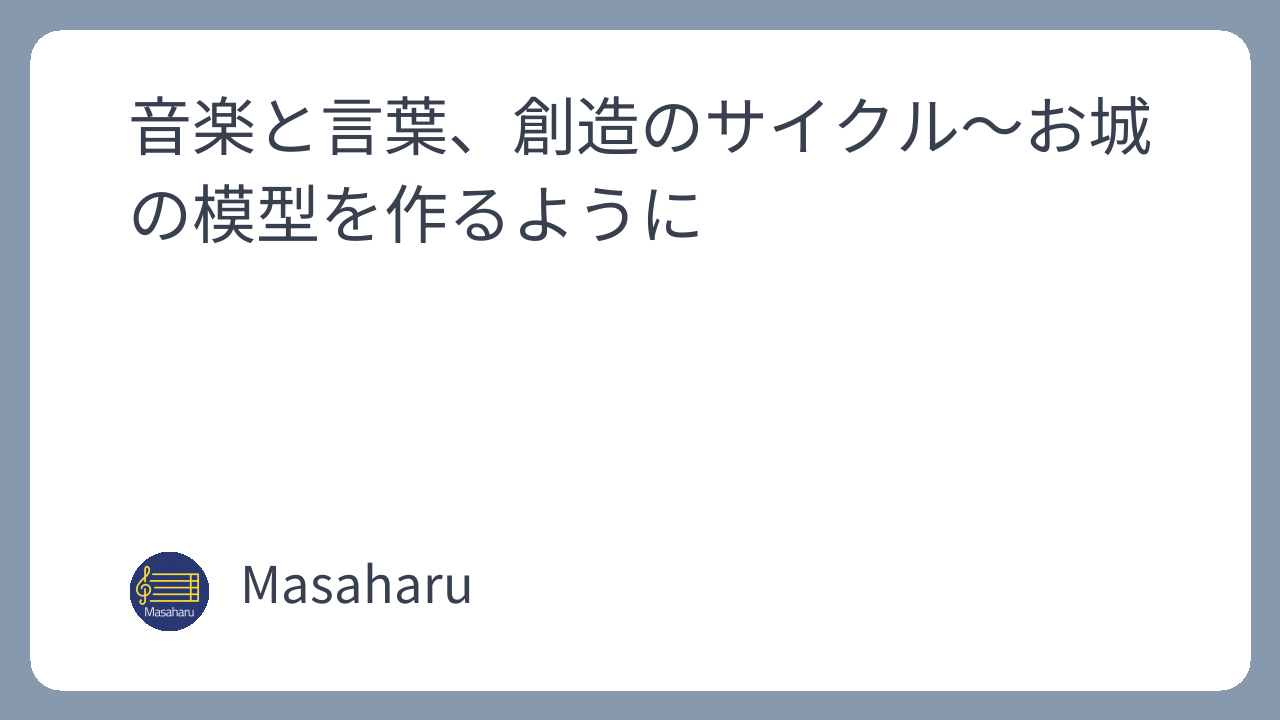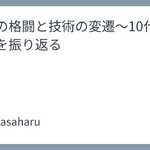音楽をつくる者が「音楽についての文章」を書くとき、そこにはどんな思いがあるでしょうか。
私の場合は、音楽という本質的に言語化し得ないものの前に立った時に感じる、その変換不可能な強い力を知るからこそ、あえて言葉を紡いでいるようなところがあります。
それは例えるなら、まばゆい光そのものを掴もうとするのではなく、その光が生み出す影の輪郭を丹念になぞろうとする行為に似ていると思います。
音楽とは何か。作曲とは何か。こうした問いを立てて言語化しようとすることによって、逆説的に「音楽そのものの非言語性」を認めざるを得ない地点に立たされます。私の「音楽に関する文章」は、音楽という巨大な存在の淵に立ち、そこで描き出された似姿や抽象化されたスケッチとして綴られたものと言えるかもしれません。
かつてヴィトゲンシュタインは「語り得ぬものには沈黙せねばならない」と述べました。ですが、芸術人類学者の中島智氏が示唆するように、私たちは語り得ぬものに沈黙すると共に、「語り得ぬものの語り得なさ」について言語化することが出来るのではないでしょうか。
沈黙の淵に立ち、なぜそこが淵なのかを問い、語ること。それもまた、創作に携わる者のひとつの誠実な態度なのではないかと思います。
私にとって、作曲を通じて得られる音楽体験は、そのどうしようもない音楽の力とクオリア(質感)を実感させられる無二の体験です。その体験に触発されて紡がれる言葉は、言わば二次創作のような性格を帯びます。
そうやって生まれた文章は単に音楽に従属するものではなく、ましてや音楽を変換したものでもなく、例えるならそれは、音楽という惑星の引力に捉えられながらも自らの軌道を描く「衛星」のような、独立した創作物とも呼べるものでしょう。
こうして、この言語化という行為は、いつしかそれ自体が私自身の創作行為のひとつとして成立していくことになります。音楽に耳をそばだて、じっと眼差し、そこから生まれた言葉を組み合わせ、まとめていきながら、ひとつのオブジェとしての文章を構成(作曲)していく訳です。
作曲すること、文章を書くこと、そして、これらの創作行為によって創り出されたものを自らの人格のもとに集積し、ひとつのフォルムを形作ること。こうした営みは私にとって、創作活動全体を象徴する「お城の模型」を作り上げていくような感興に満ちたものだと言えます。
そのフォルムの細部に宿る美意識と執着心、全体の調和と歪み、そのフォルムによって喚起される独自のクオリア──そういったものが立ち現れそして味わえる、このメタな創作活動に魅力を感じています。
さらに考えてみると、これは「自己の創作プロセスを外部から観測するシステム」を、自らの手で構築していると捉えることが可能でしょう。つまり、音楽と言葉という質的に異なる表現が組み合わされることで、それは、自己の創造性を高めるための「観測実験装置」になり得るのではないかということです。
この装置の中には二人の自分がいます。ひとりは、音楽を作曲する「実践者」、もうひとりは、その実践者の振る舞いをメタな視点から観察し、記録し、次の創作の行く先と糧を探る「観察者」です。
すると、このシステムが生命体のような様相を呈し始めていることに気付くことでしょう。生物学でいう「オートポイエーシス(自己生産)」の概念がしっくりくるかもしれません。
音楽を作るという実践が、例えば「何を作ったのか(これは何なのか)」という言語化への問いを生みます。そして「言語化する」という観察行為が、自己を客観視させ、次の音楽を生むための新たな視点やエネルギーを供給することに繋がっていきます。
私の中では、音楽は言葉を導き出し、言葉は音楽制作の土壌を豊かにする肥しとなり得ます。こうした循環によって、このシステムは自らの構成要素を生産し続けており、それは自律的に駆動する生命体のようでもあります。
そして「生命体」という比喩が示すように、そこには「健康状態」の良し悪しが存在しています。具体的には、私の場合、観察者としての言語活動に傾倒し過ぎている時期は大抵、不健全な感覚を覚えます。
そうした感覚の自覚は、システムの根源的なエネルギーであるはずの実践(音楽制作)が疎かになっている状況へのアラートなのだと考えられます。
つまり創造的なエネルギーが循環していないことへの注意信号です。創造的自己のポテンシャルを活かせていないという、もったいなさのような居心地の悪さであり、システムの血流が滞り、生命力が失われかけているサインということです。
やはり私は、何よりもまず音楽と向き合い、それを具現化する者としてありたいと願っていますし、それが自分なりの価値の届け方だということです。ですから、実践を伴わないまま言葉だけが尽くされていく状況に陥ると、どこか空虚さを感じてしまいます。言い尽くされた言い方ですが、批評家である前に実践家でありたいということなのでしょう。
このような感覚と想いは、私自身の創作におけるひとつの大切な軸なのだろうと思います。だからこそ、生み出されるものと語られる言葉との間に大きな隔たりが生まれてしまうと、そんな自分に一種のもどかしさや違和感を覚えてしまうのかもしれません。
と同時にその視線は、常に自身に向けられ続けているのであり、「言葉を尽くす自分が、実践者としての自分から離れていないか」という問いかけが、常に内なる他者性(審判の目)となって私を支え、かつ戒めているのだと思います。
もちろん、創作の過程では誰もが立ち止まり、悩み、言葉の森に深く分け入る時期があるのだと思います。それは決して無駄な時間ではありませんし、我が身を振り返ってみてもそう思えます。
ですがその上で、「吟じない詩人」や「描かない画家」といった在り方にロマンを見出すよりも、たとえ拙くとも、少しでも何かを生み出すという実践の側に身を置いていたいという願いを持っています。
──このようにして思考を言語化していくこと、それ自体が私の創作システムの一部であり、こうした在り方に対する「健康診断の仕組み」でもあります。そして今も、観察者としての視線が、文章を綴る自分を眼差しているのを感じます。
今回述べてきたことは、恐らく多くのクリエイターが感じたことのある内容だと思いますが、こうして改めて自分なりに言語化をすることによって、自身の在り方がまた少し明瞭になった感があります。
言葉の海での思索の時間は、私にとって、次の創作と自己メンテナンスのための大切な土壌ですが、創造の循環を澱まさないためには、それも含めて全体を攪拌し続けるイメージを持つことが重要なのだろうと思います。