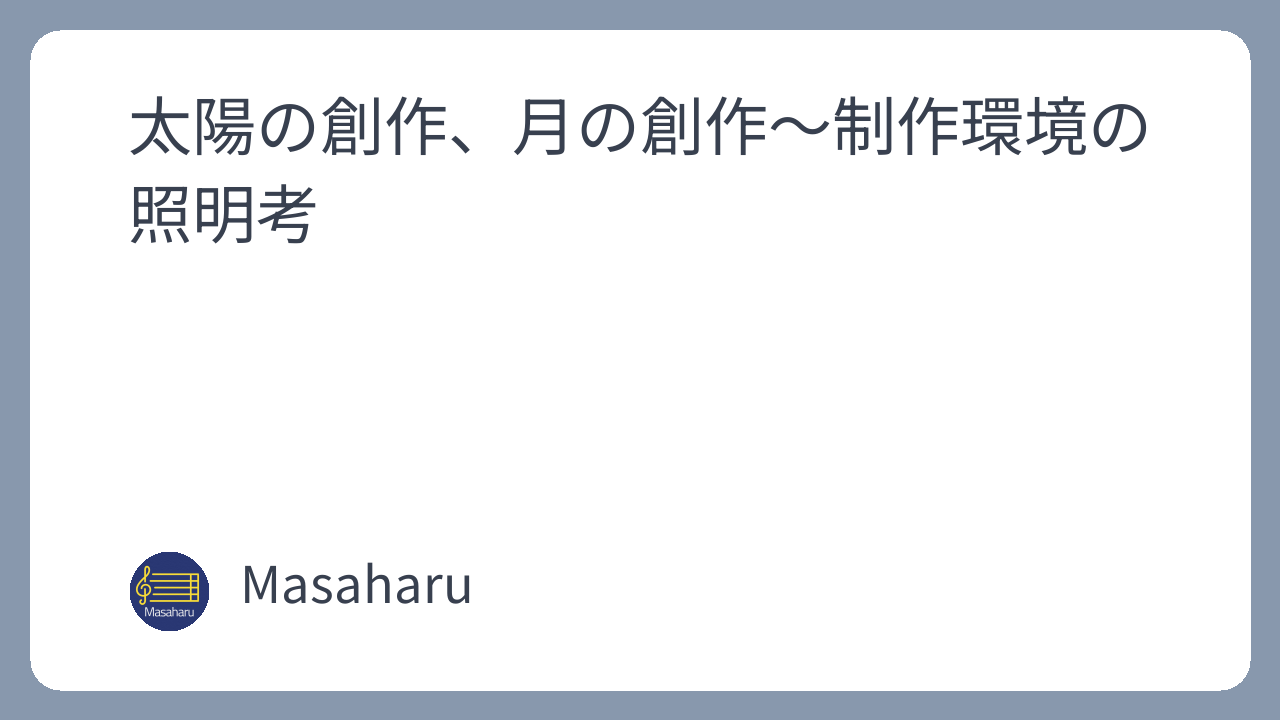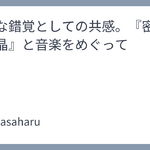部屋を明るく照らす「照明の色」には、勉強や読書に向いた青白い「昼光色」、日中の太陽光と同じ「昼白色」、そして電球や焚火のようなオレンジ色の「電球色」があります。
そして私のプライベートスタジオ兼書斎では長年、「昼白色」の照明を使っていました。
特に深い意図があったわけではありませんでした。当時、引っ越しを機に、新しい生活のスタートを切るにあたり、単に「日中と同じ、活動的な光のもとで過ごす」という漠然としたイメージで選んだだけという感じだったのです。
そしてその色を、新しい季節の始まりに太陽の下で動き始めるような、心機一転を促す象徴のように感じていたのだと思います。
しかし、その明るさとは裏腹に、意識に明確には浮かび上がってこないレベルでの違和感が、長い年月に渡ってじわじわと蓄積して来ていたのかもしれません。
無自覚ながらも、集中力の散漫や慢性化した疲労感、それに伴う精神的な健全性への影響、もしかすると漠然とした焦燥感といったものも頭上を漂っていたのかもしれません。
そしてある時、無意識からの声が届くようにして、ふと、以前住んでいた部屋の光景が脳裏に蘇ります。
そこに灯っていたのは、昼白色とは対極にある、穏やかな電球色の光でした。夜の闇の中に、ほのかなオレンジ色の温かさが滲み出る、あの静謐な光景です。焚火の色、ろうそくの色。それは、太古から人間が親しんできた、夜の安心と内省を象徴する光です。
私は何かを確かめるような気持ちで、昼白色の照明を外し、電球色の照明へと付け替えてみました。
その瞬間、部屋の空気は一変します。光の色が変わることで、物理的な空間だけでなく、自分自身の内面までが、まるで「元の場所」に戻っていくかのような感覚が生じました。
例えるならば、散らばっていた精神の破片が、磁石に引き寄せられるように一つにまとまり、当時の思考の輪郭が浮かび上がってくるような感覚です。文字通り、「自分の巣の中で落ち着き集中している自分」を再発見したような思いです。
この体験は私の中に、ある種の二元論のイメージをもたらしました。
昼白色の光が象徴するのは、まさしく「太陽」による創作です。それは外に向けてエネルギーを発散し、客観的な論理や構造を構築することに長けている、そんなイメージを抱かせるものです。
緻密な設計、複雑な構想、それらを突き詰める作業には、この光がもたらす「緊張」と「発散」が適しているのかもしれません。それは、外的な評価や、他者との関係性の中で、自らの作品を位置づけようとする姿勢にも通じるでしょう。
一方で、電球色のオレンジの光が象徴するのは「夜」による創作であり、これを太陽と対置するならば「月」による創作といえます。これは、自身を外部の情報や喧噪から引き離し、ひたすら内面へと深く潜っていく、そんな「沈思と覚醒」を促すイメージです。
そして私の創作活動の多くは、この「月」の下で育まれてきたものだったと、今にして思います。
「孤独」や「内省」というキーワードは、これまでの私の創作や音楽論において、常に重要かつ核心的な位置を占めてきたと言えます。それは単なる精神的な傾向からだけでなく、物理的な環境、つまり「光の色」によっても規定されていたのかもしれません。
夜の中で、電球色の光を頼りに、内なる記憶や感情と対話する時間。それは、世間の喧騒や、他者の視線から解き放たれ、自分自身とのみ向き合うための、ひとつの厳粛で静謐な舞台装置だと言えます。
今回の一件は、「太陽による発散と緊張」よりも「月による沈思と覚醒」が自分にとって大切だったのだと、改めて実感した出来事でした。
「創作を振り返り、原点に立ち返ること」とは、単に過去の技術や手法をなぞることに留まりません。自分を育んだ光の色、そしてその光が呼び覚ます内面的な風景を再発見する旅によっても、それは為され得るのでしょう。